イギリスならだれでも知っている子供の本、Cat in the Hat。この著者ドクター・スースの書いた、Oh the Places You will Go.という本があります。
本自体は素晴らしい前向きな本で、大学に入学する子供たちに送ったりするのにぴったりな内容なんですが、この中にThe waiting place とい場所が出てきます。落ち込んでスランプに落ちて迷い込む誰も行きたくない場所。
簡単な英語なのでそのまま載せます。
THE WAITING PLACE
by Dr. Seuss
Waiting for a train to go or a bus to come,
or a plane to go or the mail to come,
or the rain to go or the phone to ring,
or the snow to snow or waiting around for a Yes or No
or waiting for their hair to grow.
Everyone is just waiting.
Waiting for the fish to bite
or waiting for wind to fly a kite
or waiting around for Friday night
or waiting, perhaps, for their Uncle Jake
or a pot to boil, or a Better Break
or a string of pearls, or a pair of pants
or a wig with curls, or Another Chance.
Everyone is just waiting
これを思い出したのは、今日つくづく、私って待つのが苦手だなあって思ったから。別に電車を待つとか信号が変わるのを待つとか、そういう「いらち」という意味じゃないんですが、もっとストレスフルな意味で。誰かの返答とか、結果とか、何かが届くのを待つとか、誰かの決断とか。
本当にドクター・スースの言うように、待ってる状況って嫌ですね。身動きが取れなくて、気持ちを切り替えて他のことに集中するのも難しく。その待っている内容をいろいろ想像したり、最悪の事態を考えたり。遅れていると、なんで遅れているんだろうとか思ったり。
この本のほうは、この後前向きに話が向かっていき、また下降し、でも最後はやっぱり前向きに終わるという話(っていうか、詩というかなんちゅうか)です。久しぶりに読んでまた感動しました。(全編3分くらいで読めます。)
ではこちらもよろしくお願いします
2018年5月3日木曜日
書道と俳句
毎週水曜の夜、隣町の小学校でヨガを(大人に)教えています。
今週行くと、ドアの向こうにこんなものが貼ってありました。ちょっとピンボケだけど、見えます?日本の書道みたいなもの、「朝」と「強」です。字の感じ(下手さ)からして、イギリス人の生徒か先生が書いたみたい。
何か、文化とかアートの時間にやったのかな。
うちの子供たちが小学生のころは、書道はやらなかったけど、俳句はやりました。
俳句って言っても、要するに17シラブルの短い詩というだけなんですが、イギリスでは実は結構知られていて、特に子供にとっては短くて簡単でとっつきやすいし、小学校で俳句を授業で作ったり するそうです。
チャーリーも昔俳句を作りました。
今週行くと、ドアの向こうにこんなものが貼ってありました。ちょっとピンボケだけど、見えます?日本の書道みたいなもの、「朝」と「強」です。字の感じ(下手さ)からして、イギリス人の生徒か先生が書いたみたい。
何か、文化とかアートの時間にやったのかな。
うちの子供たちが小学生のころは、書道はやらなかったけど、俳句はやりました。
俳句って言っても、要するに17シラブルの短い詩というだけなんですが、イギリスでは実は結構知られていて、特に子供にとっては短くて簡単でとっつきやすいし、小学校で俳句を授業で作ったり するそうです。
チャーリーも昔俳句を作りました。
Charlie’s Haiku
The Bat
While little wings
beat
Like a scuttling
little mouse
It flies through
the sky.
Cats
It cutely meows
While making a
giant mess
Like a little bear
The Deer
Hunters are
running
While the deer is
hiding
Like the mice in
holes
The Daisy
The Daisy is small
But only comes out
in spring
Like the springy
lambs
なかなか俳句らしいですが、17音節かどうか、なんかよくわからないな。
ではこちらもよろしくお願いします
2016年10月13日木曜日
おめでとう、ボブ・ディラン
春の阪神、秋の村上春樹なんて言われてますが、今年はボブ・ディランだったんですね。こんな偉大な人に対し一介のファンが言うのもなんですが、嬉しかったです。
私がファンになったのは15年くらい前かな。なんとなく安売りしてたのでFreeWheelinのCDを買い、しばらくしたら取り付かれるようにそのCD以外聞きたくないほどになってました。
その頃かな、ボブ・ディランについての詩を書きました。何かの文学賞に応募して、第2次だか第3次だかの予選に通過して、評論も送ってもらいました。詩のブログの方に載せましたが、この機会にこちらにも載せておきます。
微笑まないユダヤ人
神をチャネルする
それほどの才能のあることの
それほどの前が見れることの
責任をあなたは負わない
逃げよ
つかまらず
ただ自由であることを証明するだけのために
自分の声で自分の歌を歌い続けるために
自分の歌を自分のものとし続けるために
愛を歌わず
反戦を掲げず
時代を代弁せず
歌わないために
笑わないために
語らないために
走り続けよ
評論家もファンも
誰も追いつけないスピードで
変わり続けよ
批判され続けよ
失望させ続けよ
裏切り続けよ
あなたが潔く捨てていくものを
振り返らずに
踏みにじっていくものを
拾い上げることで
私たちは魂の枷を少しだけゆるめる
ではこちらもよろしく

イギリス(海外生活・情報) ブログランキングへ
私がファンになったのは15年くらい前かな。なんとなく安売りしてたのでFreeWheelinのCDを買い、しばらくしたら取り付かれるようにそのCD以外聞きたくないほどになってました。
その頃かな、ボブ・ディランについての詩を書きました。何かの文学賞に応募して、第2次だか第3次だかの予選に通過して、評論も送ってもらいました。詩のブログの方に載せましたが、この機会にこちらにも載せておきます。
ボブ・ディラン
神をチャネルする
それほどの才能のあることの
それほどの前が見れることの
責任をあなたは負わない
逃げよ
つかまらず
ただ自由であることを証明するだけのために
自分の声で自分の歌を歌い続けるために
自分の歌を自分のものとし続けるために
愛を歌わず
反戦を掲げず
時代を代弁せず
歌わないために
笑わないために
語らないために
走り続けよ
評論家もファンも
誰も追いつけないスピードで
変わり続けよ
批判され続けよ
失望させ続けよ
裏切り続けよ
あなたが潔く捨てていくものを
振り返らずに
踏みにじっていくものを
拾い上げることで
私たちは魂の枷を少しだけゆるめる
ではこちらもよろしく
イギリス(海外生活・情報) ブログランキングへ
2015年11月24日火曜日
ごまめ
私が昔から好きだった詩人に伊藤比呂美さんと言う人がいます。偶然にも彼女の現在の境遇は私と似ていて、今はアメリカ人のだんなさんと成人した娘さんが3人と一緒に、アメリカに住んでいます。
今のだんなさんの前には、日本人のだんなさんがいて、お子様が二人いました。その頃は出産記録や育児記録的な散文集や詩集も出版されてました。
その比呂美さんですが、昔、結婚して日本に住んでいたころ、職業が詩人ということは、社会からは、「大きな目で」見られたり、「ああしょうがないわね」という見方をされると書いてました。たとえばゴミを出す日を間違えたら、近所の奥さんたちが、「ああ、でもあの人は詩人だから、しかたないわね。」と思ってくれるそうです。
大阪弁で言うと「ごまめ」と言いますか・・。
で、考えてみたら、私もこれはよくあるんですよ。まず外国人。ロンドンと違いこの辺の外人慣れしてないイギリス人は、きっと私のことを、「まああの人は外人だからしょうがない。」と思ってることが多いと思います。
それからヨガの先生。これも、私が結構一般的によく知られていることにぜんぜん疎かったりした場合、きっと、まあヨガの先生だから、と思われてるでしょうね。
しかも、日本に行ったら行ったで、「あの人は外国暮らしが長いから」と絶対思われてると思いますよ。
これは別に、暖かい愛情のある目で寛容に許してくれるっていうだけではないんですけどね。 「あの人とは世界が違う・常識が違う・次元が違うから、言ってもしょうがない」と思われてるわけです。かといって、白い目で差別してるって言うわけでもないし、「あきらめ」と「寛容」が混ざったような感じかな。
ごまめ扱いされるほうとしては、実はこれはすごく楽です。ちょっとぐらい常識外れても、多めに見てもらえるし、それに慣れてくると、 そのちょっとした疎外感って、拘束がなくて自由。
私が外国に住むことが好きなもの、このちょっとした疎外感、孤独感が好きなのかも。
ではこちらもよろしく

イギリス(海外生活・情報) ブログランキングへ
今のだんなさんの前には、日本人のだんなさんがいて、お子様が二人いました。その頃は出産記録や育児記録的な散文集や詩集も出版されてました。
その比呂美さんですが、昔、結婚して日本に住んでいたころ、職業が詩人ということは、社会からは、「大きな目で」見られたり、「ああしょうがないわね」という見方をされると書いてました。たとえばゴミを出す日を間違えたら、近所の奥さんたちが、「ああ、でもあの人は詩人だから、しかたないわね。」と思ってくれるそうです。
大阪弁で言うと「ごまめ」と言いますか・・。
で、考えてみたら、私もこれはよくあるんですよ。まず外国人。ロンドンと違いこの辺の外人慣れしてないイギリス人は、きっと私のことを、「まああの人は外人だからしょうがない。」と思ってることが多いと思います。
それからヨガの先生。これも、私が結構一般的によく知られていることにぜんぜん疎かったりした場合、きっと、まあヨガの先生だから、と思われてるでしょうね。
しかも、日本に行ったら行ったで、「あの人は外国暮らしが長いから」と絶対思われてると思いますよ。
これは別に、暖かい愛情のある目で寛容に許してくれるっていうだけではないんですけどね。 「あの人とは世界が違う・常識が違う・次元が違うから、言ってもしょうがない」と思われてるわけです。かといって、白い目で差別してるって言うわけでもないし、「あきらめ」と「寛容」が混ざったような感じかな。
ごまめ扱いされるほうとしては、実はこれはすごく楽です。ちょっとぐらい常識外れても、多めに見てもらえるし、それに慣れてくると、 そのちょっとした疎外感って、拘束がなくて自由。
私が外国に住むことが好きなもの、このちょっとした疎外感、孤独感が好きなのかも。
ではこちらもよろしく
イギリス(海外生活・情報) ブログランキングへ
2012年8月27日月曜日
書類の断捨離
直視したくないもの、永遠に放っておけるものなら放っておきたいもの。それが昔の書類。いつか整理しないといけないと分かっていても、ついつい手がつけられなくって。
でもこの洋服ではじまった「ときめきの片付け」、次は書類の順番です。ラッキーなことに1年位前にふとそんな気になってずいぶん捨てたので、 ひどいことにはなっていないことはわかってたんだけど、やっぱりなんとなく気が乗りません。洋服なんかと比べてときめくことってないし。
こんまりさんのアドバイスは「基本全部捨て」。領収書も給料明細もカード明細も電気機器の説明書も、どんどん捨てましょうとのことでした。
本当にそんなに捨てられればすっきりするんでしょうけどね。でも私は自営業なのでそうも行きません。電気代の請求書もも銀行の明細も、毎年申告時に1年分整理します。調べてみると、それは6年間保存しないといけないそうです。
こんまりさんがそうは言っても、やっぱり個人的に好みというかカンフォート・ゾーンというものもあるので、あまり鵜呑みにしないほうがいいんじゃないかなあ。説明書も、私は実は8年前くらい前に買った電話の説明書を未だにたまに見るし。(どんだけメカに弱いねん)
クレジットカードの請求書は1年間は取ってます。めったにないけどたまに昔のことをチェックすることもあるし、1年を半年に減らしたところで、量的にはそれほど変わらないので、これはそのまま。銀行の明細も1年分保存。
年金積み立ての明細などは本当に今年の分だけあればいいはずなんだけど、一応2010年のものまでキープしました。
終わってみた感想は、思ったよりは時間はかかりませんでした。うちは2000年に家を建てたので、その関係の書類がたくさんあり、一々目を通さないと何か分からないものもあって、そういうので時間を取られましたが、そういったややこしいことがなければ、たぶん1時間くらいで終わるんじゃないかなあ。
今これを書きながら、やっぱりもっと思い切って捨てたらよかったかなという部分もあるけど、実際にはクレジットカードの明細を1年キープしようと半年しようと、年金掛け金の明細を3年キープしようと1年しようと、家の空間に占めるかさというのは、服などとは比較にならないくらい小さいですから、どちらでもいいと思います。要は、1年なら1年と決めて、新しい明細を受け取るたびに古いものを捨てていくこと。
それさえできれば、書類って一度断捨離出来れば 、一番リバウンドしにくい分野なんじゃないかな。
子供の書類を整理していたら、ルイが小学校のときに(2年くらいのときに)書いた詩が出てきました。My Magic Boxという題で、自分の箱の中にどんなお気に入りのものを入れるか、そしてそれを地球の真ん中に埋めて、自分は大金持ちになるぞという内容。はじめてみたときも、本当にすごいなあと感心したのですが、改めてみて小さい頃の姿などと重なって、かなりウルウルときてしまいました。
英語のままですが、上記のリンクで御一読ください。
これはもちろん断捨離はしません。
でも思い出の物はまた改めて最後に断捨離することになってるので、また去年の成績表なんかと同じファイルに戻しました。
クリック疲れがなければ、よろしければこちらのボタンのクリックお願いいたします。
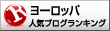
ヨーロッパ(海外生活・情報) ブログランキングへ
でもこの洋服ではじまった「ときめきの片付け」、次は書類の順番です。ラッキーなことに1年位前にふとそんな気になってずいぶん捨てたので、 ひどいことにはなっていないことはわかってたんだけど、やっぱりなんとなく気が乗りません。洋服なんかと比べてときめくことってないし。
こんまりさんのアドバイスは「基本全部捨て」。領収書も給料明細もカード明細も電気機器の説明書も、どんどん捨てましょうとのことでした。
本当にそんなに捨てられればすっきりするんでしょうけどね。でも私は自営業なのでそうも行きません。電気代の請求書もも銀行の明細も、毎年申告時に1年分整理します。調べてみると、それは6年間保存しないといけないそうです。
こんまりさんがそうは言っても、やっぱり個人的に好みというかカンフォート・ゾーンというものもあるので、あまり鵜呑みにしないほうがいいんじゃないかなあ。説明書も、私は実は8年前くらい前に買った電話の説明書を未だにたまに見るし。(どんだけメカに弱いねん)
クレジットカードの請求書は1年間は取ってます。めったにないけどたまに昔のことをチェックすることもあるし、1年を半年に減らしたところで、量的にはそれほど変わらないので、これはそのまま。銀行の明細も1年分保存。
年金積み立ての明細などは本当に今年の分だけあればいいはずなんだけど、一応2010年のものまでキープしました。
終わってみた感想は、思ったよりは時間はかかりませんでした。うちは2000年に家を建てたので、その関係の書類がたくさんあり、一々目を通さないと何か分からないものもあって、そういうので時間を取られましたが、そういったややこしいことがなければ、たぶん1時間くらいで終わるんじゃないかなあ。
今これを書きながら、やっぱりもっと思い切って捨てたらよかったかなという部分もあるけど、実際にはクレジットカードの明細を1年キープしようと半年しようと、年金掛け金の明細を3年キープしようと1年しようと、家の空間に占めるかさというのは、服などとは比較にならないくらい小さいですから、どちらでもいいと思います。要は、1年なら1年と決めて、新しい明細を受け取るたびに古いものを捨てていくこと。
それさえできれば、書類って一度断捨離出来れば 、一番リバウンドしにくい分野なんじゃないかな。
子供の書類を整理していたら、ルイが小学校のときに(2年くらいのときに)書いた詩が出てきました。My Magic Boxという題で、自分の箱の中にどんなお気に入りのものを入れるか、そしてそれを地球の真ん中に埋めて、自分は大金持ちになるぞという内容。はじめてみたときも、本当にすごいなあと感心したのですが、改めてみて小さい頃の姿などと重なって、かなりウルウルときてしまいました。
英語のままですが、上記のリンクで御一読ください。
これはもちろん断捨離はしません。
でも思い出の物はまた改めて最後に断捨離することになってるので、また去年の成績表なんかと同じファイルに戻しました。
クリック疲れがなければ、よろしければこちらのボタンのクリックお願いいたします。
ヨーロッパ(海外生活・情報) ブログランキングへ
2011年10月7日金曜日
クリエーティビティー教育
俳句って書いたことありますか? 私はないのですが、うちのチャーリーは8歳くらいのときに学校で書いていました。
俳句といってもこちらで言う俳句は、5・7・5にシラブルがなっているというだけのシンプルなもの。日本の俳句とはかなり違いますが、詩の定型としては定着しているようで、こんな風に学校で習ったりします。
チャーリーの俳句はこちら
詩や俳句に限らず、イギリスでは学校の「国語」の時間は「書く」時間が多いです。たとえば国語の宿題はいくつか難しい言葉を与えられて、それを使った文章を作りましょうと言うのがよくあります。
たとえば今週のチャーリー(小学校6年生)の宿題の単語のひとつはPiteously(憐れみをこめて)。それでチャーリーの書いた文章は、
As I lay dying on the ground, my murderer looked at me piteouisly, but I didn't want her sympathy. (地面で死にかけている私を、殺人犯は憐れみの目で見た。だか彼女の同情など欲しくはなかった。)
私が小学生の頃は国語の時間と言えば教科書を読む読解ばかりでした。これは中学でも高校でもあまり変わりがなかったように覚えています。小学校では週に一度作文の時間があり、これが嫌でした。どうして嫌かと言うと、遠足だとか運動会だとかつまらないことばかりについて書かされたからです。どういうことがあったか描写し、それについて感想を書く。そういう単調な作業ばかりだったので、4年生くらいには、「xxxxxxということはありましたが、とっても楽しい遠足でした。」とか、先生が満足するようなフォーマットを編み出し、適当にお茶を濁していました。先生もそれで納得していたようなので、こんなものじゃ文章力が上達するはずはありません。オリジナリティーだとか、創造性だとかを伸ばすなんてことはぜんぜん頭になかったと思います。
読書感想文も嫌でした。これは文章力と言うよりは、課題図書をちゃんと読んでいるかチェックするために書かされているようなものだったので、それならそれでこちらもあとがきを読んで適当にはしょって書くとか、こつをつかんで無難にかわしていました。
想像力を羽ばたかせて、文章で自由に創作したこと。そんな記憶はまったくありません。とにかく作文でも読書感想でも小論文でも、事実に基づいたことばかりを書かされました。句読点の使い方だとか、段落の変え方などの技術的なことは覚えたけど、肝心の文章力はぜんぜんつかなかったと思います。おそらく先生も、フィクションの書き方なんて教える技量がなかったんでしょうね。
中学1年生のとき頭のよかった同級生が転校したのですが、その時に「私の趣味は小説を書くこと、将来は小説家になりたいです。」と言ったのが記憶に強くあります。「中学生でも小説なんてかけるのか」とすごく感心しました。
こっちの子供はよくフィクションを学校で書いています。小説などというとあらすじだとか構成だとかいろいろ大層に聞こえますが、たとえば上のチャーリーの例のように、まったく文脈なして短文を書くこともあるし、数週間かけて まとまった話を書くこともあります。
簡単な例だと、「3匹の子豚」の話を自分流にアレンジして、エンディングを変えて書きましょうだとか、先に書いた俳句だとか、子供でも取り組みやすいやり方はいろいろあるようです。
日本では俳句は季語がいるだとか、 川柳は風刺が入ってるだとか学校で習いました。でも実際に「じゃあ作ってみましょう」と創作したことはないと思います。もしかしたら申し訳程度に一度くらいはやったかもしれないけど、毎週毎週練習を重ねてなんてことは決してありませんでした。
じゃあイギリスは日本よりも作家が多いかというとそんなことはない様に思いますし、日本人のブログ人口は世界一とも聞いているので、日本人が文章をかけないかというとそんなことは全然ない。でもクリエーティビティーという意味では、日本の学校教育は偏ってるなあ思ってしまいます。
もうひとつ驚いたのは音楽です。イギリスの音楽教育はすごく劣っていて、たとえば小学生は楽譜はぜんぜん読み方も知りません。 楽器が弾けたり楽譜が読めるのは、家でピアノなどの楽器を習っている子供だけです。
でも中学では作曲をするんですよ。ルイは中学2年生なのですが、クラスの中のルイを含めた数人だけが楽譜が読めます。それでその生徒達は今学期は作曲をすることが課題になっています。ただ単に「曲を書け」といわれてもどうしたらいいかわからないので、ちゃんとやり方を教えてくれます。
とりあえず最初の作品は、好きな音楽をいくつか選んで、その中から好きな小節を選んで、それをつなげてアレンジしてごらん、という感じみたいです。
中学校は5年生までなのですが、その4年目と5年目のときにGCSEという試験を受けます。音楽は選択なのですが、選択した生徒は、試験の3分の1は作曲だそうです。その頃はまだ15歳くらいなんだけど、多くの中学生が作曲するんだねえと思うと、日本とはえらく違うなあという気がします。
私が中学生の頃は週に2回音楽があり、期末テストも年に3回あったけど、音楽のセオリーや作曲家の名前ばっかり覚えて、ぜんぜん楽しかった記憶がありません。
日本ってフィクションを書くにしても作曲をするにしても、そういうことができるのは一部の才能のある人だけで、普通の生徒は句読点や文法やクレッシェンドとディクレッシェンドの違いがわかっていればいいという教育方針なんでしょうか?
日本人は応用はうまいが、オリジナルにゼロから物を作り出すことは下手だと世界的に評判がありますよね。(少なくとも昔はあったけど、今はもしかして変わったかも?) こういった日英の学校教育の違いを見ていると、やっぱりそう言われても仕方ないなあという気がします。
でも日本のほうがGDPも(まだ僅かに)高いし、衛生的で礼儀正しくてすみやすいし、日本のコンテンポラリー文化は今世界的に高く評価されてるって言えばそれも本当のことだから、日本の教育はなってないというわけではないけど・・・でも私が小学生、中学生なら、イギリス風のオリジナリティーを育む教育を受けたかったなあと思います。
逆に言えば、日本ってあんなに個人性を育まない教育なのに、作家もアーティストもたくさんいるって言うことは、個人個人の中には、いかに日本的な抑圧的な教育でも芽を摘むことができない才能が眠ってるって事なんでしょうか。
話は大きく変わりますが阪神は今日で4連勝。私の大好きな岩田君が今日は完投完封でした。 火曜からの3連戦、今のところ全勝。この調子で13連勝や!!
やっとこさ料理ブログ更新。ぜひごらんください。失敗したジャムやジェリーの作り直し方
ではよろしければこちらのボタンのクリック、よろしくお願いいたします。

俳句といってもこちらで言う俳句は、5・7・5にシラブルがなっているというだけのシンプルなもの。日本の俳句とはかなり違いますが、詩の定型としては定着しているようで、こんな風に学校で習ったりします。
チャーリーの俳句はこちら
詩や俳句に限らず、イギリスでは学校の「国語」の時間は「書く」時間が多いです。たとえば国語の宿題はいくつか難しい言葉を与えられて、それを使った文章を作りましょうと言うのがよくあります。
たとえば今週のチャーリー(小学校6年生)の宿題の単語のひとつはPiteously(憐れみをこめて)。それでチャーリーの書いた文章は、
As I lay dying on the ground, my murderer looked at me piteouisly, but I didn't want her sympathy. (地面で死にかけている私を、殺人犯は憐れみの目で見た。だか彼女の同情など欲しくはなかった。)
私が小学生の頃は国語の時間と言えば教科書を読む読解ばかりでした。これは中学でも高校でもあまり変わりがなかったように覚えています。小学校では週に一度作文の時間があり、これが嫌でした。どうして嫌かと言うと、遠足だとか運動会だとかつまらないことばかりについて書かされたからです。どういうことがあったか描写し、それについて感想を書く。そういう単調な作業ばかりだったので、4年生くらいには、「xxxxxxということはありましたが、とっても楽しい遠足でした。」とか、先生が満足するようなフォーマットを編み出し、適当にお茶を濁していました。先生もそれで納得していたようなので、こんなものじゃ文章力が上達するはずはありません。オリジナリティーだとか、創造性だとかを伸ばすなんてことはぜんぜん頭になかったと思います。
読書感想文も嫌でした。これは文章力と言うよりは、課題図書をちゃんと読んでいるかチェックするために書かされているようなものだったので、それならそれでこちらもあとがきを読んで適当にはしょって書くとか、こつをつかんで無難にかわしていました。
想像力を羽ばたかせて、文章で自由に創作したこと。そんな記憶はまったくありません。とにかく作文でも読書感想でも小論文でも、事実に基づいたことばかりを書かされました。句読点の使い方だとか、段落の変え方などの技術的なことは覚えたけど、肝心の文章力はぜんぜんつかなかったと思います。おそらく先生も、フィクションの書き方なんて教える技量がなかったんでしょうね。
中学1年生のとき頭のよかった同級生が転校したのですが、その時に「私の趣味は小説を書くこと、将来は小説家になりたいです。」と言ったのが記憶に強くあります。「中学生でも小説なんてかけるのか」とすごく感心しました。
こっちの子供はよくフィクションを学校で書いています。小説などというとあらすじだとか構成だとかいろいろ大層に聞こえますが、たとえば上のチャーリーの例のように、まったく文脈なして短文を書くこともあるし、数週間かけて まとまった話を書くこともあります。
簡単な例だと、「3匹の子豚」の話を自分流にアレンジして、エンディングを変えて書きましょうだとか、先に書いた俳句だとか、子供でも取り組みやすいやり方はいろいろあるようです。
日本では俳句は季語がいるだとか、 川柳は風刺が入ってるだとか学校で習いました。でも実際に「じゃあ作ってみましょう」と創作したことはないと思います。もしかしたら申し訳程度に一度くらいはやったかもしれないけど、毎週毎週練習を重ねてなんてことは決してありませんでした。
じゃあイギリスは日本よりも作家が多いかというとそんなことはない様に思いますし、日本人のブログ人口は世界一とも聞いているので、日本人が文章をかけないかというとそんなことは全然ない。でもクリエーティビティーという意味では、日本の学校教育は偏ってるなあ思ってしまいます。
もうひとつ驚いたのは音楽です。イギリスの音楽教育はすごく劣っていて、たとえば小学生は楽譜はぜんぜん読み方も知りません。 楽器が弾けたり楽譜が読めるのは、家でピアノなどの楽器を習っている子供だけです。
でも中学では作曲をするんですよ。ルイは中学2年生なのですが、クラスの中のルイを含めた数人だけが楽譜が読めます。それでその生徒達は今学期は作曲をすることが課題になっています。ただ単に「曲を書け」といわれてもどうしたらいいかわからないので、ちゃんとやり方を教えてくれます。
とりあえず最初の作品は、好きな音楽をいくつか選んで、その中から好きな小節を選んで、それをつなげてアレンジしてごらん、という感じみたいです。
中学校は5年生までなのですが、その4年目と5年目のときにGCSEという試験を受けます。音楽は選択なのですが、選択した生徒は、試験の3分の1は作曲だそうです。その頃はまだ15歳くらいなんだけど、多くの中学生が作曲するんだねえと思うと、日本とはえらく違うなあという気がします。
私が中学生の頃は週に2回音楽があり、期末テストも年に3回あったけど、音楽のセオリーや作曲家の名前ばっかり覚えて、ぜんぜん楽しかった記憶がありません。
日本ってフィクションを書くにしても作曲をするにしても、そういうことができるのは一部の才能のある人だけで、普通の生徒は句読点や文法やクレッシェンドとディクレッシェンドの違いがわかっていればいいという教育方針なんでしょうか?
日本人は応用はうまいが、オリジナルにゼロから物を作り出すことは下手だと世界的に評判がありますよね。(少なくとも昔はあったけど、今はもしかして変わったかも?) こういった日英の学校教育の違いを見ていると、やっぱりそう言われても仕方ないなあという気がします。
でも日本のほうがGDPも(まだ僅かに)高いし、衛生的で礼儀正しくてすみやすいし、日本のコンテンポラリー文化は今世界的に高く評価されてるって言えばそれも本当のことだから、日本の教育はなってないというわけではないけど・・・でも私が小学生、中学生なら、イギリス風のオリジナリティーを育む教育を受けたかったなあと思います。
逆に言えば、日本ってあんなに個人性を育まない教育なのに、作家もアーティストもたくさんいるって言うことは、個人個人の中には、いかに日本的な抑圧的な教育でも芽を摘むことができない才能が眠ってるって事なんでしょうか。
話は大きく変わりますが阪神は今日で4連勝。私の大好きな岩田君が今日は完投完封でした。 火曜からの3連戦、今のところ全勝。この調子で13連勝や!!
やっとこさ料理ブログ更新。ぜひごらんください。失敗したジャムやジェリーの作り直し方
ではよろしければこちらのボタンのクリック、よろしくお願いいたします。

2011年9月30日金曜日
アトム
空を越えて、ラララ
星のかたな
行くぞ、アトム、ジェットの限り
心優し
ラララ
科学の子
十万馬力だ鉄腕アトム
(谷川俊太郎)
この詩を読んで、あの音楽が頭に自然に流れてこない人は一体日本に何人くらいいるでしょう。
この上記の文章は谷川俊太郎の詩集のあとがきに載っていました。本当にそうですよね。最近の子供達(10歳以下)は例外かもしれませんが、少なくとも私の年代上下20年くらいの人はみんなあの音楽が頭に浮かんでくることでしょう。
それで他にもそういう歌詞があるかなあと思ってみたのですが、童謡の赤とんぼやめだかの学校などを除くとなかなか思い浮かびません。 しかも童謡の場合は学校で歌わされたので、自然と身についていたとはいえません。
無理やり頭をひねると・・・
「お魚くわえたドラ猫、追いかけて・・・・ 」
「きゅう、きゅう、きゅう。お化けのQ。僕はお化けのQ太郎・・・」
なんてのが浮かびますが 、それでもたぶんアトムの曲の浸透度にはぜんぜん及ばない気がします。(ちなみに上はサザエさん)
わたしは実は年代的にはちょっとアトムより下の年代なので、テレビでアニメを見たことは数回しかないし、ほとんど記憶もありません。おそらくテレビでこの曲を聴いたこともない。それでもこの詞を節なしで音読することなんて不可能です。
それって考えてみたらすごい。
それにこれは贔屓目かもしれないけれど、やっぱり詞の格が違うと思いませんか?一つ一つの言葉を取るとどのフレーズも特に目新しい表現はないですよね。空を越えても、星のかなたも、ありふれてると言えばありふれた表現。でも科学の子・・・・これはなかなかユニークな言葉でぴったりだと思います。
それでそれを全部つなげて詩にすると、言葉の世界以上のものが、なんだか心が広々するような感じがします。私のつたない説明じゃわかりにくければ、「お魚くわえたドラ猫追いかけて」と比べてみてください。なんかやっぱり心に伝わってくるものが違うじゃないですか。
手塚治虫ってアトム以外にももちろん作品を書いたけど、アトム以上に愛され評価されてるものってないですよね。(私は実は個人的にはリボンの騎士が無茶苦茶好きだったんですが。)これってもしかすると、その理由のひとつはこの谷川俊太郎の詩じゃないか。そういう気がします。
じゃあさあ。リボンの騎士にも谷川俊太郎が歌詞を書いたらもっと歴史上に残る名作になって、今でもリバイバルとかされたり、簡単に昔のビデオが手に入ったりするんじゃないの・・・・なんてことを考えてみましたが、実は谷川俊太郎は最近では宮崎駿作品の歌詞など、いろいろ幅広くやったようです。校歌もいろいろ依頼されて書いたらしい。
だから谷川俊太郎なら大ヒットって言うわけでもないし、誰が書いたって校歌は校歌で、あんまり歌いたくはないだろうなあ。
話は詩から大きく変わって・・・・
今日は阪神はやっと勝って連敗を脱出。不遇の岩田君にも勝ちがつきました。(涙)。自力優勝の可能性どころか、自力2位の可能性もないらしいですが、阪神ファンはしつこいです。自力でも他力でもなんでもええ。とにかく最後まであきらめずがんばれ!
ではよろしければこちらのボタン、ポチッとクリックお願いします。

星のかたな
行くぞ、アトム、ジェットの限り
心優し
ラララ
科学の子
十万馬力だ鉄腕アトム
(谷川俊太郎)
この詩を読んで、あの音楽が頭に自然に流れてこない人は一体日本に何人くらいいるでしょう。
この上記の文章は谷川俊太郎の詩集のあとがきに載っていました。本当にそうですよね。最近の子供達(10歳以下)は例外かもしれませんが、少なくとも私の年代上下20年くらいの人はみんなあの音楽が頭に浮かんでくることでしょう。
それで他にもそういう歌詞があるかなあと思ってみたのですが、童謡の赤とんぼやめだかの学校などを除くとなかなか思い浮かびません。 しかも童謡の場合は学校で歌わされたので、自然と身についていたとはいえません。
無理やり頭をひねると・・・
「お魚くわえたドラ猫、追いかけて・・・・ 」
「きゅう、きゅう、きゅう。お化けのQ。僕はお化けのQ太郎・・・」
なんてのが浮かびますが 、それでもたぶんアトムの曲の浸透度にはぜんぜん及ばない気がします。(ちなみに上はサザエさん)
わたしは実は年代的にはちょっとアトムより下の年代なので、テレビでアニメを見たことは数回しかないし、ほとんど記憶もありません。おそらくテレビでこの曲を聴いたこともない。それでもこの詞を節なしで音読することなんて不可能です。
それって考えてみたらすごい。
それにこれは贔屓目かもしれないけれど、やっぱり詞の格が違うと思いませんか?一つ一つの言葉を取るとどのフレーズも特に目新しい表現はないですよね。空を越えても、星のかなたも、ありふれてると言えばありふれた表現。でも科学の子・・・・これはなかなかユニークな言葉でぴったりだと思います。
それでそれを全部つなげて詩にすると、言葉の世界以上のものが、なんだか心が広々するような感じがします。私のつたない説明じゃわかりにくければ、「お魚くわえたドラ猫追いかけて」と比べてみてください。なんかやっぱり心に伝わってくるものが違うじゃないですか。
手塚治虫ってアトム以外にももちろん作品を書いたけど、アトム以上に愛され評価されてるものってないですよね。(私は実は個人的にはリボンの騎士が無茶苦茶好きだったんですが。)これってもしかすると、その理由のひとつはこの谷川俊太郎の詩じゃないか。そういう気がします。
じゃあさあ。リボンの騎士にも谷川俊太郎が歌詞を書いたらもっと歴史上に残る名作になって、今でもリバイバルとかされたり、簡単に昔のビデオが手に入ったりするんじゃないの・・・・なんてことを考えてみましたが、実は谷川俊太郎は最近では宮崎駿作品の歌詞など、いろいろ幅広くやったようです。校歌もいろいろ依頼されて書いたらしい。
だから谷川俊太郎なら大ヒットって言うわけでもないし、誰が書いたって校歌は校歌で、あんまり歌いたくはないだろうなあ。
話は詩から大きく変わって・・・・
今日は阪神はやっと勝って連敗を脱出。不遇の岩田君にも勝ちがつきました。(涙)。自力優勝の可能性どころか、自力2位の可能性もないらしいですが、阪神ファンはしつこいです。自力でも他力でもなんでもええ。とにかく最後まであきらめずがんばれ!
ではよろしければこちらのボタン、ポチッとクリックお願いします。
2011年9月29日木曜日
ペパークムからグリーンクリフへと詩人からの手紙
イギリスは夏に舞い戻っています。水曜から熱波がやってきて今日は気温は25度。真夏でもなかなかこんなに気温は上がりません。今年の9月はやたら雨が多くて寒くって、もう夏服なんてとっくにしまって、暖房まで欲しいくらいだったのに。
それでと言うわけではないのですが、友人と6月ごろから計画して計画倒れになっていた海岸の散歩をついに実行しました。毎週木曜の朝9時から1時間半ほどこのあたりを一緒に散歩するのですが、今日は思い切って長距離を歩きました。
まず車を1台はアボシャムに、1台はペパークムという場所に停めて、ペパークムからアボシャムまで歩くと言う計画です。
道しるべによると、距離は全部で10キロくらいです。それも平坦な道ではなく、海岸の崖に沿って下りたり登ったり。途中5分ほど座って休憩したほかは、時々立ち止まるくらいで歩き続け、時間にしたら3時間強でした。
写真を載せます。クリックすると大きくなります。
途中で雉狩のための私有地があり、そのあたりではとにかく雉の多いこと多いこと。100羽は見ました。まだ雉狩解禁じゃないんだけど、あと数週間で解禁。そうなると撃たれちゃうんですね、かわいそうに。ほかには野生動物には出会わなかったけれど、一度だけふくろうがすっと音も立てずに頭上を通っていきました。この辺でもふくろうはあんまり見かけないのですごくラッキーでした。
見かけないといえば、人間にはほとんど会いませんでした。最初の2時間くらいは一人も。後半アボシャム(村がある)に近づいていくると、2組くらい出会いました。それにしても平日とはいえこんなに天気がよくてすばらしい場所なのに、ぜんぜん人がいなくて、それがまた素晴らしい。
家に帰って地図でどれだけ歩いたか見てみました。すると・・・道調べに出ている距離を総合すると10キロくらいのはずなのに8キロくらいでした。ちょっとがっかりだったんですが、おそらく地図は直線距離だから、実際とはずいぶん違うんじゃないかなあ。写真をよく見ていただくとわかるけど、目線が高かったり海のレベルだったりするでしょ。すごく上り下りがたくさんあったのですよ。
それから話はぜんぜん変わるんですが、昨日どういうきっかけだか、昔書いた自分のブログのあるページを読んでいました。それはMidnight Expressという詩の雑誌の話で、そこで気に入った詩を載せて、ちょっとした感想を書いていたんです。そうしたら一番最後に今まで読んだことのなかったコメントが入っていたのに気づきました。
あら、リプライしていなかったわ。 失礼なことをしましたと思って読んでみると・・・・・
驚いたことに岡田すみれこさんというその詩人の方からのコメントだったんです。無断転記して怒られるどころか、感想を書いたお礼まで書いていただいていました。
そして驚いたことにそのブログの日付を見ると、きっちり2年前の同月同日だったんです。不思議な偶然。
それで夜中にそこに書いていただいていたすみれこさんのブログを読みました。するとまたたまたま偶然昨日の記事のところにたまたま御自分のメルアドを書いていらしたのです。それでメールを早速送らせていただきました。
すると今日は御丁寧にお返事のメールをいただきました。恥ずかしいことには、その2年前のブログには私の詩のブログのURLを載せていたのですが、それをわざわざ読んでくださったみたいでした。「よき書き手はよき読者である」とまで書いていただいて、恐縮でしたが、とっても嬉しかったです。
厳密に言えばいただいたのはEメールなんだけど、やっぱり詩人の方からいただいた通信物となると手紙と呼びたいですね。(伊藤比呂美さんという詩人は、「あの人は詩人だから」で、結構いろんなことを大目に見られる、たとえばゴミの日を間違えるとか。」と言っていました。やっぱり我々詩心に欠ける人間は詩人は特別な人と思ってるみたいですね。)
今日はこのことも含め、いろいろいい事があった1日でした。やっぱり引き寄せの法則だと思うんですよ。天気がいいから気分がいい。気分がいいからハッピーな気持ちになる。ハッピーな気持ちなのでハッピーなことが起こる。明日から数日好天気だそうです。
遅ればせながら、今年もやっとイギリスに夏がやってきました。
では今日もハッピーついでにワンクリックお願いいたします。

それでと言うわけではないのですが、友人と6月ごろから計画して計画倒れになっていた海岸の散歩をついに実行しました。毎週木曜の朝9時から1時間半ほどこのあたりを一緒に散歩するのですが、今日は思い切って長距離を歩きました。
まず車を1台はアボシャムに、1台はペパークムという場所に停めて、ペパークムからアボシャムまで歩くと言う計画です。
道しるべによると、距離は全部で10キロくらいです。それも平坦な道ではなく、海岸の崖に沿って下りたり登ったり。途中5分ほど座って休憩したほかは、時々立ち止まるくらいで歩き続け、時間にしたら3時間強でした。
写真を載せます。クリックすると大きくなります。
 |
| 車を停めて1マイルほど歩いた場所、海岸線の散策はここから始まります。 |
 |
| 中間点 |
 |
| 前を行く友達。これはすごく険しい下りでした。こんな風に整備されているのは2箇所ほどだけでした。友達がいるからこそ行こうと思うけど、一人では行かないだろうから、本当に感謝。 |
 |
| ここはこんなに低いです。上の写真の降りた場所。 |
 | |
| ゴール地点まで後3キロほど、左は海、右は 草原や農耕地 |
途中で雉狩のための私有地があり、そのあたりではとにかく雉の多いこと多いこと。100羽は見ました。まだ雉狩解禁じゃないんだけど、あと数週間で解禁。そうなると撃たれちゃうんですね、かわいそうに。ほかには野生動物には出会わなかったけれど、一度だけふくろうがすっと音も立てずに頭上を通っていきました。この辺でもふくろうはあんまり見かけないのですごくラッキーでした。
見かけないといえば、人間にはほとんど会いませんでした。最初の2時間くらいは一人も。後半アボシャム(村がある)に近づいていくると、2組くらい出会いました。それにしても平日とはいえこんなに天気がよくてすばらしい場所なのに、ぜんぜん人がいなくて、それがまた素晴らしい。
家に帰って地図でどれだけ歩いたか見てみました。すると・・・道調べに出ている距離を総合すると10キロくらいのはずなのに8キロくらいでした。ちょっとがっかりだったんですが、おそらく地図は直線距離だから、実際とはずいぶん違うんじゃないかなあ。写真をよく見ていただくとわかるけど、目線が高かったり海のレベルだったりするでしょ。すごく上り下りがたくさんあったのですよ。
それから話はぜんぜん変わるんですが、昨日どういうきっかけだか、昔書いた自分のブログのあるページを読んでいました。それはMidnight Expressという詩の雑誌の話で、そこで気に入った詩を載せて、ちょっとした感想を書いていたんです。そうしたら一番最後に今まで読んだことのなかったコメントが入っていたのに気づきました。
あら、リプライしていなかったわ。 失礼なことをしましたと思って読んでみると・・・・・
驚いたことに岡田すみれこさんというその詩人の方からのコメントだったんです。無断転記して怒られるどころか、感想を書いたお礼まで書いていただいていました。
そして驚いたことにそのブログの日付を見ると、きっちり2年前の同月同日だったんです。不思議な偶然。
それで夜中にそこに書いていただいていたすみれこさんのブログを読みました。するとまたたまたま偶然昨日の記事のところにたまたま御自分のメルアドを書いていらしたのです。それでメールを早速送らせていただきました。
すると今日は御丁寧にお返事のメールをいただきました。恥ずかしいことには、その2年前のブログには私の詩のブログのURLを載せていたのですが、それをわざわざ読んでくださったみたいでした。「よき書き手はよき読者である」とまで書いていただいて、恐縮でしたが、とっても嬉しかったです。
厳密に言えばいただいたのはEメールなんだけど、やっぱり詩人の方からいただいた通信物となると手紙と呼びたいですね。(伊藤比呂美さんという詩人は、「あの人は詩人だから」で、結構いろんなことを大目に見られる、たとえばゴミの日を間違えるとか。」と言っていました。やっぱり我々詩心に欠ける人間は詩人は特別な人と思ってるみたいですね。)
今日はこのことも含め、いろいろいい事があった1日でした。やっぱり引き寄せの法則だと思うんですよ。天気がいいから気分がいい。気分がいいからハッピーな気持ちになる。ハッピーな気持ちなのでハッピーなことが起こる。明日から数日好天気だそうです。
遅ればせながら、今年もやっとイギリスに夏がやってきました。
では今日もハッピーついでにワンクリックお願いいたします。
2010年11月1日月曜日
G先生の自殺
G先生が自殺した翌日
子供たちは学校に行く
何度も親を振り返り
手を振って教室に消えていく
G先生が自殺した翌日
親たちは子供を学校に連れてくる
笑って子供を見送っては
校門でひそひそと囁きあう
G先生が自殺した翌日
先生たちは早く出勤する
職員室での会合の後
誰もいない教室で
教材をもう一度確かめる
出席が取られ
給食費が集められる
教科書を広げ誰かがそれを読み始めると
教室は静かになる
昨日まで普通だったものを
珍しいものを眺めるように
一つ一つ指で取り上げては
積み木を積んでいく
退屈で整然とした詳細を
慣れない手つきで不器用に集めなおす
休み時間が来ると
子供たちはいつものようにざわざわと
話をしながら校庭に出る
誰かが倒した椅子がひとつ
床に転がっている
子供達がいなくなると
教頭先生は数秒壁に眼をやる
そしてほっとしたように
歩いて
椅子を拾い上げる
暗く暗く暗く
冷たい場所では
G先生が梁からぶら下がっている
誰もまだ知らない数時間
車の音も
庭の鳥の声も届かない
空気のしんとした闇の中で
静かに
静かに
静かに
先生は揺れている
2010年9月4日土曜日
ワード様
日本から公募ガイドを買ってきました。ぱらぱらとみていると、9月14日締め切りの原稿用紙5枚のエッセイのコンテストがあります。テーマは子育て。
子供は確かに育ててるけど、これといって書くこと無いなあ。うちの子供たちって、普通に悪いことはするけれど、健康だし学校でも問題ないし、特に苦労して育てたともいえないから、書くようなテーマが無いなあと思ってました。
何回かエッセイコンテストに出して思ったのですが、やっぱり題材が重要みたいです。普通の日常生活で気づいたこと程度では、なかなか入賞は難しいみたい。だっていまだに入賞作品って、戦争の頃の思い出が半分に近いくらいあります。こりゃあ、70歳未満の若造は立ち向かえない。それでなくても、大病とか家族の悲劇だとか、そういうテーマが当選しやすいみたいです。
それでも、これといって書きたいテーマがあれば、入選にはこだわらず、ただ誰かに読んでもらういい機会だと思って書きます。そういう時はすらすらかけるし、原稿用紙10枚くらいまでなら、ぜんぜん苦にならないからね。
で、今回はまだ日本から帰ってきてすぐだし、まだ腑抜け状態だし、とてもとてもと思ってたんですが、ふと思いついて、今日の夕方書き始めました。書き始めると、読み返しもせず字数も数えず、とにかくどんどん書きます。それで一応書きたいことを8割がた書き終わり、読み返していると・・・・
ガーン!!
なんとショックなことに停電!!コンピューターが消えてしまいました。ガーン!一気に書いたのでセーブなんてぜんぜんしていなかったんです。
同じ部屋で今日買ったばかりのWiiゲームをしていたルイも悲鳴を上げています。今までしたゲームがセーブされていないとか。
ショック
でも仕方ありません。まああれは殴り書きのようなものだったし、内容は頭に入ってるから、また書き直そうとコンピューターを入れると!!
なんとラッキーなことに、ワードに自動セーブされてました。失ったのは数行だけ。今のコンピューターはワード07なんですが、昔のコンピューターに入っていた昔のワード(2000だったかな)だったら、セーブされていなかったんじゃないかな。
でも最近調子悪かったプリンターは壊れちゃったみたいです。停電のあと赤いランプがついて、どうやっても消えません。
知人は雷が落ちてPCが壊れたことがあるといっていました。停電が原因で精密機器が壊れることって、たまにあるのかなあ。
そうそう、日本に行く前に応募していた文芸思潮という会社の現代詩大賞という公募では、第3次選考に通過との連絡がわざわざ来ました。去年は2次だったから、進歩。次は最終選考なんだけど、これは無理だろうなあと、やっぱり自分でも思っています。ポジティブではあるんだけど、自分も知ってるからね。でも3次選考でもたいしたものやん、と自分で言い聞かせてるところがポジティブなんですよ。
子供は確かに育ててるけど、これといって書くこと無いなあ。うちの子供たちって、普通に悪いことはするけれど、健康だし学校でも問題ないし、特に苦労して育てたともいえないから、書くようなテーマが無いなあと思ってました。
何回かエッセイコンテストに出して思ったのですが、やっぱり題材が重要みたいです。普通の日常生活で気づいたこと程度では、なかなか入賞は難しいみたい。だっていまだに入賞作品って、戦争の頃の思い出が半分に近いくらいあります。こりゃあ、70歳未満の若造は立ち向かえない。それでなくても、大病とか家族の悲劇だとか、そういうテーマが当選しやすいみたいです。
それでも、これといって書きたいテーマがあれば、入選にはこだわらず、ただ誰かに読んでもらういい機会だと思って書きます。そういう時はすらすらかけるし、原稿用紙10枚くらいまでなら、ぜんぜん苦にならないからね。
で、今回はまだ日本から帰ってきてすぐだし、まだ腑抜け状態だし、とてもとてもと思ってたんですが、ふと思いついて、今日の夕方書き始めました。書き始めると、読み返しもせず字数も数えず、とにかくどんどん書きます。それで一応書きたいことを8割がた書き終わり、読み返していると・・・・
ガーン!!
なんとショックなことに停電!!コンピューターが消えてしまいました。ガーン!一気に書いたのでセーブなんてぜんぜんしていなかったんです。
同じ部屋で今日買ったばかりのWiiゲームをしていたルイも悲鳴を上げています。今までしたゲームがセーブされていないとか。
ショック
でも仕方ありません。まああれは殴り書きのようなものだったし、内容は頭に入ってるから、また書き直そうとコンピューターを入れると!!
なんとラッキーなことに、ワードに自動セーブされてました。失ったのは数行だけ。今のコンピューターはワード07なんですが、昔のコンピューターに入っていた昔のワード(2000だったかな)だったら、セーブされていなかったんじゃないかな。
でも最近調子悪かったプリンターは壊れちゃったみたいです。停電のあと赤いランプがついて、どうやっても消えません。
知人は雷が落ちてPCが壊れたことがあるといっていました。停電が原因で精密機器が壊れることって、たまにあるのかなあ。
そうそう、日本に行く前に応募していた文芸思潮という会社の現代詩大賞という公募では、第3次選考に通過との連絡がわざわざ来ました。去年は2次だったから、進歩。次は最終選考なんだけど、これは無理だろうなあと、やっぱり自分でも思っています。ポジティブではあるんだけど、自分も知ってるからね。でも3次選考でもたいしたものやん、と自分で言い聞かせてるところがポジティブなんですよ。
2010年7月22日木曜日
エッセイ賞
インターネットの調子がよくないので、デイブのラップトップで書いています。
金曜に日本から郵便が来ました。何かと思ったら、4月に送った文芸思潮という雑誌のエッセイコンテストの結果でした。その手紙の内容を見るまで、一体どんなエッセイを送ったのかも忘れていました。結果は3次審査に通貨とのことでした。8月に最終選考があるそうです。
去年初めて送ったのですが、そのときはエッセイは1次審査通過、現代詩は2次審査通過だったように覚えています。なので今年は去年よりも進歩しているようです。
5月には現代詩のほうも送ったのですが、こちらはまだ通知はありません。もうしばらくしたら来るかな。もしも1次審査で落ちたら、多分何も言ってこないとも思うんですが。
エッセイよりも詩のほうが気になりますね。やっぱり詩のほうが身を削って書いているという気がするし、パッションを感じるからかな。だからエッセイのほうは評価されるとうれしいけれど、別にだめでも気になりません。詩のほうは1次審査で落ちると、かなりがっかりしますね。
どちらにしても結果は日本から帰ってきてからになりそうです。日本で売ってる文芸思潮アジアウェーブという文芸誌に結果が載ってるそうです。
金曜に日本から郵便が来ました。何かと思ったら、4月に送った文芸思潮という雑誌のエッセイコンテストの結果でした。その手紙の内容を見るまで、一体どんなエッセイを送ったのかも忘れていました。結果は3次審査に通貨とのことでした。8月に最終選考があるそうです。
去年初めて送ったのですが、そのときはエッセイは1次審査通過、現代詩は2次審査通過だったように覚えています。なので今年は去年よりも進歩しているようです。
5月には現代詩のほうも送ったのですが、こちらはまだ通知はありません。もうしばらくしたら来るかな。もしも1次審査で落ちたら、多分何も言ってこないとも思うんですが。
エッセイよりも詩のほうが気になりますね。やっぱり詩のほうが身を削って書いているという気がするし、パッションを感じるからかな。だからエッセイのほうは評価されるとうれしいけれど、別にだめでも気になりません。詩のほうは1次審査で落ちると、かなりがっかりしますね。
どちらにしても結果は日本から帰ってきてからになりそうです。日本で売ってる文芸思潮アジアウェーブという文芸誌に結果が載ってるそうです。
2010年2月1日月曜日
ふるさとの橋
子供のころ両親が離婚しました。私が小学校2年生に上がる春でした。妹はまだ幼稚園に上がる前です。大阪の住之江区というところから西成区へ。距離にしてはほんの少しだったんですが、子供心に遠くに越してきたつもりでいました。
母は看護婦の資格を持っていたので、文化住宅を借りての母子家庭の暮らしが始まりました。私は小学生ですから午後まで学校に行っています。それで妹は母の働いてる病院についていってぶらぶらするということだったんですが、短期間でそれは無理だということが明らかになってきました。そりゃそうです。彼女はたった3歳。朝から晩まで母のいる職場とはいえ、一人で自分の世話など出来るわけがありません。
それで妹だけ母の岐阜の実家に預けられることになりました。かわいそうですが仕方ありません。3歳児が病院で一人で一日中ぶらぶらしてるよりはまだましです。その頃はまだ土曜も仕事していましたから、毎週土曜に母が昼に仕事を終えて、午後から4時間かけてそこまで妹に会いに行っていました。そしてまた日曜に4時間かけて帰ってきます。体も疲れたけど、お金もさぞやかかったことでしょう。何せ新幹線で行ってましたから。
その初めて妹が祖父母の家に置いていかれた日のことを良く覚えています。幼い妹に説明してもしかたがないと大人たちは思ったのでしょう、妹が祖母と出かけているか従兄弟と遊んでいる隙に、何も言わずに彼女を置き去りにして大阪に戻ってきたんです。
私は7歳でしたが、子供心にもひどいことをするなあと思いました。別に妹思いの優しいお姉さんというわけでもなかったんですけどね。置いてきぼりにされたと気付いた妹は、どんなに絶望して泣いたことでしょう。私だったらとても自分の子供には出来ません。
妹が祖父母の家にいた期間はそう長くはなく、せいぜい数ヶ月だったと思います。その後、また彼女は大阪に連れてこられて、今度は保育所に入れられました。でもそこでも長く続かず、1ヵ月後位から3歳にして登園拒否を始めました。
お迎えの時間は5時だったか6時だったかと思うんですが、うちのは母いつもこれに遅れていました。そして妹はいつも一人で、皆が帰ってしまった後保母さんと待っていました。保母さんが母に文句をいていたのを覚えています。
妹は登園拒否の理由は、お昼寝の時間が嫌だったからだといっていました。それはたぶん本当でしょう。でもこのことも関係あるんじゃないかなあと私は思っています。
先日「公募ガイド」を見てたら、埼玉県羽生市主催の「ふるさとの橋」詩コンテストというのが募集されていました。橋についての詩を原稿用紙2枚以内で応募とのこと。募集要領には返信用に80円切手を同封とのことだったので、メールで外国からですがどうしましょうかと訊くと、「こちらで用意しますから大丈夫です。」と親切に返事をくれました。
橋についていろいろ思いをめぐらすと、この祖父母の家の近くの橋のことが頭に浮かびました。それでここに書いたようなことを詩にして先日投稿しました。
その詩を詩のブログに載せましたので、ぜひよかったら見てください。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/
母は看護婦の資格を持っていたので、文化住宅を借りての母子家庭の暮らしが始まりました。私は小学生ですから午後まで学校に行っています。それで妹は母の働いてる病院についていってぶらぶらするということだったんですが、短期間でそれは無理だということが明らかになってきました。そりゃそうです。彼女はたった3歳。朝から晩まで母のいる職場とはいえ、一人で自分の世話など出来るわけがありません。
それで妹だけ母の岐阜の実家に預けられることになりました。かわいそうですが仕方ありません。3歳児が病院で一人で一日中ぶらぶらしてるよりはまだましです。その頃はまだ土曜も仕事していましたから、毎週土曜に母が昼に仕事を終えて、午後から4時間かけてそこまで妹に会いに行っていました。そしてまた日曜に4時間かけて帰ってきます。体も疲れたけど、お金もさぞやかかったことでしょう。何せ新幹線で行ってましたから。
その初めて妹が祖父母の家に置いていかれた日のことを良く覚えています。幼い妹に説明してもしかたがないと大人たちは思ったのでしょう、妹が祖母と出かけているか従兄弟と遊んでいる隙に、何も言わずに彼女を置き去りにして大阪に戻ってきたんです。
私は7歳でしたが、子供心にもひどいことをするなあと思いました。別に妹思いの優しいお姉さんというわけでもなかったんですけどね。置いてきぼりにされたと気付いた妹は、どんなに絶望して泣いたことでしょう。私だったらとても自分の子供には出来ません。
妹が祖父母の家にいた期間はそう長くはなく、せいぜい数ヶ月だったと思います。その後、また彼女は大阪に連れてこられて、今度は保育所に入れられました。でもそこでも長く続かず、1ヵ月後位から3歳にして登園拒否を始めました。
お迎えの時間は5時だったか6時だったかと思うんですが、うちのは母いつもこれに遅れていました。そして妹はいつも一人で、皆が帰ってしまった後保母さんと待っていました。保母さんが母に文句をいていたのを覚えています。
妹は登園拒否の理由は、お昼寝の時間が嫌だったからだといっていました。それはたぶん本当でしょう。でもこのことも関係あるんじゃないかなあと私は思っています。
先日「公募ガイド」を見てたら、埼玉県羽生市主催の「ふるさとの橋」詩コンテストというのが募集されていました。橋についての詩を原稿用紙2枚以内で応募とのこと。募集要領には返信用に80円切手を同封とのことだったので、メールで外国からですがどうしましょうかと訊くと、「こちらで用意しますから大丈夫です。」と親切に返事をくれました。
橋についていろいろ思いをめぐらすと、この祖父母の家の近くの橋のことが頭に浮かびました。それでここに書いたようなことを詩にして先日投稿しました。
その詩を詩のブログに載せましたので、ぜひよかったら見てください。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/
2010年1月18日月曜日
詩のコメント
今朝郵便受けに日本からの郵便が着ていました。インターネットができてからというもの、日本から郵送で手紙が来ることなんてめったにないので何かと思いきや、春に応募した現代詩賞の主催者の会社からでした。結果発表のときに、希望者には有料で(後払い)詩の批評をお送りしますということでしたので、めったにない機会なのでお願いしていたのがやっと届いたんです。
送ったのは「私たちが求めるもの」、「ボブ・ディラン」、「裏切る」という3作でした。これ全部に批評して、わざわざイギリスまで送ってくれました。
内容は全体的に批評をいただいて、それから個別の詩についてコメントしてくださいました。褒めていただいたとこだけ載せます。
「予選の総合評価はBに丸 がついてますが、これはB のランクの上位、もう少しで最終選考対象であるAにはいるというレベルということです。
全体的に、表現の切れ、リズム感はかなりあるように思われます。ですから詩作品として拙さからの揺らぎがなく、安心して読んでいくことが出来ます。その点は自信を持っても良いのではないでしょうか。」
ここから個別作品についてコメントしてありました。
一つ目の「私たちが」については、テーマが普遍的過ぎて、面白い表現もあるが、読者の予想の範囲を超えられていない。3番目の「裏切る」については、テーマが抽象的過ぎてわかりにくいとのコメントでした。
「ボブ・ディラン」が一番よかったようで、
「とても特色のある作品になってます。この歌手の肖像として生き生きした表現で、読者はそれぞれ抱くボブ・ディランのイメージと絡み合わせて十分に楽しむことが出来ます。」と評価していただきました。「愛を歌わず」以降の10数行は単調とのことでした。
全体として、良いところを見つけ出して褒めてくださって、一方ではきちんと欠点が指摘されていて、自分でもとっても気分よく読めましたし、これから何を心がけたら良いのか、抽象的にならず具体的に方向を示されたようで、ますますがんばるぞという気になってます。
詩の文学賞に応募したのは初めてでした。人に見せることもまずないので、こういう公募に送って読んでもらえるだけでもありがたいという気持ちでした。人に見せないから、自分の詩がどの程度のものなのか、人様に読んでもらえるだけの価値があるのか、箸にも棒にもかからないものなのか良くわからなかったんですが、今回こうやって客観的にコメントをいただいて、がんばって書くぞという気になりました。
この文学賞、応募したのはエッセイと詩なのですが、その後有料で「文学思潮」の雑誌を送料サービスででイギリスまで送ってくれたり、今回はこんな風なコメンをしてくれました。どれも有料ではありますが、代金はあとで結構と、先に送って来てくれます。
この文芸思潮という雑誌、編集長は五十嵐勉さんといって、群像新人賞作家だそうです。そしてその編集人グループ「塊」には芥川賞作家の高橋三千綱さんをはじめとする、群像新人賞や文学界新人賞といった肩書きがつく作家の人たちが肩を並べています。
でもこの雑誌自体は、かなりマイナーなようです。文芸思潮取り扱い書店として何軒か本屋の名前が載っていましたから、どこでも買えるというわけではなく、要するに同人誌に毛の生えたようなものか、自己出版の本の雑誌版というところのようです。バックナンバーは申し込めば無料で送ってくれるそうです。ウエブサイトはこちら。 http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/index.htm
こんな丁寧に作られた雑誌でも、なかなかメジャーには売れないんですね。たぶん赤字赤字で、それでも文学を志す有志が集まって運営してるんだなあという感じがします。昔昭和の初期ころ、たくさんの同人誌が出てそういうところから著名な作家も生まれましたが、ああいうのっていまだにあるんですね。大きい本屋に行くと、聞いたこともないマイナーそうな文学雑誌がたくさんありますが、こういうの他にもたくさんあるんだろうな。なんだかそういう赤貧の文学者という雰囲気、昔はあこがれていました。今もあこがれてますが、赤貧は嫌ですね。
ボブ・ディランは昔このブログに載せたんですが、あらためて詩のブログのほうに載せておきます。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html
送ったのは「私たちが求めるもの」、「ボブ・ディラン」、「裏切る」という3作でした。これ全部に批評して、わざわざイギリスまで送ってくれました。
内容は全体的に批評をいただいて、それから個別の詩についてコメントしてくださいました。褒めていただいたとこだけ載せます。
「予選の総合評価はBに丸 がついてますが、これはB のランクの上位、もう少しで最終選考対象であるAにはいるというレベルということです。
全体的に、表現の切れ、リズム感はかなりあるように思われます。ですから詩作品として拙さからの揺らぎがなく、安心して読んでいくことが出来ます。その点は自信を持っても良いのではないでしょうか。」
ここから個別作品についてコメントしてありました。
一つ目の「私たちが」については、テーマが普遍的過ぎて、面白い表現もあるが、読者の予想の範囲を超えられていない。3番目の「裏切る」については、テーマが抽象的過ぎてわかりにくいとのコメントでした。
「ボブ・ディラン」が一番よかったようで、
「とても特色のある作品になってます。この歌手の肖像として生き生きした表現で、読者はそれぞれ抱くボブ・ディランのイメージと絡み合わせて十分に楽しむことが出来ます。」と評価していただきました。「愛を歌わず」以降の10数行は単調とのことでした。
全体として、良いところを見つけ出して褒めてくださって、一方ではきちんと欠点が指摘されていて、自分でもとっても気分よく読めましたし、これから何を心がけたら良いのか、抽象的にならず具体的に方向を示されたようで、ますますがんばるぞという気になってます。
詩の文学賞に応募したのは初めてでした。人に見せることもまずないので、こういう公募に送って読んでもらえるだけでもありがたいという気持ちでした。人に見せないから、自分の詩がどの程度のものなのか、人様に読んでもらえるだけの価値があるのか、箸にも棒にもかからないものなのか良くわからなかったんですが、今回こうやって客観的にコメントをいただいて、がんばって書くぞという気になりました。
この文学賞、応募したのはエッセイと詩なのですが、その後有料で「文学思潮」の雑誌を送料サービスででイギリスまで送ってくれたり、今回はこんな風なコメンをしてくれました。どれも有料ではありますが、代金はあとで結構と、先に送って来てくれます。
この文芸思潮という雑誌、編集長は五十嵐勉さんといって、群像新人賞作家だそうです。そしてその編集人グループ「塊」には芥川賞作家の高橋三千綱さんをはじめとする、群像新人賞や文学界新人賞といった肩書きがつく作家の人たちが肩を並べています。
でもこの雑誌自体は、かなりマイナーなようです。文芸思潮取り扱い書店として何軒か本屋の名前が載っていましたから、どこでも買えるというわけではなく、要するに同人誌に毛の生えたようなものか、自己出版の本の雑誌版というところのようです。バックナンバーは申し込めば無料で送ってくれるそうです。ウエブサイトはこちら。 http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/index.htm
こんな丁寧に作られた雑誌でも、なかなかメジャーには売れないんですね。たぶん赤字赤字で、それでも文学を志す有志が集まって運営してるんだなあという感じがします。昔昭和の初期ころ、たくさんの同人誌が出てそういうところから著名な作家も生まれましたが、ああいうのっていまだにあるんですね。大きい本屋に行くと、聞いたこともないマイナーそうな文学雑誌がたくさんありますが、こういうの他にもたくさんあるんだろうな。なんだかそういう赤貧の文学者という雰囲気、昔はあこがれていました。今もあこがれてますが、赤貧は嫌ですね。
ボブ・ディランは昔このブログに載せたんですが、あらためて詩のブログのほうに載せておきます。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html
2010年1月14日木曜日
母ア
12月5日のブログに現代詩は難解であるということを書きました。
http://myfordfarmdiary.blogspot.com/2009/12/blog-post_05.html
おととい日本から船便で文芸思潮という雑誌が届きました。去年春にこの現代詩賞に応募したので、入選作の掲載された雑誌を応募者に日本から送ってくれたんです。そこに10作ほどの作品が載っていました。最優秀賞は2作です。そのうちのひとつは若い女性の作品で、長くてわかりにくいといえばわかりにくい。でも妙に心惹かれるというか、なるほど何かがあるなあという作品でした。
もうひとつは福地順一さんという73歳の男性です。これは津軽弁で書かれていて、はじめだけちょっと読みにくいんですが、長すぎずわかりやすい内容で、泣けました。振り仮名が打てないので、読み方をカタカナでカッコに入れますので、辛抱して読んでみて下さい。
「母(カッチャ)ア」
母ア、俺(ワ)七十三ネなたネ
元気良(マミシ)ぐしてるよ
母ア 俺母アの事(ゴト)、何(ナ)も覚(オ)べねエンだネ
顔(ツラ)コも声コも覚でねエンだ
写真コも見だ事(ゴト)ねエンだ
母ア 母ア、俺三つの時(ツギ)
俺ど離されだンだってのオ
急性の流行性脳膜炎で
伊東(イドウ)病院の隔離病棟サ入られだンだってのオ
そのとき母ア泣き叫(サガ)ンだべアなア
だして呉(ケ)へってよオ
其処(ソゴ)ア如何(ド)したンだ部屋だべなア
鉄格子嵌(ハマ)てンだがア
母ア、母ア、俺四つの時
其処で亡ぐなったンだってのオ
誰(ダ)ネも看取(ミド)られなくてのオ
その時母ア俺の名前コ呼ンだベアなア
一人(ツトリ)息子の俺の名前ばよオ
母ア、母アの声、そえでも俺の耳サ残(ノゴ)ってねエンだネ
何(ナ)も覚えでねエンだ
情(ナサゲ)けねエ息子だと思(モ)てるンでねべがなア
それでも俺、母アの亡ぐなった時の事
何時(エッツ)も気ネ掛げ出るンだネ
この七十過ぎた今(エマ)でも気ネ掛ゲデるんだネ
あの一年(エツネン)、何ンぼ切ねがったべアなアど思てるンだネ
母ア、俺七十三ネなた
元気良ぐしてるよ
これが泣けるなあと思うのは自分が母親だからかなあ。小さい一人息子を残して死ぬお母さんの無念さが胸にひしひしせまってきます。
方言で書かれてるところがまた70年前の情感が出てるし、土着した感じが母と子供の絆をしみじみ感じさせます。それに何よりも、自分はもう70を過ぎたけど気に掛けてるというところが良いですね。これが50くらいじゃだめで、73歳というところが良い。何も覚えてないというところが、センチメンタルになりすぎるのをとどめている一方、お母さんのことを何も覚えていないというのは寂しいものだろうなあと想像させます。 泣ける詩なのに、最後の「元気良くしてるよ」というのが、ごく普通の親子の会話という風で、全体としてさらっとした印象が残るところが特に良い。
幼くしてお母さんを失って、寂しい幼少時代を送ったものの、今ではそれも大昔で70年近く月日が経ち、おそらくそれ相応に苦労しながらも元気で成人して、普通に社会人となり家族を作り平凡に生活してきたけれど、それでも自分を残していったお母さんのことを時々思い出す。
と書いてしまえばそれまでなんだけど、それが詩になってるところがすごいなあと思います。
これって津軽弁だから特にいいのかな。大阪弁ではどうかなあと思ってちょっとやってみましたが、ちょっと柄が悪くなる気もするけど、なかなかいけると思います。標準語では味は出ないけど、東京弁(東京の落語家のような語り調)でも良いんじゃないかなあ。
こう考えると方言っていいですね。私は大阪弁が一番良いと思ってるけど、皆さん自分のふるさとの言葉が一番と思ってるんでしょうね。
この人は若いときは詩を書いていたけれど、現代詩の観念的独善的な経口が嫌になり、興味を失ったそうです。それが去年から急に津軽弁で書きたくなり、物の怪に疲れたように70編ほど書いたとの事。
こういう現代詩、このコンテストで入選して雑誌に載って、私も読むことが出来て本当によかったと思ってます。
http://myfordfarmdiary.blogspot.com/2009/12/blog-post_05.html
おととい日本から船便で文芸思潮という雑誌が届きました。去年春にこの現代詩賞に応募したので、入選作の掲載された雑誌を応募者に日本から送ってくれたんです。そこに10作ほどの作品が載っていました。最優秀賞は2作です。そのうちのひとつは若い女性の作品で、長くてわかりにくいといえばわかりにくい。でも妙に心惹かれるというか、なるほど何かがあるなあという作品でした。
もうひとつは福地順一さんという73歳の男性です。これは津軽弁で書かれていて、はじめだけちょっと読みにくいんですが、長すぎずわかりやすい内容で、泣けました。振り仮名が打てないので、読み方をカタカナでカッコに入れますので、辛抱して読んでみて下さい。
「母(カッチャ)ア」
母ア、俺(ワ)七十三ネなたネ
元気良(マミシ)ぐしてるよ
母ア 俺母アの事(ゴト)、何(ナ)も覚(オ)べねエンだネ
顔(ツラ)コも声コも覚でねエンだ
写真コも見だ事(ゴト)ねエンだ
母ア 母ア、俺三つの時(ツギ)
俺ど離されだンだってのオ
急性の流行性脳膜炎で
伊東(イドウ)病院の隔離病棟サ入られだンだってのオ
そのとき母ア泣き叫(サガ)ンだべアなア
だして呉(ケ)へってよオ
其処(ソゴ)ア如何(ド)したンだ部屋だべなア
鉄格子嵌(ハマ)てンだがア
母ア、母ア、俺四つの時
其処で亡ぐなったンだってのオ
誰(ダ)ネも看取(ミド)られなくてのオ
その時母ア俺の名前コ呼ンだベアなア
一人(ツトリ)息子の俺の名前ばよオ
母ア、母アの声、そえでも俺の耳サ残(ノゴ)ってねエンだネ
何(ナ)も覚えでねエンだ
情(ナサゲ)けねエ息子だと思(モ)てるンでねべがなア
それでも俺、母アの亡ぐなった時の事
何時(エッツ)も気ネ掛げ出るンだネ
この七十過ぎた今(エマ)でも気ネ掛ゲデるんだネ
あの一年(エツネン)、何ンぼ切ねがったべアなアど思てるンだネ
母ア、俺七十三ネなた
元気良ぐしてるよ
これが泣けるなあと思うのは自分が母親だからかなあ。小さい一人息子を残して死ぬお母さんの無念さが胸にひしひしせまってきます。
方言で書かれてるところがまた70年前の情感が出てるし、土着した感じが母と子供の絆をしみじみ感じさせます。それに何よりも、自分はもう70を過ぎたけど気に掛けてるというところが良いですね。これが50くらいじゃだめで、73歳というところが良い。何も覚えてないというところが、センチメンタルになりすぎるのをとどめている一方、お母さんのことを何も覚えていないというのは寂しいものだろうなあと想像させます。 泣ける詩なのに、最後の「元気良くしてるよ」というのが、ごく普通の親子の会話という風で、全体としてさらっとした印象が残るところが特に良い。
幼くしてお母さんを失って、寂しい幼少時代を送ったものの、今ではそれも大昔で70年近く月日が経ち、おそらくそれ相応に苦労しながらも元気で成人して、普通に社会人となり家族を作り平凡に生活してきたけれど、それでも自分を残していったお母さんのことを時々思い出す。
と書いてしまえばそれまでなんだけど、それが詩になってるところがすごいなあと思います。
これって津軽弁だから特にいいのかな。大阪弁ではどうかなあと思ってちょっとやってみましたが、ちょっと柄が悪くなる気もするけど、なかなかいけると思います。標準語では味は出ないけど、東京弁(東京の落語家のような語り調)でも良いんじゃないかなあ。
こう考えると方言っていいですね。私は大阪弁が一番良いと思ってるけど、皆さん自分のふるさとの言葉が一番と思ってるんでしょうね。
この人は若いときは詩を書いていたけれど、現代詩の観念的独善的な経口が嫌になり、興味を失ったそうです。それが去年から急に津軽弁で書きたくなり、物の怪に疲れたように70編ほど書いたとの事。
こういう現代詩、このコンテストで入選して雑誌に載って、私も読むことが出来て本当によかったと思ってます。
2009年12月11日金曜日
エッセイ
先日もちょっと書きましたが、今年の春、文芸思潮という雑誌のエッセイ大賞と現代詩大賞に応募しました。それでその結果の載った雑誌をイギリスまで送っていただいたのですが、そこにエッセイ大賞受賞作品が15編ほど載っていました。(私はエッセイは一次予選、詩は二次予選通過にとどまりました。まあ初めてのことで満足しています。)
こういう公募は大体字数が少なくて、これも2000字から4000字だったように記憶しています。そのエッセイを読んだのですが、その三分の一くらいが戦争についてかかれたことでした。被爆してなくなった青年の話や、戦争中に食べようと亀を焼いた話。グライダーの訓練の話など。
それから肉親の死や病気についての話も多くありました。寝たきりになった母親の話。自殺したお姉さんの話。自分を捨てていった母親との再会。憎みあった父親の死。
ほかには不運な人生を送って苦しんで死んでいった患者さんの話。自閉症になった話。会社の同僚が殺人を起こした話。自閉症の娘の話。父親の死。
それから海外での生活の苦労話もありました。言葉の通じない南米に中学生のときに留学した苦労話や、サウジアラビアに親の転勤で住んでいて、現地人の友達と断食(ラマダン)した話。
全体の3分の2くらいはさすが文章がうまいなあ、この人はもう何年も書いてるんだろうなという感じの作品でした。後の3分の1くらいは、これくらいなら私でもがんばればかけるかなという感じでした。
それにしても思ったんですが、テーマが重い。一応エッセイですから、100パーセント実話でなくても、実際の体験に基づいてると思うんですが、なかなかこんな体験は普通の人は持っていません。すると、なんだか普通の体験に基づいて書いたエッセイなんて、こんな重い話と比べればテーマが比較にならないから、初めから勝ち目はないような気がしてきました。それともこれって、負け惜しみ?いえいえ、そんなつもりはないんですが、私には幸いにも戦争体験もないし、肉親が死んだこともないし、それだけでぱっとひきつけるような大きなドラマがないんです。
よくよく考えてみれば、私の母親は子供のころ2回も離婚してるし、自分も離婚してるし、波風ない人生を送ってきたわけでもないんですが、それとて別にエッセイにするほどのことでもない。これは私の分析力、文章力がないせいか?
よくない思い出のことを、深く思い出して書こうという気にもなりません。アブラハムの引き寄せの法則によると、嫌なことはとにかく忘れることが幸せに生きるコツ。まあこれはアブラハムでなくても当たり前と言えば当たり前。だからエッセイのためとはいえ、掘り返して書こうとは思いませんね。
文章力も当然ながら、そこも賞をとる人ととらない人の差につながるのかも。
今また別のエッセイコンテストのための原稿を書いています。今度はたった1600字なので、すぐに書けることは書けるんですが、なかなかテーマが浮かんできませんでした。テーマは約束。テーマに沿っていれば題は自由です。明るいエッセイ募集とのことなので、戦争体験のない私でも大丈夫か?
過去の受賞作品を見てみると、婚約者のおじいさんとの約束とか、中学生のときのサッカーの先生との約束とか、美容師さんが入院中の患者さんとした約束とかの話でした。それでいろいろ考えたんですが、私には思いつくような約束がない!
それでちょっとひねって、水仙の球根をテーマに書くことにしました。秋に植えた球根は、何ヶ月も寒くて暗いイギリスの冬を地面の中ですごし、わたしが忘れたころの早春に花咲いて、春がそこまで来ていることを知らせてくれる。たった30円やそこらで買った球根の約束が守られると言うテーマです。小さいテーマだから、1600字という短さでもまとめやすいし。
でもこれってたぶん主催者の意図とはぜんぜん外れてると思うんですよね。産経新聞の公募なのですが、あのサラ金のプロミスが主催者のようです。だからテーマが約束。こんなぜんぜんヒューマンドラマのない、心の温まらないテーマ、書く前からぜんぜん入賞なんて無理と思って書いています。
なら時間の無駄だからやめれば良いようなものなんですが、やっぱり物好きで書いてます。だめでもともとというよりも、こうやって公募の経験を重ねるのも良い修行だなって思いながら。結局楽しいんですよね。
こういう公募は大体字数が少なくて、これも2000字から4000字だったように記憶しています。そのエッセイを読んだのですが、その三分の一くらいが戦争についてかかれたことでした。被爆してなくなった青年の話や、戦争中に食べようと亀を焼いた話。グライダーの訓練の話など。
それから肉親の死や病気についての話も多くありました。寝たきりになった母親の話。自殺したお姉さんの話。自分を捨てていった母親との再会。憎みあった父親の死。
ほかには不運な人生を送って苦しんで死んでいった患者さんの話。自閉症になった話。会社の同僚が殺人を起こした話。自閉症の娘の話。父親の死。
それから海外での生活の苦労話もありました。言葉の通じない南米に中学生のときに留学した苦労話や、サウジアラビアに親の転勤で住んでいて、現地人の友達と断食(ラマダン)した話。
全体の3分の2くらいはさすが文章がうまいなあ、この人はもう何年も書いてるんだろうなという感じの作品でした。後の3分の1くらいは、これくらいなら私でもがんばればかけるかなという感じでした。
それにしても思ったんですが、テーマが重い。一応エッセイですから、100パーセント実話でなくても、実際の体験に基づいてると思うんですが、なかなかこんな体験は普通の人は持っていません。すると、なんだか普通の体験に基づいて書いたエッセイなんて、こんな重い話と比べればテーマが比較にならないから、初めから勝ち目はないような気がしてきました。それともこれって、負け惜しみ?いえいえ、そんなつもりはないんですが、私には幸いにも戦争体験もないし、肉親が死んだこともないし、それだけでぱっとひきつけるような大きなドラマがないんです。
よくよく考えてみれば、私の母親は子供のころ2回も離婚してるし、自分も離婚してるし、波風ない人生を送ってきたわけでもないんですが、それとて別にエッセイにするほどのことでもない。これは私の分析力、文章力がないせいか?
よくない思い出のことを、深く思い出して書こうという気にもなりません。アブラハムの引き寄せの法則によると、嫌なことはとにかく忘れることが幸せに生きるコツ。まあこれはアブラハムでなくても当たり前と言えば当たり前。だからエッセイのためとはいえ、掘り返して書こうとは思いませんね。
文章力も当然ながら、そこも賞をとる人ととらない人の差につながるのかも。
今また別のエッセイコンテストのための原稿を書いています。今度はたった1600字なので、すぐに書けることは書けるんですが、なかなかテーマが浮かんできませんでした。テーマは約束。テーマに沿っていれば題は自由です。明るいエッセイ募集とのことなので、戦争体験のない私でも大丈夫か?
過去の受賞作品を見てみると、婚約者のおじいさんとの約束とか、中学生のときのサッカーの先生との約束とか、美容師さんが入院中の患者さんとした約束とかの話でした。それでいろいろ考えたんですが、私には思いつくような約束がない!
それでちょっとひねって、水仙の球根をテーマに書くことにしました。秋に植えた球根は、何ヶ月も寒くて暗いイギリスの冬を地面の中ですごし、わたしが忘れたころの早春に花咲いて、春がそこまで来ていることを知らせてくれる。たった30円やそこらで買った球根の約束が守られると言うテーマです。小さいテーマだから、1600字という短さでもまとめやすいし。
でもこれってたぶん主催者の意図とはぜんぜん外れてると思うんですよね。産経新聞の公募なのですが、あのサラ金のプロミスが主催者のようです。だからテーマが約束。こんなぜんぜんヒューマンドラマのない、心の温まらないテーマ、書く前からぜんぜん入賞なんて無理と思って書いています。
なら時間の無駄だからやめれば良いようなものなんですが、やっぱり物好きで書いてます。だめでもともとというよりも、こうやって公募の経験を重ねるのも良い修行だなって思いながら。結局楽しいんですよね。
2009年12月5日土曜日
難解な現代詩
現代詩を読む人口ってどのくらいでしょう?結構日本では雑誌が出ているようだけど、現代詩手帳という雑誌ご存知ですか。そのバックナンバーを手に入れたので、読んでいました。雑誌とはいえぱらぱらとめくれると言う感じではなく、結構敷居が高い感じです。それで、対談やコメントは飛ばして、詩だけを読んでるんですが、うーん、たとえばこの詩、どう思われますか?作者は荒川洋治という、現代詩人の中ではなかなか名前の知られた人です。タイトルは「初恋」
(前略)
不確かな弟の宿題を解くように
肌を合わせ切ってみた
「井原」は戦争の画家となった
この絵でビルマを全部出す
朝食を抜いてもいつもベロが口の中にあった
車の場所を何度も見て
安堵の袋をいっぱいにふくらませた
胸はこんなにいっぱいなのに
違反はひとつ
全部を残して、全部が消え去ることだ
あたりにはふたをもつ森のようにたたかって
「それはわかります。
明日も気をつけて、私の中にこられますように」
超然と奥地で陸稲を刈るひとたちに
定規のような形相が
絵の中に浮かぶ
全部とはおんなだ 婦警のからだは途中から歩き始めた
初恋は過ぎていった
駐車は続き
夕日は下がらない
前半を省略したのでわからないなあと思ってらっしゃるかもしれませんが、前半を読んでもぜんぜんわかりません。前半で出てくるのは、井原という人が画家でビルマにいて、婦警が駐車を取り締まってる。そういうことが書いてありますが、調子としてはこんな感じで、わけがわからない。筋がわからないだけでなく、何が良いたいのかがわからないだけでなく、どこが良いのかがわからない。
それに最後から3行目に初恋が出てきますが、それに関わるようなことは何にも出てこない。それなのにタイトルは初恋。
この詩に限らず、この雑誌の詩は大体こんなもので、すごく難解。こういう詩がわかるどころか、これを鑑賞できるようでなければ、現代詩を読むどころか書くなんてとんでもないって言うことなんでしょうか?
日本に行く前に「文芸思潮」という雑誌の現代詩大賞に応募したところ、二次予選を通過したとのご連絡をいただきました。それでその結果の載った雑誌を送っていただいたんですが、1307人の応募があったそうです。現代詩なんて読者すら少ないだろうに、そんなに書く人がいるんですね。そう思っても、「競争が激しい」という気にはならず、へえ、そんなに詩を書く酔狂な人がいるのか。すごいもんだなあと、なんだか嬉しいと言うか、心づけられる気持ちもします。
この1307人のうちの一人は私ですが、私以外の1306人のうちでも、こんな難解な詩、一体何人の人がわかるんだろう。私以外の人は大体わかるんだろうか?
もちろん難解なほうが良いというわけではないことはわかっていますし、難解な詩もあれば簡単なのもあって、その自由さが現代詩なんですけど、お粗末ながら詩を書くものとしては、こんなにぜんぜん理解できなくて大丈夫だろうか、というか、なんか不安な気持ちがしないではありません。
詩のついでに久しぶりに詩のブログ更新しておきます。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/
(前略)
不確かな弟の宿題を解くように
肌を合わせ切ってみた
「井原」は戦争の画家となった
この絵でビルマを全部出す
朝食を抜いてもいつもベロが口の中にあった
車の場所を何度も見て
安堵の袋をいっぱいにふくらませた
胸はこんなにいっぱいなのに
違反はひとつ
全部を残して、全部が消え去ることだ
あたりにはふたをもつ森のようにたたかって
「それはわかります。
明日も気をつけて、私の中にこられますように」
超然と奥地で陸稲を刈るひとたちに
定規のような形相が
絵の中に浮かぶ
全部とはおんなだ 婦警のからだは途中から歩き始めた
初恋は過ぎていった
駐車は続き
夕日は下がらない
前半を省略したのでわからないなあと思ってらっしゃるかもしれませんが、前半を読んでもぜんぜんわかりません。前半で出てくるのは、井原という人が画家でビルマにいて、婦警が駐車を取り締まってる。そういうことが書いてありますが、調子としてはこんな感じで、わけがわからない。筋がわからないだけでなく、何が良いたいのかがわからないだけでなく、どこが良いのかがわからない。
それに最後から3行目に初恋が出てきますが、それに関わるようなことは何にも出てこない。それなのにタイトルは初恋。
この詩に限らず、この雑誌の詩は大体こんなもので、すごく難解。こういう詩がわかるどころか、これを鑑賞できるようでなければ、現代詩を読むどころか書くなんてとんでもないって言うことなんでしょうか?
日本に行く前に「文芸思潮」という雑誌の現代詩大賞に応募したところ、二次予選を通過したとのご連絡をいただきました。それでその結果の載った雑誌を送っていただいたんですが、1307人の応募があったそうです。現代詩なんて読者すら少ないだろうに、そんなに書く人がいるんですね。そう思っても、「競争が激しい」という気にはならず、へえ、そんなに詩を書く酔狂な人がいるのか。すごいもんだなあと、なんだか嬉しいと言うか、心づけられる気持ちもします。
この1307人のうちの一人は私ですが、私以外の1306人のうちでも、こんな難解な詩、一体何人の人がわかるんだろう。私以外の人は大体わかるんだろうか?
もちろん難解なほうが良いというわけではないことはわかっていますし、難解な詩もあれば簡単なのもあって、その自由さが現代詩なんですけど、お粗末ながら詩を書くものとしては、こんなにぜんぜん理解できなくて大丈夫だろうか、というか、なんか不安な気持ちがしないではありません。
詩のついでに久しぶりに詩のブログ更新しておきます。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/
2009年10月8日木曜日
読書感想文 コヨーテソング


昨日友達とここから車で20分くらいのハートランドというところに海岸の散歩に行きました。海岸といってもここ北デボンは海岸線が荒々しく、ほぼ道なき道を岩沿いに歩きます。寒くなってきたのにサーファーが4人いました。友人によるとこの海岸は実は知る人ぞ知るサーフィンの伝説的なメッカで、年に何度か北斎の海の絵に出てくるような波がやってくるとかで、つわもののサーファーが水に浮かんで波を待っています。ここに来るにはわたしの歩いた海岸沿いにサーフボードを担いで何キロも岩場を歩いていくか、道なき道を車を引っかき傷だらけにしながら藪の中を抜けてくるかしかありません。
伊藤比呂美のコヨーテソングという本を読みました。前も一度読んだんですが、また読みたくなって再読しました。伊藤比呂美さんは詩人です。わたしより10歳年上で青山大学の国文科の出身です。わたしが初めて伊藤さんの詩を読んだのは大学生のとき。「わたしは便器なのか」という詩でした。タイトルのとおりかなりショッキングというか赤裸々なテーマで詩を書く人です。
その頃から彼女のことが好きだったので、あれこれ25年くらいのお付き合いになりますね。その間ずっとフォローしていたのでもないのですが、また最近になって彼女の本をいろいろ読んでます。
その頃は厳戒令下のポーランドに恋人を追いかけて行ったとかで、情熱的な人だなあと思いました。その後(多分)3回結婚して、今はアメリカ人のだんなさんがいて、カリフォルニアに住んでるようです。3人娘さんがいて、一番下の子はアメリカ人とのハーフで、日本語の勉強のために日本につれてきたりと、わたしと同じ様なことしてるようで、身につまされます。
昔は彼女の詩も一応詩らしい体裁をとっていました。韻が云々ではなく、ただ単純に詩の様に見えたということです。でも最近のものは詩なのか散文なのか、よくわからないものが多い。一応、行が段落が終わる前に途中で改行になってるから、詩なのかなあという感じです。でも内容はエッセイ風だったりします。それが何ページも続いて、急に詩のように終わったりだとか、とっても自由な書き方です。でも自由詩というのは、五七五調や韻を踏んだりという規制から外れて自由に書かれるものですから、散文長になっていようと、形式にこだわる必要なないんだから、それはそれで彼女らしくてとても好きです。
彼女は結構テーマにこだわる人なんです。昔はセイタカアワダチソウに凝っていてそれについてたくさん詩を書いてました。毛抜きで毛を抜くこと、生粋の東京弁では「ひ」がうまく発音できなくて、「し」に聞こえること(日比谷がシビヤに聞こえる)にもこだわってました。それでどうも今回はコヨーテにこだわっているようです。
昔子供のころ、シートン動物記でコヨーテのことを読んだのがきっかけでした。それを大人になってアマゾンで検索して英語の古本を手に入れました。それは図書館の本だったのですが、おそらく残酷すぎるという理由で「廃棄本」となりました。残酷というのは、母親コヨーテが授乳して仔をなめていると、そこを射殺され、子らは一匹一匹穴から引きずり出され殺されるという描写ではないかと彼女は書いています。
彼女は昔読んだ日本語訳を覚えているので、その記憶を交えながら、英語と日本語を交えながらその描写を書きます。それがなんとも心を打つんです。かわいそうはかわいそうなんですが、彼女の書き方はセンチメンタルではありません。そこが詩人の詩人たるところなんですよねえ。
その後日、(というかその前かもしれない。この辺は不明)デパートの広告でコヨーテの毛皮が特売になっているのを知り、買い求めます。たぶんこの辺は実話。その殺されたコヨーテの皮を着て、彼女はコヨーテの力を得ていきます。この辺からが詩というか、彼女らしい展開になります。
何しろ当時私は、ごく社会的に、とても家庭的に、秩序正しく生きてましたから、ええ、ただの夢でした、
ジユウニナリタイという、
ドコカニイキタイという、
ゴハンツクルノハモウイヤダという、
コシノヌケルホドセックスシタイという、
中略
コヨーテがささやき声で問いました。
「どんな力が欲しいか。」
わたしはその毛皮に鼻までうずめてイグニッションキイを入れ、
ステアリングを握りながら答えました、
「走る力を」
「死なない命とイヌ科の臭いと跳躍力を」
「それから、はてしない性欲を 」
(「平原色の死骸」より抜粋)
それとは別に、彼女がアメリカを旅して知ったコヨーテに関する伝説や民話のようなものが、これまた彼女の語り口で、詩とも散文ともつかないような書き方でかかれます。コヨーテと鴨娘の話し、コヨーテが小人の子供を腰につけた膀胱に入れて育てる話、コヨーテが人間のおんなに成りすます話し、コヨーテと魔女の話、コヨーテが蛙娘を殺す話。膀胱の話を除いては、コヨーテは好色なオスで、どれもセックスがテーマになってます。
また好きな抜粋を書きます。
平原で。
コヨーテの逃げようとした足を見ました。
罠に残されていて、食いちぎったのだと人々がいいました。
昔におこったことですから、干からびていました。
干からびた足の先。食いちぎられて。
それを見た人々が、おお、ああ、といいました、おお、ああ、と。
苦しかったろうつからったろうと。
どうせ死んでしまっただろうと。
(「風一陣」より抜粋)
或る夜コヨーテが訪ねてきて、
なくした足をわたしに見せた
どうしても食いちぎらねばならなかったのだ
どうしても出ていきたかったのだどうしても、と
行きなよ、とわたしはいってやった
コヨーテにはいろんなことをされたけれど
わたしもいろんなことをしてやった
かみ殺されなかったのが不思議なくらいだ
(「タンブルウィード」より抜粋)
伊藤比呂美のコヨーテソングという本を読みました。前も一度読んだんですが、また読みたくなって再読しました。伊藤比呂美さんは詩人です。わたしより10歳年上で青山大学の国文科の出身です。わたしが初めて伊藤さんの詩を読んだのは大学生のとき。「わたしは便器なのか」という詩でした。タイトルのとおりかなりショッキングというか赤裸々なテーマで詩を書く人です。
その頃から彼女のことが好きだったので、あれこれ25年くらいのお付き合いになりますね。その間ずっとフォローしていたのでもないのですが、また最近になって彼女の本をいろいろ読んでます。
その頃は厳戒令下のポーランドに恋人を追いかけて行ったとかで、情熱的な人だなあと思いました。その後(多分)3回結婚して、今はアメリカ人のだんなさんがいて、カリフォルニアに住んでるようです。3人娘さんがいて、一番下の子はアメリカ人とのハーフで、日本語の勉強のために日本につれてきたりと、わたしと同じ様なことしてるようで、身につまされます。
昔は彼女の詩も一応詩らしい体裁をとっていました。韻が云々ではなく、ただ単純に詩の様に見えたということです。でも最近のものは詩なのか散文なのか、よくわからないものが多い。一応、行が段落が終わる前に途中で改行になってるから、詩なのかなあという感じです。でも内容はエッセイ風だったりします。それが何ページも続いて、急に詩のように終わったりだとか、とっても自由な書き方です。でも自由詩というのは、五七五調や韻を踏んだりという規制から外れて自由に書かれるものですから、散文長になっていようと、形式にこだわる必要なないんだから、それはそれで彼女らしくてとても好きです。
彼女は結構テーマにこだわる人なんです。昔はセイタカアワダチソウに凝っていてそれについてたくさん詩を書いてました。毛抜きで毛を抜くこと、生粋の東京弁では「ひ」がうまく発音できなくて、「し」に聞こえること(日比谷がシビヤに聞こえる)にもこだわってました。それでどうも今回はコヨーテにこだわっているようです。
昔子供のころ、シートン動物記でコヨーテのことを読んだのがきっかけでした。それを大人になってアマゾンで検索して英語の古本を手に入れました。それは図書館の本だったのですが、おそらく残酷すぎるという理由で「廃棄本」となりました。残酷というのは、母親コヨーテが授乳して仔をなめていると、そこを射殺され、子らは一匹一匹穴から引きずり出され殺されるという描写ではないかと彼女は書いています。
彼女は昔読んだ日本語訳を覚えているので、その記憶を交えながら、英語と日本語を交えながらその描写を書きます。それがなんとも心を打つんです。かわいそうはかわいそうなんですが、彼女の書き方はセンチメンタルではありません。そこが詩人の詩人たるところなんですよねえ。
その後日、(というかその前かもしれない。この辺は不明)デパートの広告でコヨーテの毛皮が特売になっているのを知り、買い求めます。たぶんこの辺は実話。その殺されたコヨーテの皮を着て、彼女はコヨーテの力を得ていきます。この辺からが詩というか、彼女らしい展開になります。
何しろ当時私は、ごく社会的に、とても家庭的に、秩序正しく生きてましたから、ええ、ただの夢でした、
ジユウニナリタイという、
ドコカニイキタイという、
ゴハンツクルノハモウイヤダという、
コシノヌケルホドセックスシタイという、
中略
コヨーテがささやき声で問いました。
「どんな力が欲しいか。」
わたしはその毛皮に鼻までうずめてイグニッションキイを入れ、
ステアリングを握りながら答えました、
「走る力を」
「死なない命とイヌ科の臭いと跳躍力を」
「それから、はてしない性欲を 」
(「平原色の死骸」より抜粋)
それとは別に、彼女がアメリカを旅して知ったコヨーテに関する伝説や民話のようなものが、これまた彼女の語り口で、詩とも散文ともつかないような書き方でかかれます。コヨーテと鴨娘の話し、コヨーテが小人の子供を腰につけた膀胱に入れて育てる話、コヨーテが人間のおんなに成りすます話し、コヨーテと魔女の話、コヨーテが蛙娘を殺す話。膀胱の話を除いては、コヨーテは好色なオスで、どれもセックスがテーマになってます。
また好きな抜粋を書きます。
平原で。
コヨーテの逃げようとした足を見ました。
罠に残されていて、食いちぎったのだと人々がいいました。
昔におこったことですから、干からびていました。
干からびた足の先。食いちぎられて。
それを見た人々が、おお、ああ、といいました、おお、ああ、と。
苦しかったろうつからったろうと。
どうせ死んでしまっただろうと。
(「風一陣」より抜粋)
或る夜コヨーテが訪ねてきて、
なくした足をわたしに見せた
どうしても食いちぎらねばならなかったのだ
どうしても出ていきたかったのだどうしても、と
行きなよ、とわたしはいってやった
コヨーテにはいろんなことをされたけれど
わたしもいろんなことをしてやった
かみ殺されなかったのが不思議なくらいだ
(「タンブルウィード」より抜粋)
2009年10月1日木曜日
Procrastination

今日のタイトルのProcrastinationというのは、「ぐずぐずする」と辞書に載っています。もっと詳しく説明すると、やらないといけないこと、やっておいたほうが良いことがあるんだけど、それを先延ばしにしてなかなかやらないこと。
わたしは普通はその日にやらないといけないことは無理してでも済ませて、余裕があれば明日の分もやっておきたいほうです。それはそれで律儀というか、悪い性格ではないと思うんだけど、時々疲れます。昔メキシコに住んでいた人が、メキシコ人は今日しなくても良いことは絶対に今日しないといっていましたが、時々そういう性格になれたらなあと思う。
でもそういう性格のわたしですが、proctastinateして、ぐずぐず先延ばしにしていることがあります。それはエッセイ。
おととしの11月位からふと思い立って、デボンについてのエッセイを書き始めたんです。その頃は今のようにブログをつけていなかったし、日本語を書くのは久しぶりというところでした。それまでにも一度銀行勤めを辞めたときに、毎日家でロンドンについてのエッセイを書いたのですが、初稿が終わったところで放ったらかしにしてありました。そのときは一人暮らしで働いてもいず、一日中書いていられたのですが、ほんと、結構しんどい思いをして書きました。でも本1冊分くらいは書こうとがんばりました。
それが今回はさらさらかけるんです。時間もまとめて取れないし、家事の合間とか、夜子供が寝たあと書いてたんですが、割と短期間に本にするには長すぎるくらい書けました。それが去年の春。それから推敲を何度もして、同時になんとなく出版社に出版の打診とかを始めました。それで結局長すぎるということで、また今年の春過ぎから再び推敲して、3分の2くらいに減らしています。それがそろそろ終わりかけになってきました。
初稿が書き終わったのは1年半くらい前。その間は夢中で書いていましたが、推敲になると結構つまらない。だってもう自分の書きたいことは書いてしまったのだし、気持ちとしてはもう次のことに向かっているから。それで推敲する傍ら、別のエッセイ(奇談集)だとか詩だとか小説だとか、文学賞に出すための原稿なんかを書いています。ブログもそうしているうちにはじめました。
そうしているうちに、気持ちはデボンのエッセイからはますます離れていって、もっと違うことを書きたいし、文学賞だとかコンテストだとか、詩や小説ももっとやりたいなあという気になってきました。
推敲ってやりだすときりがないんですよね。特にワープロだから、いくらでも直せるし、時間を空けて前書いた物を読むと、変えたいところもどうしても出てくる。それでこのデボンのエッセイはこれで終わりにしようと思っています。今最後の章の推敲が終わって、これを縦書きに直しているところ。これが終わったらもう一度はじめから通して読んで、目次を作ってあらすじをまとめて、それで最後にしたいんです。
最後にしたらどうするかというと、また出版社をいくつか当たってみるつもりです。でもそれで良い返事がもらえようともらえまいと、もう書き直すの嫌だなあって言う気になってます。だからはじめに書いたprocrastination。なかなか筆が進まないというか、ワープロに向かう気になれない。もうこれにかかわるのは飽きたという気持ちと同時に、きっぱり足を洗いきれない気持ち。そして本当に最後の推敲が終わったら、もっと熱心に出版社にコンタクトをしない口実がなくなるから、それも怖いというかめんどくさいというか。結局却下されるのが怖いんでしょうね。 Fear of rejection.
でも人生にはけじめが大切というか、パタンとページを閉じて次に進まないといけない時もある。こんなことそんな大げさに言うほどのことでもないんだけど、そういう時が来た気がします。そうしたら今度は書きかけの奇談集にまた取り掛かれるし、小説のほうももうちょっと膨らませたいし、公募ガイドをチェックしてまた文学賞に応募したいしなど。そこからはまた新しいチャレンジというか、楽しみがあります。
こうして思うと、何年も文章をぜんぜん書かなくて、(でもそういえば思い出しましたが、5年位前にロンドン出版の日本語の雑誌に半年ほどエッセイを連載してもらってたこともありました。)それがふとしたきっかけで書いてみようかなという気になって、今ではそれが踏み台となって次の野望というか希望というかが生まれてる。そうして思えば、別にただの趣味のレベルの話ですが、いろんなことがいろいろ良い方向で廻ってきている気がします。ブログをはじめたおかげて知り合った方だとか、長年音信不通になっていてまたお付き合いが始まった方だとか、楽しいことがたくさん増えたし。
One thing always leads to another. そう思えば、デボンのエッセイがどうなろうと、それを書くことによっていろいろまた新たな楽しみや可能性が出てきたわけです。だからそろそProcrastinationもやめて、このエッセイを仕上げなきゃ。
今日の写真は庭に咲いていたひまわり。この週末から寒くなるということなので、切花にして家に入れました。どんなデザイナーのどんな高いインテリア用品よりも、結局本物の花よりぱっと目を引いて部屋を生き生きさせるものってないと思いませんか。その中でもわたしは特にひまわりとチューリップが好きです。
わたしは普通はその日にやらないといけないことは無理してでも済ませて、余裕があれば明日の分もやっておきたいほうです。それはそれで律儀というか、悪い性格ではないと思うんだけど、時々疲れます。昔メキシコに住んでいた人が、メキシコ人は今日しなくても良いことは絶対に今日しないといっていましたが、時々そういう性格になれたらなあと思う。
でもそういう性格のわたしですが、proctastinateして、ぐずぐず先延ばしにしていることがあります。それはエッセイ。
おととしの11月位からふと思い立って、デボンについてのエッセイを書き始めたんです。その頃は今のようにブログをつけていなかったし、日本語を書くのは久しぶりというところでした。それまでにも一度銀行勤めを辞めたときに、毎日家でロンドンについてのエッセイを書いたのですが、初稿が終わったところで放ったらかしにしてありました。そのときは一人暮らしで働いてもいず、一日中書いていられたのですが、ほんと、結構しんどい思いをして書きました。でも本1冊分くらいは書こうとがんばりました。
それが今回はさらさらかけるんです。時間もまとめて取れないし、家事の合間とか、夜子供が寝たあと書いてたんですが、割と短期間に本にするには長すぎるくらい書けました。それが去年の春。それから推敲を何度もして、同時になんとなく出版社に出版の打診とかを始めました。それで結局長すぎるということで、また今年の春過ぎから再び推敲して、3分の2くらいに減らしています。それがそろそろ終わりかけになってきました。
初稿が書き終わったのは1年半くらい前。その間は夢中で書いていましたが、推敲になると結構つまらない。だってもう自分の書きたいことは書いてしまったのだし、気持ちとしてはもう次のことに向かっているから。それで推敲する傍ら、別のエッセイ(奇談集)だとか詩だとか小説だとか、文学賞に出すための原稿なんかを書いています。ブログもそうしているうちにはじめました。
そうしているうちに、気持ちはデボンのエッセイからはますます離れていって、もっと違うことを書きたいし、文学賞だとかコンテストだとか、詩や小説ももっとやりたいなあという気になってきました。
推敲ってやりだすときりがないんですよね。特にワープロだから、いくらでも直せるし、時間を空けて前書いた物を読むと、変えたいところもどうしても出てくる。それでこのデボンのエッセイはこれで終わりにしようと思っています。今最後の章の推敲が終わって、これを縦書きに直しているところ。これが終わったらもう一度はじめから通して読んで、目次を作ってあらすじをまとめて、それで最後にしたいんです。
最後にしたらどうするかというと、また出版社をいくつか当たってみるつもりです。でもそれで良い返事がもらえようともらえまいと、もう書き直すの嫌だなあって言う気になってます。だからはじめに書いたprocrastination。なかなか筆が進まないというか、ワープロに向かう気になれない。もうこれにかかわるのは飽きたという気持ちと同時に、きっぱり足を洗いきれない気持ち。そして本当に最後の推敲が終わったら、もっと熱心に出版社にコンタクトをしない口実がなくなるから、それも怖いというかめんどくさいというか。結局却下されるのが怖いんでしょうね。 Fear of rejection.
でも人生にはけじめが大切というか、パタンとページを閉じて次に進まないといけない時もある。こんなことそんな大げさに言うほどのことでもないんだけど、そういう時が来た気がします。そうしたら今度は書きかけの奇談集にまた取り掛かれるし、小説のほうももうちょっと膨らませたいし、公募ガイドをチェックしてまた文学賞に応募したいしなど。そこからはまた新しいチャレンジというか、楽しみがあります。
こうして思うと、何年も文章をぜんぜん書かなくて、(でもそういえば思い出しましたが、5年位前にロンドン出版の日本語の雑誌に半年ほどエッセイを連載してもらってたこともありました。)それがふとしたきっかけで書いてみようかなという気になって、今ではそれが踏み台となって次の野望というか希望というかが生まれてる。そうして思えば、別にただの趣味のレベルの話ですが、いろんなことがいろいろ良い方向で廻ってきている気がします。ブログをはじめたおかげて知り合った方だとか、長年音信不通になっていてまたお付き合いが始まった方だとか、楽しいことがたくさん増えたし。
One thing always leads to another. そう思えば、デボンのエッセイがどうなろうと、それを書くことによっていろいろまた新たな楽しみや可能性が出てきたわけです。だからそろそProcrastinationもやめて、このエッセイを仕上げなきゃ。
今日の写真は庭に咲いていたひまわり。この週末から寒くなるということなので、切花にして家に入れました。どんなデザイナーのどんな高いインテリア用品よりも、結局本物の花よりぱっと目を引いて部屋を生き生きさせるものってないと思いませんか。その中でもわたしは特にひまわりとチューリップが好きです。
2009年9月29日火曜日
読書感想文 Midnight Press
今日も一人でプールに行きました。今日はちょこっとクロールも交えながら、平泳ぎで1200メートル、ノンストップで泳ぎました。結構自信がついてきた。その気になれば、5キロくらいなら泳げるような気がしてきました。
マイ電動ドリルの話がコメントで出ましたが、私もマイかなづちを持ってます。これです。よく見るとgirly hammerと書いてあります。girlyというのはただ「女の子の」という意味だけではなく、「おんなおんなした」というか、ほんのちょっとさげずむ様なな意味合いのある言葉です。でもこれがよくできていて、持つところをあけるといろいろなサイズのドライバーが出てきます。
マイ電動ドリルの話がコメントで出ましたが、私もマイかなづちを持ってます。これです。よく見るとgirly hammerと書いてあります。girlyというのはただ「女の子の」という意味だけではなく、「おんなおんなした」というか、ほんのちょっとさげずむ様なな意味合いのある言葉です。でもこれがよくできていて、持つところをあけるといろいろなサイズのドライバーが出てきます。


さて、今日書くのは、1年ほど前に日本から2冊送ってもらったMidnight Pressという詩の雑誌についての読書感想です。内容は半分くらいが詩で、半分くらいが散文とか書評とかインタービュー、対談になっています。
詩のほうはわかりにくいというか、難解な詩が多い。こういうのをまじめにこつこつ読むのはしんどいので、1日ひとつとか二つのペースでさらりと読んで、気に入ったのだけ読み返すという読み方をしていました。
学校で読まされた詩って、読解だとか意味を考えたりだとか無理やり暗誦させられたりだとか、堅苦しい読み方が多かったですよね。でも本当はそんな読み方よりも、意味なんか考えずただ気に入ったものだけを何度も読んで、それでその一部だけでも記憶に残って、ふとしたときに思い出す、なんていうのが詩を読む醍醐味ではないかなあと思うようになりました。その詩の一部を自分の考え方の一部に取り込んでしまうような。
詩っていうのは歌にもつながるもので、意味だけでなくリズムだとか音感が大切な要素ですから、気づいたら覚えてた、口ずさんでたというのが、詩なんじゃないかなあ。
たとえば私は時々美しい光景なんかに出会うと「世はすべてこともなし」っていう言葉が浮かんできて、どう頭をひねってもこれ以上の表現って思いつきません。それでこれがどこから来たかというと、多分ロバート・ブラウニングというイギリスの詩人の詩の翻訳を昔どこかで読んだのが頭に残ってるんだと思うんだけど、その辺は良くわからない。でも確かに、この一節は私の精神の一部になってるんです。
ああ話がそれた。midnight pressにもどると、谷川俊太郎が田村さと子というラテンアメリカ専門の詩人をインタビューする記事があります。これを読むと、詩にはぜんぜん関係ないんだけど、南米ってほんとに半端じゃなくまだ危ない国なんだなあと、しみじみ思いました。英語ではLife is cheapという表現があって、これって命は尊いの逆なんだけど、ほんと南米ではライフ・イズ・チープなんだなあ。
それから谷川俊太郎さん。彼って戦後の日本を代表する現代詩の第一人者ですが、彼って詩人的な敷居の高いところがぜんぜんなくって、今ではかなりお年だと思うのに、すごく精力的にいろいろ活躍されています。この雑誌でも、詩はもちろん載っているし、前述のインタビューだとか、アバンガルドでパンク的な若者の詩のムーブメントに参加して、その対談をしたり。彼って昔はスヌーピーの漫画を翻訳していたし、確か鉄腕アトムの作詞も、宮崎駿のアニメ、ハウルの動く城の主題曲の作詞も彼だったように記憶しています。もっとも彼の書いた本によると、「詩では食べていけないから」ということなんですが。谷川俊太郎でも詩で食べてはいけないんだなあ。
あとは詩の教室というページがあります。これはある意味ではとっても日本的だと思いました。投稿されてきた詩を分析して批評するわけですが、こういうのってすごく勉強になる反面、それはある一人の詩人(おそらく)の意見でしかない。その辺を忘れないで読むと、とっても参考になるけど、こういうのをまったく文面とおりに100パーセント真に受ける人もいるんだろうなあ。すごい詩人とか作家とかアーティストって言うのは、こんな風に細かく分析されて徐々に上達するというようなものでもない気もします。他人の批判だとか規制の価値観なんかをぜんぜん意に介さないほどでないと、すごい詩人にも芸術家にもなれないんじゃないかなあ。まあわたしのような人間には、ありがたい記事ですが。
ひとつ気に入った詩を見つけたので載せます。岡田すみれこという詩人です。彼女の詩が何篇か載っていて、結婚して何年も経つ旦那との仲が今ひとつうまく行っていないんだろうなあと思わせる詩のあとに、これが出てきます。
「わたしとかれ」
三日ほど家を空けた
猫は玄関に寝そべったまま
黙って待っていたという
わたしが帰宅すると
家人の間からのっそり顔を出して見上げた
夜も更けたので寝ようと思うと
かれは階段の横に
ひっそりとすわっていた
秘密の約束のように
わたしは胸躍らせてしゃがみこみ
深い思索のようなかれの目を見つめて
柔らかな毛並みに手を入れる
確かめるようにわたしのからだの匂いを
何度も嗅いでいるときに
ふっと電気が消えた
「わたしね、かえってきたでしょ?
でもまた出かけるのよ」
「知ってるよ、またいなくなるんだね」
暗闇の中で会話をすれば
ほてったからだに猫の小さな鼻が冷たく
心地よい
その夜かれは
夫のベッドの脇をすり抜けて
わたしの腕の中にそっと滑り込んできた
つかの間の愛しい時間を、慈しむかのように
この猫との会話がなんだか胸にひしひしと来ます。それでどういうわけで、この人は3日家を空けていて、また出て行くのかなあとか、あまり良い事情ではないんだろうなあとか、そんな大変なときに猫なんてかまってる余裕はないんだろうけど、その中にあってつかの間の猫との会話がなんか心に響くんですよね。猫と人間の愛情、なんていう安っぽい感情以上のいろいろなものを感じます。
こんなに良い詩のあとで恐縮ですが、わたしも詩のブログのほうにひとつ載せましたので、よかったら見てやってください。短いですから。
http://fordfarmpoems.blogspot.com/
リクエストをいただきましたので、そこに去年撮ったこの辺の海の写真を載せましたが、詩アレルギーの人のために同じ写真をここにも載せておきます。

2009年8月23日日曜日
Practice makes perfect
え、あつこさんが文学?と驚かれたので、ちょっといきさつを書いてみたいと思います。
詩のほうは、2月ごろのブログに書きましたが、中学生のときから、なんとは無くノートに書き綴っていました。どうしてそういうことになったのかは覚えていませんが、詩との始めての出会いは小学2年生位かな。誰かが詩の本(書き方だとか読み方だとか)をくれて、そのときに詩とはどういうものか初めて知りました。といっても今でも詩は何かと聞かれれば、なかなか答えにくいものだけれど、そのときの印象は、「詩って短くて簡単で、誰でもかけるんだなあ。」というものだったと思います。それが良かったのかもしれない。だってそうでなければ、詩ってとっつきにくいものだなあと思ってもおかしくないですからね。
イギリスの学校では子供たちはよく詩を書かされます。でもイギリスの詩は、日本の小学生が習う現代詩、自由詩とは違うんです。「韻文」という言葉があるように、基本的に英語の詩は韻を踏むんです。だから子供はゲーム感覚で入っていきます。たとえばルイはCrab called Barbという詩を昔書いていました。クラブとバーブの最後が韻になっているでしょ。
でも私は日本の小学校で、詩を書いた記憶はありません。作文は覚えているけれど。自由詩ってルールもないし、先生には教えにくいのかもしれません。
とにかく中学生位から詩を書き始めたのですが、だんだん大人になるにしたがって、書かなくなりました。イギリスに来てからは、ほんのいくつかしか書きませんでした。
エッセイのほうは、15年位前、イギリスの銀行を辞めたときに、しばらく家にいたので、この機会にとロンドンについてのエッセイを書きました。でも1日中家にいて集中して書いたのが返ってよくなかったのか、結構書くのが大変だった。それでも一応書き上げたのですが、人に話を聞いてみると、そのころはロンドンについてのエッセイは山ほど出版されていて飽和状態とのことで、結局は出版社に送ることも無く、それどころか本格的に推敲することも無く、それっきりになっていました。
それが3年位前、ある日本人の人と話していて、その人が転勤で地方の支店に行ったときのことをエッセイにしたいという話を聞いて、私も書こうと思いつきました。今度はロンドンではなくて、イギリスのど田舎のことなので、また違ったアングルで、興味を持ってくれる人もいるのではないかと思ったからです。
それで仕事や家事の合間、子供が学校に行っているときや夜に書いていると、するするかけるんです。あっという間にとはいいませんが、割と短期間で原稿用紙にすれば500枚くらいになってしました。それができたのが今から1年以上前。その後何回か推敲しながら、同時に出版社に当たってみましたが、なかなか良い返事は来ません。今回はそれでぐっとポイントを絞って、3分の2くらいまで減らしました。まああきらめずに、出版社を当たってみようと思っています。
まあそんなことをしているうちに、詩もまたぼちぼちと書き始めました。書いていると思うんですが、私は本当は詩のほうが好きなのかも知れません。エッセイは前後の説明が多いので、書いていて結構退屈な部分もあるし、常に読者を意識して書くけれど、詩はまったく前後の説明なしで、どこまで読者が理解してくれるかとは別の次元で書くので、自己満足だけの世界といえば、まったくそのとおりです。わかってくれる人だけがわかってくれれば良い、というのが基本的な姿勢ですから、どうしようもないですね。
でも詩って何かインスピレーションがないとかけないなあと思うのですが、本当に詩人はそんなもの待っていないようです。とにかく毎日何かを書く。それが大切らしい。それで私もそれを見習おうと、毎日10分でひとつ詩を書くようにしていた時期(1年位前)もあったのですが、いつの間にかそれもやめてしまいました。そんな機械的なやり方、なんとなく詩人らしくないなあという気もしないではありませんでした。
今回、昨日ブログに書いた文学賞に送った詩は3篇で、「私たちが求めるもの」「ボブ・ディラン」「裏切る」というタイトルです。そのうちの「ボブ・ディラン」は、そういえばこんな風に毎晩10分で書いていた詩のうちから膨らませたひとつでした。はじめの「微笑まないユダヤ人」という出だしが気に入った以外はぜんぜん駄作だったのですが、どういうわけか手を入れているうちに、ひとつ送ってみるかという気になるくらい膨らみました。
そんな風に考えると、やっぱりPractice makes perfectですね。インスピレーションなんて頼りにならないものを待っていないで、毎日こつこつと歯を磨くように詩を書いていれば、そのうち何かまた書けるかもしれません。せっかくこんな風に少しでも評価してくださる人がいたので、がんばろうという気になっています。
詩のほうは、2月ごろのブログに書きましたが、中学生のときから、なんとは無くノートに書き綴っていました。どうしてそういうことになったのかは覚えていませんが、詩との始めての出会いは小学2年生位かな。誰かが詩の本(書き方だとか読み方だとか)をくれて、そのときに詩とはどういうものか初めて知りました。といっても今でも詩は何かと聞かれれば、なかなか答えにくいものだけれど、そのときの印象は、「詩って短くて簡単で、誰でもかけるんだなあ。」というものだったと思います。それが良かったのかもしれない。だってそうでなければ、詩ってとっつきにくいものだなあと思ってもおかしくないですからね。
イギリスの学校では子供たちはよく詩を書かされます。でもイギリスの詩は、日本の小学生が習う現代詩、自由詩とは違うんです。「韻文」という言葉があるように、基本的に英語の詩は韻を踏むんです。だから子供はゲーム感覚で入っていきます。たとえばルイはCrab called Barbという詩を昔書いていました。クラブとバーブの最後が韻になっているでしょ。
でも私は日本の小学校で、詩を書いた記憶はありません。作文は覚えているけれど。自由詩ってルールもないし、先生には教えにくいのかもしれません。
とにかく中学生位から詩を書き始めたのですが、だんだん大人になるにしたがって、書かなくなりました。イギリスに来てからは、ほんのいくつかしか書きませんでした。
エッセイのほうは、15年位前、イギリスの銀行を辞めたときに、しばらく家にいたので、この機会にとロンドンについてのエッセイを書きました。でも1日中家にいて集中して書いたのが返ってよくなかったのか、結構書くのが大変だった。それでも一応書き上げたのですが、人に話を聞いてみると、そのころはロンドンについてのエッセイは山ほど出版されていて飽和状態とのことで、結局は出版社に送ることも無く、それどころか本格的に推敲することも無く、それっきりになっていました。
それが3年位前、ある日本人の人と話していて、その人が転勤で地方の支店に行ったときのことをエッセイにしたいという話を聞いて、私も書こうと思いつきました。今度はロンドンではなくて、イギリスのど田舎のことなので、また違ったアングルで、興味を持ってくれる人もいるのではないかと思ったからです。
それで仕事や家事の合間、子供が学校に行っているときや夜に書いていると、するするかけるんです。あっという間にとはいいませんが、割と短期間で原稿用紙にすれば500枚くらいになってしました。それができたのが今から1年以上前。その後何回か推敲しながら、同時に出版社に当たってみましたが、なかなか良い返事は来ません。今回はそれでぐっとポイントを絞って、3分の2くらいまで減らしました。まああきらめずに、出版社を当たってみようと思っています。
まあそんなことをしているうちに、詩もまたぼちぼちと書き始めました。書いていると思うんですが、私は本当は詩のほうが好きなのかも知れません。エッセイは前後の説明が多いので、書いていて結構退屈な部分もあるし、常に読者を意識して書くけれど、詩はまったく前後の説明なしで、どこまで読者が理解してくれるかとは別の次元で書くので、自己満足だけの世界といえば、まったくそのとおりです。わかってくれる人だけがわかってくれれば良い、というのが基本的な姿勢ですから、どうしようもないですね。
でも詩って何かインスピレーションがないとかけないなあと思うのですが、本当に詩人はそんなもの待っていないようです。とにかく毎日何かを書く。それが大切らしい。それで私もそれを見習おうと、毎日10分でひとつ詩を書くようにしていた時期(1年位前)もあったのですが、いつの間にかそれもやめてしまいました。そんな機械的なやり方、なんとなく詩人らしくないなあという気もしないではありませんでした。
今回、昨日ブログに書いた文学賞に送った詩は3篇で、「私たちが求めるもの」「ボブ・ディラン」「裏切る」というタイトルです。そのうちの「ボブ・ディラン」は、そういえばこんな風に毎晩10分で書いていた詩のうちから膨らませたひとつでした。はじめの「微笑まないユダヤ人」という出だしが気に入った以外はぜんぜん駄作だったのですが、どういうわけか手を入れているうちに、ひとつ送ってみるかという気になるくらい膨らみました。
そんな風に考えると、やっぱりPractice makes perfectですね。インスピレーションなんて頼りにならないものを待っていないで、毎日こつこつと歯を磨くように詩を書いていれば、そのうち何かまた書けるかもしれません。せっかくこんな風に少しでも評価してくださる人がいたので、がんばろうという気になっています。
登録:
投稿 (Atom)

