2020年5月2日土曜日
コロナウィルスロックダウン 39,40日目、お花見
今日は毎年恒例のお花見をしました。うちにあるのは桜の木は一本だけ(しかもさくらんぼうの木)で、あとはリンゴと梨の木がたくさんあり、リンゴの花が美しく咲くので、リンゴで花見です。が、今年はどういうわけかリンゴの花が例年の5分の1くらいで、その代わりに桜が例年の5倍くらい咲いて、今年は桜のお花見です。
直前に、母の4年目の命日だと気づいて、命日の集い(?)を兼ねて。
今週は雨で気温も下がったけど、天気、花状態、太陽の3つの条件がぴったりマッチすることなどあまりありません。今朝も朝は曇っていたのですが、天気予報を信じてお弁当を準備したら、ぴったりと午後1時には太陽が射してきました。
毎年恒例と書きましたが、本当なら去年が最後のはずなのでした。だってルイとチャーリーは普通ならこの季節は大学ですからね。コロナのせいで(おかげで)こうして今年もお花見できました。家人デイブと二人なら、絶対やろうとは思いませんからね。一人で花の下でワイン飲みますよ。
ではこちらもよろしくお願いします。
2020年4月18日土曜日
コロナウィルスロックダウン 26日目 スーパーでの出来事
昨日のことなのですが、チャーリーと一緒に週に一度の買い物に行きました。最近は入るのに並ばされるし、レジは混むし、中はギスギスした雰囲気だし、気が重いです。
昨日行ったスーパーは列はなかったのですが、入るところで、ひと家族につき一人しかダメといわれました。それで、「我々は一緒に住んではいるが、食事の買い物は別々」とうそをついて入りました。中に入ると、一緒に買い物してる大人同士の家族連れはいたので、どういうわけだったんでしょうね。
二人で一つずつ別々のトローリーを持たされたので、せっかくなので、本当にちょっと別々に買い物しました。チャーリーは肉をほとんど食べないし、家族と違うものを食べることが多いので、まんざら嘘というわけでもありません。
支払いのレジは混んでいて、別々の列に並びました。チャーリーのほうが物が少なかったので、先に清算して店を出て、車の隣で私が終わるまで10分近く待っていました。
私もやっとパッキングを終え車に行くと、チャーリーが、携帯のアップルペイが使えなかったとのこと。合計15ポンドちょっとだったのですが、現金は10ポンドしか持ってませんでした。私に声をかけれくれたらよかったのに、どこにいるかわからなかったようで、困ったチャーリーは「じゃあ5ポンド分返します。」といったら、後ろに並んでいた男性が、「僕が払うよ」と言ってくれたそうです。(長く待たされて、もーええってー、となってたのかも)。そうもいきませんからチャーリーは断ったのですが、結局払ってくれて、「チャリティーに寄付しといて。」と言われたとか。
こういう話、人からも聞いたことあるのですが、本当に親切な人っているものですね。
それで昨日、忘れないうちに10ポンド「国境なき医師団」のCovid-19アピールに寄付しておきました。
ではこちらもよろしくお願いします。
昨日行ったスーパーは列はなかったのですが、入るところで、ひと家族につき一人しかダメといわれました。それで、「我々は一緒に住んではいるが、食事の買い物は別々」とうそをついて入りました。中に入ると、一緒に買い物してる大人同士の家族連れはいたので、どういうわけだったんでしょうね。
二人で一つずつ別々のトローリーを持たされたので、せっかくなので、本当にちょっと別々に買い物しました。チャーリーは肉をほとんど食べないし、家族と違うものを食べることが多いので、まんざら嘘というわけでもありません。
支払いのレジは混んでいて、別々の列に並びました。チャーリーのほうが物が少なかったので、先に清算して店を出て、車の隣で私が終わるまで10分近く待っていました。
私もやっとパッキングを終え車に行くと、チャーリーが、携帯のアップルペイが使えなかったとのこと。合計15ポンドちょっとだったのですが、現金は10ポンドしか持ってませんでした。私に声をかけれくれたらよかったのに、どこにいるかわからなかったようで、困ったチャーリーは「じゃあ5ポンド分返します。」といったら、後ろに並んでいた男性が、「僕が払うよ」と言ってくれたそうです。(長く待たされて、もーええってー、となってたのかも)。そうもいきませんからチャーリーは断ったのですが、結局払ってくれて、「チャリティーに寄付しといて。」と言われたとか。
こういう話、人からも聞いたことあるのですが、本当に親切な人っているものですね。
それで昨日、忘れないうちに10ポンド「国境なき医師団」のCovid-19アピールに寄付しておきました。
ではこちらもよろしくお願いします。
2020年1月28日火曜日
解脱・出家・孤高
先日の続きです。
まず解脱と書きましたが、一番いい日本語ってなんでしょうね?出家?ネットで探してみたら、「俗塵を避ける」という言葉がありましたが、これいいですね。他になにかいい言葉があれば教えてください。
ラーマクリシュナは解脱の敵は「金と女」とよく言っていました。「女」とは、つまり妻帯して家族に対する責任ができることです。そうなると、世の中とのかかわりを断つことなんて無理だということです。
で、自分の話です。
私は物質的なたちではないと思うけど、やっぱりお金によるバックアップなしでは生きていけない。そして、もうすでに子供がいて、家庭とのかかわりと断つこともできない。それでも、どうすれば少しでも解脱の心境に近づくには、具体的には何から始めたらいいのか、考えてみました。
まず、ニュースの見過ぎはよくないと思います。ニュースを見すぎると、政治とか社会に対していろいろ言いたいことも増えるし、不安に思うことも増えます。いろんなことに対してオピニオンが出来すぎてしまう。そしてこれをフェースブックに書いたりしたら、ますます世間に巻き込まれてしまいます。
それからニュースに限らす、フェースブックもほどほどにしたほうがいいですね。いろいろ言いたいこととか、呆れることとが増えてきますから。
ゴシップをしない。特に人の悪口は言わない。これはまあ当たり前です。
物を買わない。服だとかインテリアとか趣味の物とか、買い物する癖がつくと、その「服」とか「インテリア」について考える時間が、世間にまみれてる感じがします。
お金のことですが、まず、数える(帳簿や通帳を見る)のはよくないと思います。と言っても、私の様に現金で支払われる自由業の人は、簿記もしないといけないし、全く数えないわけにもいかないんだけど、それでもなるべく数えたり計算したりしないようにしようと思います。
それからこれは一番大きいテーマですが、お金を人にあげるというのは、すごくいいことと思います。ホームレスの人やチャリティー。もっと頑張りたいことです。子供たちにも、機会があるごとに渡そうと思います。
「解脱」という意味では、ほとんど全部のお金をあげて、「必要なものはどこからか与えられるもの」と腹をくくって生きるのが一番なんですけど、私には現生では到底たどり着けない境地です。
家族とのかかわりが私にとっては一番の「世の中とのつながり」であるわけですが、これは難しいですね。誰かを愛すれば、それは自分にとっては足かせになるわけですから。子供たちに関しては、「健康で幸せ」であってくれさえすれば、その他のことは何でもいいとは思ってますが。 でもこれだけでも、十分すぎる望みかな。
ではこちらもよろしくお願いします。
まず解脱と書きましたが、一番いい日本語ってなんでしょうね?出家?ネットで探してみたら、「俗塵を避ける」という言葉がありましたが、これいいですね。他になにかいい言葉があれば教えてください。
ラーマクリシュナは解脱の敵は「金と女」とよく言っていました。「女」とは、つまり妻帯して家族に対する責任ができることです。そうなると、世の中とのかかわりを断つことなんて無理だということです。
で、自分の話です。
私は物質的なたちではないと思うけど、やっぱりお金によるバックアップなしでは生きていけない。そして、もうすでに子供がいて、家庭とのかかわりと断つこともできない。それでも、どうすれば少しでも解脱の心境に近づくには、具体的には何から始めたらいいのか、考えてみました。
まず、ニュースの見過ぎはよくないと思います。ニュースを見すぎると、政治とか社会に対していろいろ言いたいことも増えるし、不安に思うことも増えます。いろんなことに対してオピニオンが出来すぎてしまう。そしてこれをフェースブックに書いたりしたら、ますます世間に巻き込まれてしまいます。
それからニュースに限らす、フェースブックもほどほどにしたほうがいいですね。いろいろ言いたいこととか、呆れることとが増えてきますから。
ゴシップをしない。特に人の悪口は言わない。これはまあ当たり前です。
物を買わない。服だとかインテリアとか趣味の物とか、買い物する癖がつくと、その「服」とか「インテリア」について考える時間が、世間にまみれてる感じがします。
お金のことですが、まず、数える(帳簿や通帳を見る)のはよくないと思います。と言っても、私の様に現金で支払われる自由業の人は、簿記もしないといけないし、全く数えないわけにもいかないんだけど、それでもなるべく数えたり計算したりしないようにしようと思います。
それからこれは一番大きいテーマですが、お金を人にあげるというのは、すごくいいことと思います。ホームレスの人やチャリティー。もっと頑張りたいことです。子供たちにも、機会があるごとに渡そうと思います。
「解脱」という意味では、ほとんど全部のお金をあげて、「必要なものはどこからか与えられるもの」と腹をくくって生きるのが一番なんですけど、私には現生では到底たどり着けない境地です。
家族とのかかわりが私にとっては一番の「世の中とのつながり」であるわけですが、これは難しいですね。誰かを愛すれば、それは自分にとっては足かせになるわけですから。子供たちに関しては、「健康で幸せ」であってくれさえすれば、その他のことは何でもいいとは思ってますが。 でもこれだけでも、十分すぎる望みかな。
ではこちらもよろしくお願いします。
2018年12月3日月曜日
I am time, the great destroyer of the world.
9月からオックスフォード大学のインド研究所のオンライン講座で、インドの聖典のバガヴァッド・ギータの12週間のコースを受けています。今はもうレクチャーは終わって、今月23日の課題の提出に向けてレポートを書いているところです。
このバガヴァッド・ギータとはクリシュナ(多分知っている人もいるであろうインドの青い神様)がアージュナという主人公に霊的指導を授ける話です。アージュナとクリシュナは友達で従妹であり、今まさに一緒の馬車に乗って戦いに挑もうとしているのですが、その場での会話がこのバガヴァッド・ギータです。
アージュナはクリシュナが霊的な存在であるということは薄々知っているようですが、神であるとは知りませんでした。本の後半で、クリシュナはいよいよ自分が実は神であることを語ります。その内容が長々と語られるのですが、そのうちの一言で、次のようなものがあります。
I am time, the great destroyer of the world.
(私は時間、すなわちこの世を破壊する者である)
これってすごく深いなあって思うんです。破壊も創造も同じとみなすインド哲学。ちなみにシヴァという神は破壊の神です。(カーリという女神も破壊の神で、深く信仰され愛されています。)
それで思い出したことがありました。数年前イギリスのテレビで、一般人向けの(でも難しかったです)量子物理学の番組をやっていたのですが、そこで時間とは何かを説明していました。
量子物理学的には、時間とは秩序から混沌(From order to chaos)への流れとのこと。
これって全くクリシュナの言葉と同じではありませんか!バガヴァッド・ギータが書かれたのは紀元前200-400年ですよ。
そうなんですよ、インド哲学を勉強すると、本当にこんな風に驚くようなことがたくさん出てきます。インド哲学すごいですよ。
ではこちらもよろしくお願いします
このバガヴァッド・ギータとはクリシュナ(多分知っている人もいるであろうインドの青い神様)がアージュナという主人公に霊的指導を授ける話です。アージュナとクリシュナは友達で従妹であり、今まさに一緒の馬車に乗って戦いに挑もうとしているのですが、その場での会話がこのバガヴァッド・ギータです。
アージュナはクリシュナが霊的な存在であるということは薄々知っているようですが、神であるとは知りませんでした。本の後半で、クリシュナはいよいよ自分が実は神であることを語ります。その内容が長々と語られるのですが、そのうちの一言で、次のようなものがあります。
I am time, the great destroyer of the world.
(私は時間、すなわちこの世を破壊する者である)
これってすごく深いなあって思うんです。破壊も創造も同じとみなすインド哲学。ちなみにシヴァという神は破壊の神です。(カーリという女神も破壊の神で、深く信仰され愛されています。)
それで思い出したことがありました。数年前イギリスのテレビで、一般人向けの(でも難しかったです)量子物理学の番組をやっていたのですが、そこで時間とは何かを説明していました。
量子物理学的には、時間とは秩序から混沌(From order to chaos)への流れとのこと。
これって全くクリシュナの言葉と同じではありませんか!バガヴァッド・ギータが書かれたのは紀元前200-400年ですよ。
そうなんですよ、インド哲学を勉強すると、本当にこんな風に驚くようなことがたくさん出てきます。インド哲学すごいですよ。
ではこちらもよろしくお願いします
2018年10月11日木曜日
強靭
高校を卒業するときの文集のアンケートで、何が一番欲しいかみたいなことを聞かれました。「強靭な心」って答えたと思うんですが、友達が一人「タフな心」と答えていて、この人も同じようなこと考えてるんだなあと思ったことがあります。
強靭な心。そのころは、何があっても凹まないしょげない落ち込まない強い心って思ってました。メンタル強いっていうのかな。
大人になって、ちょっと見方が変わったかな。鋼のようにタフなわけではなく、かといって柳のように折れずに曲がって受け流すというわけでもなく、何が起ころうと、「そういうこともあります。」と淡々と生きていく力というか。達観かな。
先日書いたインドの聖典の バガヴァッドギーターにはこう出ています。
Equally welcoming pain and pleasere, self-sustained and brave, to whom a clod of earth, a peice of stone and a nugget of gold are just the same, who makes no defifference between those that are dear and those who are not and is the same in praise or blame.
The same in honour and calmny, the same to freind and foe; having abandoned all worldly undertaking - such a one is declared as having overcome natural propensities.
(苦しみも喜びも同じく受け入れ、自立し勇敢で、土くれも石も金塊も区別せず、近しい人もそうでない人にも同じく接し、褒められようと咎められようと変わらない。
讃えられようと中傷されようと 変わりなく、友人にも敵にも同じく接し、世俗とのかかわりを捨てた人。こういう人は生まれつきの性質を克服したと言える。)
有名人でメンタル強いなあと思う人は、羽生君です。オリンピックでは泣いてたけどね。まあそういうところがまた、強靭でもやっぱり人間なんだなあって感じて、余計に愛しくなりますよね。
そう言えばそろそろ日本ではスケートシーズン?
ではこちらもよろしくお願いします
強靭な心。そのころは、何があっても凹まないしょげない落ち込まない強い心って思ってました。メンタル強いっていうのかな。
大人になって、ちょっと見方が変わったかな。鋼のようにタフなわけではなく、かといって柳のように折れずに曲がって受け流すというわけでもなく、何が起ころうと、「そういうこともあります。」と淡々と生きていく力というか。達観かな。
先日書いたインドの聖典の バガヴァッドギーターにはこう出ています。
Equally welcoming pain and pleasere, self-sustained and brave, to whom a clod of earth, a peice of stone and a nugget of gold are just the same, who makes no defifference between those that are dear and those who are not and is the same in praise or blame.
The same in honour and calmny, the same to freind and foe; having abandoned all worldly undertaking - such a one is declared as having overcome natural propensities.
(苦しみも喜びも同じく受け入れ、自立し勇敢で、土くれも石も金塊も区別せず、近しい人もそうでない人にも同じく接し、褒められようと咎められようと変わらない。
讃えられようと中傷されようと 変わりなく、友人にも敵にも同じく接し、世俗とのかかわりを捨てた人。こういう人は生まれつきの性質を克服したと言える。)
有名人でメンタル強いなあと思う人は、羽生君です。オリンピックでは泣いてたけどね。まあそういうところがまた、強靭でもやっぱり人間なんだなあって感じて、余計に愛しくなりますよね。
そう言えばそろそろ日本ではスケートシーズン?
ではこちらもよろしくお願いします
2018年10月5日金曜日
「インドの光」読書感想
日本から持ってきてもらった上記のタイトルの本がすごくよかったので、ちょっと書きます。作者は田中カン玉(カンギョク、女偏に間という漢字です)
これはラーマクリシュナという19世紀のインドの聖人についての本です。このころは、インドはイギリスの植民地支配の元で、自国のアイデンティティについていろいろ考えが発達した時期で、このラーマクリシュナをはじめ、ラマナ・マハルシとかシルディ・サイババ(あの有名なサティア・サイババの前世とのこと)とか、女性の聖人のアーナンダマイ・マーとか、有名な聖人がたくさん出てきました。
ラーマクリシュナについてちょっと書きます。彼は貧しいバラモンの家庭に生まれ、早くに父を亡くしろくに学校にも行かず、生活のために寺院の僧侶の地位につきます。(寺院の僧侶はインドではすごく身分が低いそうです。)そこで悟りを得、素晴らしい教えを残しました。ラーマクリシュナの素晴らしさは書きだすときりがないんですが、「まるで5歳の子供のように」純粋な信仰と教えを貫いた人です。
が、、この本の一番素晴らしいところは、この作者田中カンギョクさんです。
この手の昔のインドの聖人についての本って、大体英語で書かれた本の翻訳がほとんどなんですが、この本はそうではありません。すごく丁寧にわかりやすく書かれてあり、すごく文章のセンスがいいです。文才があるっていうのかな。
しかもこのカンギョクさん(女性)はインド哲学の学者でも僧侶でもなく、どうやら「普通の」おばさんのようなんです。自分では「碌な大学も出ていない」とあとがきに書いてらっしゃいます。
戦争の時代に学校に通い、その後結婚して子供を育てながら、中国語やロシア語の語学に興味を持ちます。そしてその後インドの霊的指導 、ヴィヴィーケーナンダの講演を読んだのを機にラーマクリシュナのことを知り、ヒンズー語、サンスクリット語を学び、ベンガル語で書かれたラーマクリシュナの教えの本を翻訳するに至ります。文才もありますが、語学センスもあるんですね。
その後その翻訳等をもとにこの本を書き、それを昭和49年に自費出版したのがこれです。
そしてその本は昭和55年に中公文庫から再版になり、今私が手にしている本は1991年の出版です。 この夏日本のアマゾンで古本で買いました。
ま、興味おありの人は少ないでしょうが、お勧めです。
ではこちらもよろしくお願いします
これはラーマクリシュナという19世紀のインドの聖人についての本です。このころは、インドはイギリスの植民地支配の元で、自国のアイデンティティについていろいろ考えが発達した時期で、このラーマクリシュナをはじめ、ラマナ・マハルシとかシルディ・サイババ(あの有名なサティア・サイババの前世とのこと)とか、女性の聖人のアーナンダマイ・マーとか、有名な聖人がたくさん出てきました。
ラーマクリシュナについてちょっと書きます。彼は貧しいバラモンの家庭に生まれ、早くに父を亡くしろくに学校にも行かず、生活のために寺院の僧侶の地位につきます。(寺院の僧侶はインドではすごく身分が低いそうです。)そこで悟りを得、素晴らしい教えを残しました。ラーマクリシュナの素晴らしさは書きだすときりがないんですが、「まるで5歳の子供のように」純粋な信仰と教えを貫いた人です。
が、、この本の一番素晴らしいところは、この作者田中カンギョクさんです。
この手の昔のインドの聖人についての本って、大体英語で書かれた本の翻訳がほとんどなんですが、この本はそうではありません。すごく丁寧にわかりやすく書かれてあり、すごく文章のセンスがいいです。文才があるっていうのかな。
しかもこのカンギョクさん(女性)はインド哲学の学者でも僧侶でもなく、どうやら「普通の」おばさんのようなんです。自分では「碌な大学も出ていない」とあとがきに書いてらっしゃいます。
戦争の時代に学校に通い、その後結婚して子供を育てながら、中国語やロシア語の語学に興味を持ちます。そしてその後インドの霊的指導 、ヴィヴィーケーナンダの講演を読んだのを機にラーマクリシュナのことを知り、ヒンズー語、サンスクリット語を学び、ベンガル語で書かれたラーマクリシュナの教えの本を翻訳するに至ります。文才もありますが、語学センスもあるんですね。
その後その翻訳等をもとにこの本を書き、それを昭和49年に自費出版したのがこれです。
そしてその本は昭和55年に中公文庫から再版になり、今私が手にしている本は1991年の出版です。 この夏日本のアマゾンで古本で買いました。
ま、興味おありの人は少ないでしょうが、お勧めです。
ではこちらもよろしくお願いします
2018年6月15日金曜日
レスターのシルディ・サイババ寺院
先日レスター大学のオープンデーに行った時に、ついでにシルディ・サイババのお寺に行ってきました。シルディ・サイババとは、19世紀の終わりから20世紀にかけてインドにいた聖人です。ヒンズー教徒ともイスラム教徒ともいわれ、未だにどちらの信者からも篤く篤く愛され敬われています。
アフロヘアでオレンジ色の袈裟のサティア・サイババは日本でもよく知られていますが、そのサイババの前世と言われています。
去年の4月にロンドンにルイの大学のオファーホルダーオープンデーに行った時に、ウエンブリーで初めて行きました。その時は初めてで、どう振舞っていいかわかりませんでしたが、今回は ちょっと気楽に行けました。イギリスに3件、シルディ・サイババのお寺があり、そのうちの一件がここレスターです。っていうことは、インド人の人口多いんでしょうね。
シルディ・サイババのお寺では、なぜか食べ物や物をくれます。普通お寺や教会って、訪問する人が献金とはお賽銭とかあげるものですけどね。(ま、献金ボックスも置いてありまして、ちゃんと入れてきましたが。)
前回はお饅頭ときれいな布をもらいましたが、今回はイチゴをくれました。大事に大学まで持って帰って、チャーリーに一つ上げました。
そして額には灰でしるしをつけてくれます。チャーリーに「汚れがついてるみたい。」と言われましたが、そのまま一日過ごしました。
チャーリーがレスター大学行ったら、会いに来るたびにこのお寺に行けるな~。ま、これは親の勝手すぎる希望か。
ではこちらもよろしくお願いします
アフロヘアでオレンジ色の袈裟のサティア・サイババは日本でもよく知られていますが、そのサイババの前世と言われています。
去年の4月にロンドンにルイの大学のオファーホルダーオープンデーに行った時に、ウエンブリーで初めて行きました。その時は初めてで、どう振舞っていいかわかりませんでしたが、今回は ちょっと気楽に行けました。イギリスに3件、シルディ・サイババのお寺があり、そのうちの一件がここレスターです。っていうことは、インド人の人口多いんでしょうね。
シルディ・サイババのお寺では、なぜか食べ物や物をくれます。普通お寺や教会って、訪問する人が献金とはお賽銭とかあげるものですけどね。(ま、献金ボックスも置いてありまして、ちゃんと入れてきましたが。)
前回はお饅頭ときれいな布をもらいましたが、今回はイチゴをくれました。大事に大学まで持って帰って、チャーリーに一つ上げました。
そして額には灰でしるしをつけてくれます。チャーリーに「汚れがついてるみたい。」と言われましたが、そのまま一日過ごしました。
チャーリーがレスター大学行ったら、会いに来るたびにこのお寺に行けるな~。ま、これは親の勝手すぎる希望か。
ではこちらもよろしくお願いします
2018年5月17日木曜日
自分を愛することと、嫌な気持ちを受け入れること 2
これは若者に限らずだれでも当てはまることですが、我々に欠けてる能力って、嫌な気持ちをそのまま受け入れて、淡々と生活を続けること思うのです。
嫌な気持ちっていうのは、例えば怒りとかイライラとか不安とか焦りとか、そういう気持ち。
簡単で無害な例を挙げるなら、何か作業中に心配なことをふと思い当たるとします。一刻を争うことじゃないけど、大事なこと。例えばクレジットカードを失くしたんじゃないかとか、もしかして何かの締め切りが今日までだったんじゃないかとか。 そういう心配って、今やってることを中断してでも、すぐに確認しないと気が済まなかったりしませんか?
例えば誰かに何か失礼なこと言われたら、その腹が立つ気持ちをそのまま受け入れられないから、相手が家族などなら、売り言葉に買い言葉で反射的に言い返したりしませんか?もしも言えない相手なら、心の中で相手のことを悪く思ったり、あとで人に愚痴を言ったり。
たとえば恋人とか配偶者とかの言葉が気になったり、意味なく機嫌が悪かったしたら、いろいろ何度も何度もしつこく気が済むまで質問したりしたくなりませんか?
つまり何か、嫌な気持ちになることがあったら、それを受け入れてる代わりに、反射的にその気持ちをかき消すような可能性のある行動をとり、何とか気を済ませようをしてしまう。
何か漠然とした不安があったりストレスがたまると過食したり深酒をしたり、一人で家にいると何となく不安になるのでテレビをつけたり、人に電話したり。何かして気を紛らさせないといけない。
まあそのくらいなら別に害はないけど、これが極端になると、イライラするから暴力や反社会的な行為に出たり、仕事や人間関係で嫌なことがあるから子供や奥さんを殴ったり。これが自分に向けられたら、先日書いたように、セルフハームとか摂食障害とか、抗うつ剤や睡眠薬の濫用に走ったり。
嫌な気持ちが起こると、それをなんとしてでもかき消すような、紛らわすような、それを感じなくて済むような行為をせずにはいられない。それができないと、ひどい場合はパニック状態に陥ってしまったり。
いろいろな個人的な問題とか人間関係の問題とか、そして社会問題も、その辺から来ていることが多々ある気がします。そこまで大きい話にしなくても、腹が立った勢いでとる行動がろくなことにならないことは、だれでも知ってるはず。
じゃあ、それをやめるにはどうしたらいいか。嫌な気持ちが起こっても、それを受け入れて自然にその気持ちが消え去るのを待てるようにするにはどうしたらいいか。
マインドフルネスはそれにすごく有効(なはず)だし、気持ちを切り替えていいことに目を向けるとか(エイブラハムの引き寄せの法則)、先日書いたルイーズ・ヘイの 本に出てくるようなアファメーションも効きます。他にはセドナ・メソッドとか、きっとほかにも私が知らない方法があると思うんだけど。
要するに、なにか自分に一番いいやり方を見つけて、自分の気持ち、自分の嫌な気持ちをコントロールできる方法を見つけなければ、いつまでたっても自分の周りに起こる出来事に心の平安をかき乱され、それだけでなく、それに反射的な(おそらくろくでもない)行動をとり続けて、そのままあ人生行ってしまうことになります。
世間を見渡してみると、そうやって自分の心をコントロール出来てる人は少ないどころか、コントロールしようとしてる人すら少ない気がします。
そういう私だって全然偉そうなことは言えないんだけどね。修行に励みます。
ではこちらのクリックもよろしくお願いしますね

イギリスランキング
嫌な気持ちっていうのは、例えば怒りとかイライラとか不安とか焦りとか、そういう気持ち。
簡単で無害な例を挙げるなら、何か作業中に心配なことをふと思い当たるとします。一刻を争うことじゃないけど、大事なこと。例えばクレジットカードを失くしたんじゃないかとか、もしかして何かの締め切りが今日までだったんじゃないかとか。 そういう心配って、今やってることを中断してでも、すぐに確認しないと気が済まなかったりしませんか?
例えば誰かに何か失礼なこと言われたら、その腹が立つ気持ちをそのまま受け入れられないから、相手が家族などなら、売り言葉に買い言葉で反射的に言い返したりしませんか?もしも言えない相手なら、心の中で相手のことを悪く思ったり、あとで人に愚痴を言ったり。
たとえば恋人とか配偶者とかの言葉が気になったり、意味なく機嫌が悪かったしたら、いろいろ何度も何度もしつこく気が済むまで質問したりしたくなりませんか?
つまり何か、嫌な気持ちになることがあったら、それを受け入れてる代わりに、反射的にその気持ちをかき消すような可能性のある行動をとり、何とか気を済ませようをしてしまう。
何か漠然とした不安があったりストレスがたまると過食したり深酒をしたり、一人で家にいると何となく不安になるのでテレビをつけたり、人に電話したり。何かして気を紛らさせないといけない。
まあそのくらいなら別に害はないけど、これが極端になると、イライラするから暴力や反社会的な行為に出たり、仕事や人間関係で嫌なことがあるから子供や奥さんを殴ったり。これが自分に向けられたら、先日書いたように、セルフハームとか摂食障害とか、抗うつ剤や睡眠薬の濫用に走ったり。
嫌な気持ちが起こると、それをなんとしてでもかき消すような、紛らわすような、それを感じなくて済むような行為をせずにはいられない。それができないと、ひどい場合はパニック状態に陥ってしまったり。
いろいろな個人的な問題とか人間関係の問題とか、そして社会問題も、その辺から来ていることが多々ある気がします。そこまで大きい話にしなくても、腹が立った勢いでとる行動がろくなことにならないことは、だれでも知ってるはず。
じゃあ、それをやめるにはどうしたらいいか。嫌な気持ちが起こっても、それを受け入れて自然にその気持ちが消え去るのを待てるようにするにはどうしたらいいか。
マインドフルネスはそれにすごく有効(なはず)だし、気持ちを切り替えていいことに目を向けるとか(エイブラハムの引き寄せの法則)、先日書いたルイーズ・ヘイの 本に出てくるようなアファメーションも効きます。他にはセドナ・メソッドとか、きっとほかにも私が知らない方法があると思うんだけど。
要するに、なにか自分に一番いいやり方を見つけて、自分の気持ち、自分の嫌な気持ちをコントロールできる方法を見つけなければ、いつまでたっても自分の周りに起こる出来事に心の平安をかき乱され、それだけでなく、それに反射的な(おそらくろくでもない)行動をとり続けて、そのままあ人生行ってしまうことになります。
世間を見渡してみると、そうやって自分の心をコントロール出来てる人は少ないどころか、コントロールしようとしてる人すら少ない気がします。
そういう私だって全然偉そうなことは言えないんだけどね。修行に励みます。
ではこちらのクリックもよろしくお願いしますね

イギリスランキング
2018年5月14日月曜日
自分を愛することと、嫌な気持ちを受け入れること 1
最近は若者、特に中学生高校生のメンタルヘルスの問題に、ニュースでも身近にでもよく接します。
それに関して私が思うこと、そして若い人たちに知ってほしいこと、それは「自分を愛すること」が何よりも大切だということです。
私がこの考えに初めて接したのは、今まで何度もここで書いたけど、ルイーズ・ヘイ(Louise Hay)という著者のYou Can Heal Your Lifeという本でした。初めて読んだのは今から30年くらい前になるんだけど、その時ですら「これはこの手の本の中では一番影響力のある本よ。」と友達に勧められて読みました。
その時は、さらっと読んでなるほどという感じでしたが、その数年後に読み返して、頭をガツンとやられたというか、心にズーンと響いたというか。とにかくそれ以来何度も何度も読み返しましたし、これからも読み返す本だと思います。
この本は最初は「体の病気には心の原因がある。」というテーマで一番注目されたのですが、(例えば腰痛はお金の心配とか)、私は(そして著者本人も)それよりも、この本全体を貫く一番大きいテーマ、「自分を愛することが何よりも大切であり、人生のいろんな問題は、自分を愛せないことに起因する。」という部分が一番感銘を受けた部分でした。
特に若い人に知ってほしいのは、「自分を愛せないから、他人にどう思われているかが気になるんだよ。」ということです。
他人にどう思われたっていいじゃない。そういうのは簡単だけど、自分を愛せない、だから自分に自信のない人は、他人にどう思われるかがすごく重要なことになってしまう。そして何より怖いことは、いくら他人によく思われても、いくら他人に愛されても、「でも私の本当の姿を知れば、私のことなど愛せるはずがない。」と思っていること。
若者のセルフハーム、うつ病、摂食障害、自殺未遂。そこまでいかないまでも、反社会的な行為とか、過度の飲酒、ドラッグ…その他いろいろな精神の問題や、心がすさんで自暴自棄になることで、犯罪や中毒に染まっていくこと。そんな問題の底には、自己愛の欠如があるはずです。
自分を愛しているならば、薬やお酒に溺れない。犯罪に流れていかない。悪い仲間に流されない。リストカットや、拒食症になったりしない。もしもそういう方向に流れて行っても、きっとどこかで、「私の人生はこんなはずではない。」と戻ってくる力を持っていると思うのです。
子供のころから親に大切に愛させて育ち、自然に自分を大切に感じ、自分を愛せる人たちはラッキーです。でもそうでない人たちもたくさんいる、というか、きっとそういう人たちが大半なので、今こんなにいろいろ問題が出てきているんじゃないかな。
この本は、そういう大半の人たちが、少しずつ過去の呪縛から逃れ、少しずつ自分を愛することを学ぶためのレッスンや手段が、本当に丁寧に、愛をこめて書かれています。
本当に、著者ルイーズの愛が行間から感じられるような本です。
若い人みんなに読んでほしいけど、大人から押し付けられた本ほど嫌なものはないので、そのうち自分で発見してくれたらいいんですけどね。
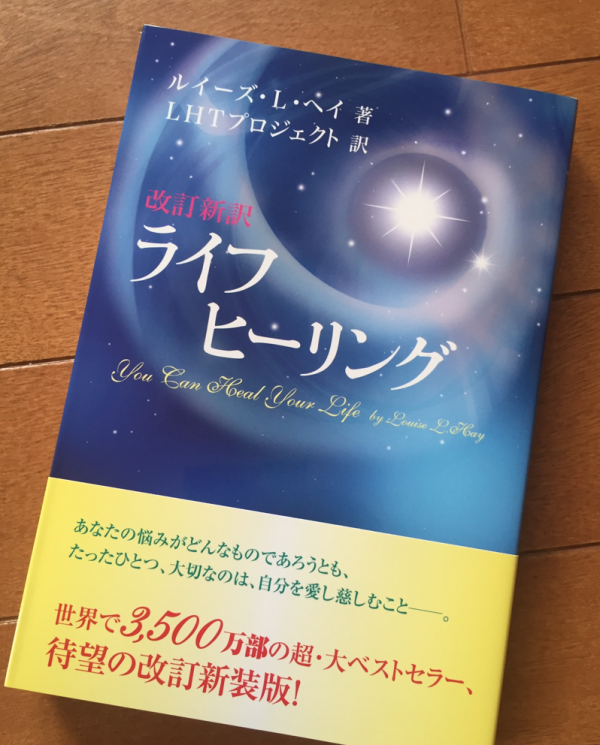
他にももうちょっと書きたいことがあるんだけど、それはまだ後日。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
それに関して私が思うこと、そして若い人たちに知ってほしいこと、それは「自分を愛すること」が何よりも大切だということです。
私がこの考えに初めて接したのは、今まで何度もここで書いたけど、ルイーズ・ヘイ(Louise Hay)という著者のYou Can Heal Your Lifeという本でした。初めて読んだのは今から30年くらい前になるんだけど、その時ですら「これはこの手の本の中では一番影響力のある本よ。」と友達に勧められて読みました。
その時は、さらっと読んでなるほどという感じでしたが、その数年後に読み返して、頭をガツンとやられたというか、心にズーンと響いたというか。とにかくそれ以来何度も何度も読み返しましたし、これからも読み返す本だと思います。
この本は最初は「体の病気には心の原因がある。」というテーマで一番注目されたのですが、(例えば腰痛はお金の心配とか)、私は(そして著者本人も)それよりも、この本全体を貫く一番大きいテーマ、「自分を愛することが何よりも大切であり、人生のいろんな問題は、自分を愛せないことに起因する。」という部分が一番感銘を受けた部分でした。
特に若い人に知ってほしいのは、「自分を愛せないから、他人にどう思われているかが気になるんだよ。」ということです。
他人にどう思われたっていいじゃない。そういうのは簡単だけど、自分を愛せない、だから自分に自信のない人は、他人にどう思われるかがすごく重要なことになってしまう。そして何より怖いことは、いくら他人によく思われても、いくら他人に愛されても、「でも私の本当の姿を知れば、私のことなど愛せるはずがない。」と思っていること。
若者のセルフハーム、うつ病、摂食障害、自殺未遂。そこまでいかないまでも、反社会的な行為とか、過度の飲酒、ドラッグ…その他いろいろな精神の問題や、心がすさんで自暴自棄になることで、犯罪や中毒に染まっていくこと。そんな問題の底には、自己愛の欠如があるはずです。
自分を愛しているならば、薬やお酒に溺れない。犯罪に流れていかない。悪い仲間に流されない。リストカットや、拒食症になったりしない。もしもそういう方向に流れて行っても、きっとどこかで、「私の人生はこんなはずではない。」と戻ってくる力を持っていると思うのです。
子供のころから親に大切に愛させて育ち、自然に自分を大切に感じ、自分を愛せる人たちはラッキーです。でもそうでない人たちもたくさんいる、というか、きっとそういう人たちが大半なので、今こんなにいろいろ問題が出てきているんじゃないかな。
この本は、そういう大半の人たちが、少しずつ過去の呪縛から逃れ、少しずつ自分を愛することを学ぶためのレッスンや手段が、本当に丁寧に、愛をこめて書かれています。
本当に、著者ルイーズの愛が行間から感じられるような本です。
若い人みんなに読んでほしいけど、大人から押し付けられた本ほど嫌なものはないので、そのうち自分で発見してくれたらいいんですけどね。
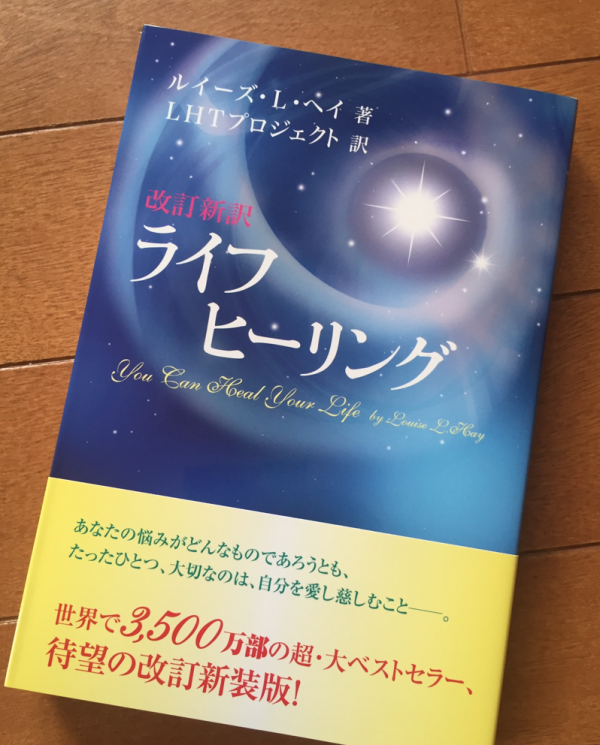
他にももうちょっと書きたいことがあるんだけど、それはまだ後日。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
2018年5月13日日曜日
仏の漢字
最近はスピリチュアル関係の本を読むことが多くなり、ブッダもよく登場します。
英語ではBuddha。だから私の最近のボキャブラリーでは仏様というよりはブッダなんですが、そういえば日本語の仏陀も全く同じ発音だなあと何となく考えていました。
そうしてよく考えてみれば、この仏という漢字、仏陀と仏という以外に読み方とか意味とかあるのかなあと気になりました。それで今、小学生の時以来の漢和辞典(オンライン)を使って調べてみましたが、やっぱり思った通り、この漢字は「仏」以外の意味はありません。(フランスっていうのもご愛敬ででてましたが。)
じゃあ、この日本語の漢字の「仏」は、サンスクリット語から来ているBuddhaと丸々100パーセント同じ意味で同じ音なんですね。
遥か紀元前からのインドの言葉が、今の日本語の普通の漢字や言葉として、全くそのままなのにちょっと驚いてちょっと感動しました。
そういえば、ちょっと前、日本語で書かれたインド哲学史の本を読みましたが、サンスクリットの言葉やコンセプトがいろいろ日本語(漢字)で書かれていたのに驚きました。しかも私ですらいろいろ聞いたことのある言葉。大半は忘れましたが、例えば涅槃。これは有名かもしれませんがNirvanaです。
そしてこれは日本のお寺で知ったのですが、真言密教に阿字観という修行があるそうで、この「阿」はサンスクリットのオウムと同じであるとも言われています。
オウムはこちら。

何となく字の形が似てなくもないかな。
ちなみに仏陀は日本では仏様、神様に近いような感じに思われていますが、ブッダとは「目覚めたもの」という敬称で、この言葉が指す本人のゴータマ・シッダールタは実は元王子様の、普通の人間で、結婚して息子もいました。
この普通の人間であったというところが、私は何となく感動します。
で
イギリスランキングはこちらもよろしくお願いします
英語ではBuddha。だから私の最近のボキャブラリーでは仏様というよりはブッダなんですが、そういえば日本語の仏陀も全く同じ発音だなあと何となく考えていました。
そうしてよく考えてみれば、この仏という漢字、仏陀と仏という以外に読み方とか意味とかあるのかなあと気になりました。それで今、小学生の時以来の漢和辞典(オンライン)を使って調べてみましたが、やっぱり思った通り、この漢字は「仏」以外の意味はありません。(フランスっていうのもご愛敬ででてましたが。)
じゃあ、この日本語の漢字の「仏」は、サンスクリット語から来ているBuddhaと丸々100パーセント同じ意味で同じ音なんですね。
遥か紀元前からのインドの言葉が、今の日本語の普通の漢字や言葉として、全くそのままなのにちょっと驚いてちょっと感動しました。
そういえば、ちょっと前、日本語で書かれたインド哲学史の本を読みましたが、サンスクリットの言葉やコンセプトがいろいろ日本語(漢字)で書かれていたのに驚きました。しかも私ですらいろいろ聞いたことのある言葉。大半は忘れましたが、例えば涅槃。これは有名かもしれませんがNirvanaです。
そしてこれは日本のお寺で知ったのですが、真言密教に阿字観という修行があるそうで、この「阿」はサンスクリットのオウムと同じであるとも言われています。
オウムはこちら。

何となく字の形が似てなくもないかな。
ちなみに仏陀は日本では仏様、神様に近いような感じに思われていますが、ブッダとは「目覚めたもの」という敬称で、この言葉が指す本人のゴータマ・シッダールタは実は元王子様の、普通の人間で、結婚して息子もいました。
この普通の人間であったというところが、私は何となく感動します。
で

イギリスランキングはこちらもよろしくお願いします
2018年4月26日木曜日
「色が見える」生徒さんの話
昨日ヨガのレッスンの後で、昔私のクラスに来ていて(らしい。私は覚えていない)、最近また来るようになった人が「実は」と話に来ました。
レッスンの最後のほうのメディテーションの最中に、目を閉じると「色」が見えると、泣きながら話してくれました。
こういう人、ごくごくたまにいるのですが、メディテーションに限らす、目を閉じてリラックスしたらいろんな色が見えたり、人を見るとその人のオーラの色が見えたりするとのことです。今まで色の話をしてくれた人は3人いました。「色が見える」といわれても(I can see colours)、色が見えない私には、どういうものがあんまりよくわからないんですが、やっぱりなにかあるみたいですね。
その人は本当にごくごく普通の中産階級のおばさん(60代前半くらい)で、ヨガも友達と一緒に半分おつきあい半分健康のためにやり始めたという感じの人です。
どうして泣いていたのか、多分自分でもどうしてそうなるのかわからなくて怖いのかもしれません。目を開けたら色は見えなくなるんだけど、メディテーションをすると深くリラックスして、目を開けるのが難しいとのこと。これも、「どう説明していいかわからないんだけど。」とのことでした。 それから、色が見えると「感情があふれてくる。」とのこと。
そういうスピリチュアルなことにすごく興味があるのに、そういう能力の全然ない私にとっては、うらやましいくらいなのですが、その人はそういう事には全然興味ないのにこんなことになって、戸惑って怖がっているようです。
上にそういう人はこの人を入れて3人会ったことがあると書きましたが、その後その一人は霊媒師に、別の人はキリスト教会の牧師になりました。(しかもそういった話をしてくれたあと割と短期間に急に。)この人もなにか、そういう方向に行くのかもしれません。
これとは別に、長年ヨガに来てくれているある60代の、ごくごく普通のおばさんは、ヨガの最中に幽体離脱をしたことがあると言っていました。(この人も怖がってました。)この人はいまだに普通のおばさんです。
私自身は全然霊感とかないんだけど、こういう話を聞くと、やっぱりそういう世界は実在するんだなあと改めて思いますね。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
レッスンの最後のほうのメディテーションの最中に、目を閉じると「色」が見えると、泣きながら話してくれました。
こういう人、ごくごくたまにいるのですが、メディテーションに限らす、目を閉じてリラックスしたらいろんな色が見えたり、人を見るとその人のオーラの色が見えたりするとのことです。今まで色の話をしてくれた人は3人いました。「色が見える」といわれても(I can see colours)、色が見えない私には、どういうものがあんまりよくわからないんですが、やっぱりなにかあるみたいですね。
その人は本当にごくごく普通の中産階級のおばさん(60代前半くらい)で、ヨガも友達と一緒に半分おつきあい半分健康のためにやり始めたという感じの人です。
どうして泣いていたのか、多分自分でもどうしてそうなるのかわからなくて怖いのかもしれません。目を開けたら色は見えなくなるんだけど、メディテーションをすると深くリラックスして、目を開けるのが難しいとのこと。これも、「どう説明していいかわからないんだけど。」とのことでした。 それから、色が見えると「感情があふれてくる。」とのこと。
そういうスピリチュアルなことにすごく興味があるのに、そういう能力の全然ない私にとっては、うらやましいくらいなのですが、その人はそういう事には全然興味ないのにこんなことになって、戸惑って怖がっているようです。
上にそういう人はこの人を入れて3人会ったことがあると書きましたが、その後その一人は霊媒師に、別の人はキリスト教会の牧師になりました。(しかもそういった話をしてくれたあと割と短期間に急に。)この人もなにか、そういう方向に行くのかもしれません。
これとは別に、長年ヨガに来てくれているある60代の、ごくごく普通のおばさんは、ヨガの最中に幽体離脱をしたことがあると言っていました。(この人も怖がってました。)この人はいまだに普通のおばさんです。
私自身は全然霊感とかないんだけど、こういう話を聞くと、やっぱりそういう世界は実在するんだなあと改めて思いますね。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
2018年4月21日土曜日
Life is Suffering
イギリスにも結構仏教徒っているんですよ。比率的にはアメリカのほうが断然多いんだけど、多分アメリカは中国系とか日系の米国人が仏教徒なんだと思います。イギリスでは、白人でもたまに仏教徒がいます。周りを見てる限りは増えてきているようです。子供たちが行った小学校は、イギリス国教会の小さな田舎の学校だったのですが、5人くらいいる先生のうち、実は二人が仏教徒でした。(しかもその一人は、のちに仏教のメディテーションの先生になりました。)
日本人は一応仏教徒と言われていますが、教義を知ってる人って少ないと思うんですが、イギリスの白人の仏教徒は、なかなか勉強していますよ。私は、日本語の仏教の本は難しいので、英語で読んでいるくらいです。初心者向けに書かれてますからね。
これも英語で書かれた仏教の本の話なんですが、仏陀の重要な教えの第一は、Life is suffering(人生は苦悩)といろんな本に書いてあります。私はここでまず躓きました。
Sufferingっていうのはなあ。そんなこと最初に断言してしまっては元も子もないし、実際、人生が苦悩とは思えないです。
そうしたら、最近読んだ本に、「一般には仏陀はLife is suffering と言ったと言われているが、実はSufferingというよりはuncertainである。」というのを読みました。これには深く納得しました。
Uncertain.不確定。先のことはわからない。一瞬先は闇・・かもしれない。
これは本当にそうだと思うんです。今日は元気でも、明日は心臓発作になるかもしれないし、もしかしたら知らないだけで癌にかかってるかもしれない。ピカピカの車を駐車して、戻ると凹んでるかもしれない。急に仕事を失うかもしれないし、株が暴落するかもしれない。理想の恋人に捨てられるかもしれない。でも一方で、その逆に、宝くじに当たるかもしれないし、運良い出会いがあるかもしれない。
そこで平常心を保つこと。これにはすごく納得が行きました。
(昔の教えがサンスクリットとかヘブライ語とかラテン語とか、そこから何度も翻訳されただろうし、同じ言葉でも時代が変われば意味が変わるし、意味が微妙に変わるってことはよくあることなのでしょう。)
この不確定さ。これが現代人が精神を病む理由の一つに思えます。
昔は何だって不確定だったし、将来のことも明日のこともぜんぜんわからないのが普通だった。でも今は社会がオーガナイズされて、しかもインターネットのおかげでそれがさらに進んだから、日常生活では何もかもが予定通りスムーズに進むことを当然のことと思っている。電車は2分と遅れないし、ネットで何週間も前に予定したことがきちんと行われるし、人でも物でも、来るか来ないかわからず待つってこともなくなった。
だから何となく、人生ってそんな風にスムーズに予定通りいくような気がするけど、実は全然そんなことはなくって、予定や計画が変わる要素は人生にはいっぱいあるんだけど、そのことを忘れて生きてるみたい。
その上、そんな風に何事もきっちりと進むことが前提の社会になったから、社会や生活がきつきつになって、余裕やら空間や無駄がなくなりすぎて、それが息苦しい。
人生は苦悩ではないけど、不確定。その不確定さを不安に感じることなく、淡々と来る日来る日を一日ずつ生きていく。そういうのを目指してます。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
日本人は一応仏教徒と言われていますが、教義を知ってる人って少ないと思うんですが、イギリスの白人の仏教徒は、なかなか勉強していますよ。私は、日本語の仏教の本は難しいので、英語で読んでいるくらいです。初心者向けに書かれてますからね。
これも英語で書かれた仏教の本の話なんですが、仏陀の重要な教えの第一は、Life is suffering(人生は苦悩)といろんな本に書いてあります。私はここでまず躓きました。
Sufferingっていうのはなあ。そんなこと最初に断言してしまっては元も子もないし、実際、人生が苦悩とは思えないです。
そうしたら、最近読んだ本に、「一般には仏陀はLife is suffering と言ったと言われているが、実はSufferingというよりはuncertainである。」というのを読みました。これには深く納得しました。
Uncertain.不確定。先のことはわからない。一瞬先は闇・・かもしれない。
これは本当にそうだと思うんです。今日は元気でも、明日は心臓発作になるかもしれないし、もしかしたら知らないだけで癌にかかってるかもしれない。ピカピカの車を駐車して、戻ると凹んでるかもしれない。急に仕事を失うかもしれないし、株が暴落するかもしれない。理想の恋人に捨てられるかもしれない。でも一方で、その逆に、宝くじに当たるかもしれないし、運良い出会いがあるかもしれない。
そこで平常心を保つこと。これにはすごく納得が行きました。
(昔の教えがサンスクリットとかヘブライ語とかラテン語とか、そこから何度も翻訳されただろうし、同じ言葉でも時代が変われば意味が変わるし、意味が微妙に変わるってことはよくあることなのでしょう。)
この不確定さ。これが現代人が精神を病む理由の一つに思えます。
昔は何だって不確定だったし、将来のことも明日のこともぜんぜんわからないのが普通だった。でも今は社会がオーガナイズされて、しかもインターネットのおかげでそれがさらに進んだから、日常生活では何もかもが予定通りスムーズに進むことを当然のことと思っている。電車は2分と遅れないし、ネットで何週間も前に予定したことがきちんと行われるし、人でも物でも、来るか来ないかわからず待つってこともなくなった。
だから何となく、人生ってそんな風にスムーズに予定通りいくような気がするけど、実は全然そんなことはなくって、予定や計画が変わる要素は人生にはいっぱいあるんだけど、そのことを忘れて生きてるみたい。
その上、そんな風に何事もきっちりと進むことが前提の社会になったから、社会や生活がきつきつになって、余裕やら空間や無駄がなくなりすぎて、それが息苦しい。
人生は苦悩ではないけど、不確定。その不確定さを不安に感じることなく、淡々と来る日来る日を一日ずつ生きていく。そういうのを目指してます。
ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング
2018年4月15日日曜日
Black Elk Speaks 読書感想
素晴らしい本を読みました。
読んだきっかけは、2か月ほど前ここに書いた、「20世紀に出版されたスピリチュアルな本100冊」のリストからです。残りの人生せいぜい1000冊も読めないんだから、とりあえずこの100冊から読破していこうと思ったのがきっかけでした。
この本はタイトルがBなのでリストの上のほうにあり、しかもデボンの図書館の蔵書リストにあったので、図書館で予約しました。本が来て取りに行くと、30年前くらいの本でした。借りた人は少ないのか、古い けれどなかなかいいコンディションで、いい雰囲気でした。しかも字のフォントが古いタイプライターみたいな字で、それもよかったです。
これはアメリカの詩人がネイティブインディアンのメディシン・マン、ブラック・エルクを インタビューし、本に仕上げたものです。ブラックエルクの語り口が、詩的に美しくまとめられています。
この本は1930年代に出版され、数年で廃版になったのち、1960年代にカール・ユングがドイツで 読んで絶賛し、その後また再出版になり、今でもアマゾンで買えます。日本語の翻訳もアマゾンの古本で買えるようです。
ブラック・エルクは子供のころに 先祖のスピリットから、インディアンたちの運命を救うヴィジョンを受けます。成長し、その能力を生かしメディシンマンとして多くの人たちの命を救いますが、結局は時代に逆らえず、何年にもわたる戦いの末、白人の攻撃についに降参し、インディアンの霊的アイデンティディーを失っていきます。
その悲しい、歴史上の話が、神秘的に詩的に、かつ淡々と語られます。
すごくすごく悲しい本です。
今まで読んだ一番好きな本の一冊に入る本です。
ではこちらもよろしくお願いします。

イギリスランキング
読んだきっかけは、2か月ほど前ここに書いた、「20世紀に出版されたスピリチュアルな本100冊」のリストからです。残りの人生せいぜい1000冊も読めないんだから、とりあえずこの100冊から読破していこうと思ったのがきっかけでした。
この本はタイトルがBなのでリストの上のほうにあり、しかもデボンの図書館の蔵書リストにあったので、図書館で予約しました。本が来て取りに行くと、30年前くらいの本でした。借りた人は少ないのか、古い けれどなかなかいいコンディションで、いい雰囲気でした。しかも字のフォントが古いタイプライターみたいな字で、それもよかったです。
これはアメリカの詩人がネイティブインディアンのメディシン・マン、ブラック・エルクを インタビューし、本に仕上げたものです。ブラックエルクの語り口が、詩的に美しくまとめられています。
この本は1930年代に出版され、数年で廃版になったのち、1960年代にカール・ユングがドイツで 読んで絶賛し、その後また再出版になり、今でもアマゾンで買えます。日本語の翻訳もアマゾンの古本で買えるようです。
ブラック・エルクは子供のころに 先祖のスピリットから、インディアンたちの運命を救うヴィジョンを受けます。成長し、その能力を生かしメディシンマンとして多くの人たちの命を救いますが、結局は時代に逆らえず、何年にもわたる戦いの末、白人の攻撃についに降参し、インディアンの霊的アイデンティディーを失っていきます。
その悲しい、歴史上の話が、神秘的に詩的に、かつ淡々と語られます。
すごくすごく悲しい本です。
今まで読んだ一番好きな本の一冊に入る本です。
ではこちらもよろしくお願いします。

イギリスランキング
2018年2月20日火曜日
脳内独り言
先日ロンドンにバスで行ったときに、バスの中で聞くようにいろいろオーディオ・ブックやインタビューをダウンロードして行ったのですが、その中のひとつが、エクハート・トールのインタビューでした。
エクハート・トール(ト-レと発音する人もいます)は日本ではまだあまり知られていないようなんですが、欧米では近年では多分一番 注目・尊敬されているスピリチュアル関係の著者です。
いくつか書いたので、この辺読んでみてください。
インタビューでこんなことを言ってました。
まだ悟りを開く前のこと。毎日地下鉄に乗って大学に通っていました。その時毎朝一緒になる女性が、いつも独り言、というか、仮想の誰かに向ってずっと話しかけているのです。それも、怒ったり愚痴を言ったり文句を言ったりです。
それで、こんなひとでも毎日同じ電車に乗ってるってことは、なにか仕事についているんだなあと感心してました。
そしてある日、そうやって大学についてトイレの鏡に向っているときに、はっとこんなことを思いつきました。
彼女のように口に出してこそ言っていないけど、同じような文句とか心配とか自分も頭の中でまったく同じようにしてる。唯一の違いは、それが音声になってるかどうかだけ。
「将来自分もあの人のようにならないといいが。」そう思ったときに、周りの反応から、それを口に出して言ってしまったことを知りました。
まあこの最後の部分は落ちなんですけどね。
でも本当に私もそうなんです。マインドフルとかヨガとか言ってますが、頭の中でずっと独り言言ってますよ。心配事だったり、ちょっとイラッとしたことだったり、なんとなく不安に感じてることだったり、これからの予定を決めかねているとか、今日これからすることのシナリオを考えたり。
まったくぜんぜんマインドフルではないです。
今日も掃除をしているときと泳いでるときに、AさんにどうやってXXXのことを伝えようかとか、今週のXXXの催しに行きたくないなとか、次に何の本を読もうかとか、いろいろ頭の中で独り言言ってるのに気づいて、いけないいけないとマインドフルに集中しました。
自分で自分の思考の中身の無益さに気づく。これって第一歩ですね。明日も心して生きます。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
エクハート・トール(ト-レと発音する人もいます)は日本ではまだあまり知られていないようなんですが、欧米では近年では多分一番 注目・尊敬されているスピリチュアル関係の著者です。
いくつか書いたので、この辺読んでみてください。
インタビューでこんなことを言ってました。
まだ悟りを開く前のこと。毎日地下鉄に乗って大学に通っていました。その時毎朝一緒になる女性が、いつも独り言、というか、仮想の誰かに向ってずっと話しかけているのです。それも、怒ったり愚痴を言ったり文句を言ったりです。
それで、こんなひとでも毎日同じ電車に乗ってるってことは、なにか仕事についているんだなあと感心してました。
そしてある日、そうやって大学についてトイレの鏡に向っているときに、はっとこんなことを思いつきました。
彼女のように口に出してこそ言っていないけど、同じような文句とか心配とか自分も頭の中でまったく同じようにしてる。唯一の違いは、それが音声になってるかどうかだけ。
「将来自分もあの人のようにならないといいが。」そう思ったときに、周りの反応から、それを口に出して言ってしまったことを知りました。
まあこの最後の部分は落ちなんですけどね。
でも本当に私もそうなんです。マインドフルとかヨガとか言ってますが、頭の中でずっと独り言言ってますよ。心配事だったり、ちょっとイラッとしたことだったり、なんとなく不安に感じてることだったり、これからの予定を決めかねているとか、今日これからすることのシナリオを考えたり。
まったくぜんぜんマインドフルではないです。
今日も掃除をしているときと泳いでるときに、AさんにどうやってXXXのことを伝えようかとか、今週のXXXの催しに行きたくないなとか、次に何の本を読もうかとか、いろいろ頭の中で独り言言ってるのに気づいて、いけないいけないとマインドフルに集中しました。
自分で自分の思考の中身の無益さに気づく。これって第一歩ですね。明日も心して生きます。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
2018年2月9日金曜日
本屋の選んだスピリチュアルな100人
先日のスピリチュアル本100選に続く話題です。
ロンドンにWatkinsという、昔からあるスピリチュアル専門の本屋があります。その本屋が毎年スピリチュアル100人というリストを作り、今年も発表されました。
このリストの特徴は現在生存している人物であること。なのでサイババとかネルソンマンデラとか、なくなった人は近年のリストには載っていません。ルイーズ・ヘイもはずされてました。😢😢😢
今年のリストはこちらです。
それと本屋のリストなので、政治的もしくは宗教的リーダーというよりは、著者が多いです。
今年のリスト、さっと見てみると、上位10人くらいは割りと知られてるかな。
ローマ法王、ダライラマ、デズモンド・ツツ、エクハート・トール、オプラ・ウィンフリー、ボブ・ディラン、アリアナ・ハフィントン。ボブディランってしかし、ファンですが、スピリチュアルかな。このアリアナ・ハフィントンって、ハフポストの人?
10位以下で知られてそうな人は、ディーパック・チョプラ、エスター・ヒックス(エイブラハムの人)、ティク・ナット・ハン、マララ・ユスフザイ、アリス・ウォーカー(カラー・パープルの著者)、サドグル、リチャード・バック、ロンダ・バーン(The Secretのビデオ作った人)、ブライアン・ワイス、などなど。
そして毎年なぜか、池田大作氏が毎年ランキングしてます。日本ではなんとなく胡散臭いおっさんというイメージですけど、それはもしかしたらマスコミがつくったイメージなのかもしれません。チラッと日本語のウィキと英語のWikiを見比べたら、別の人物について書いたのかと思うくらい違いました。(日本のはスキャンダルが中心で、教義や平和貢献などについてはぜんぜんかかれてませんでした。)
この100人の中で、その人の書いた本やその人についての本を読んだ人は23人でした。残り77人、全員を読むつもりはないけど、名前をよく聞く著者の本10冊くらい、特に興味あるインドの聖人の本はリストに載せようと思います。
リチャード・バックはいわずと知れたかもめのジョナサンの著者。すごく昔、中学生のころに読みました。昨日も今日もリストに上がってるってことは、読めってことでしょうね。近いうちに読もうと思います。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
ロンドンにWatkinsという、昔からあるスピリチュアル専門の本屋があります。その本屋が毎年スピリチュアル100人というリストを作り、今年も発表されました。
このリストの特徴は現在生存している人物であること。なのでサイババとかネルソンマンデラとか、なくなった人は近年のリストには載っていません。ルイーズ・ヘイもはずされてました。😢😢😢
今年のリストはこちらです。
それと本屋のリストなので、政治的もしくは宗教的リーダーというよりは、著者が多いです。
今年のリスト、さっと見てみると、上位10人くらいは割りと知られてるかな。
ローマ法王、ダライラマ、デズモンド・ツツ、エクハート・トール、オプラ・ウィンフリー、ボブ・ディラン、アリアナ・ハフィントン。ボブディランってしかし、ファンですが、スピリチュアルかな。このアリアナ・ハフィントンって、ハフポストの人?
10位以下で知られてそうな人は、ディーパック・チョプラ、エスター・ヒックス(エイブラハムの人)、ティク・ナット・ハン、マララ・ユスフザイ、アリス・ウォーカー(カラー・パープルの著者)、サドグル、リチャード・バック、ロンダ・バーン(The Secretのビデオ作った人)、ブライアン・ワイス、などなど。
そして毎年なぜか、池田大作氏が毎年ランキングしてます。日本ではなんとなく胡散臭いおっさんというイメージですけど、それはもしかしたらマスコミがつくったイメージなのかもしれません。チラッと日本語のウィキと英語のWikiを見比べたら、別の人物について書いたのかと思うくらい違いました。(日本のはスキャンダルが中心で、教義や平和貢献などについてはぜんぜんかかれてませんでした。)
この100人の中で、その人の書いた本やその人についての本を読んだ人は23人でした。残り77人、全員を読むつもりはないけど、名前をよく聞く著者の本10冊くらい、特に興味あるインドの聖人の本はリストに載せようと思います。
リチャード・バックはいわずと知れたかもめのジョナサンの著者。すごく昔、中学生のころに読みました。昨日も今日もリストに上がってるってことは、読めってことでしょうね。近いうちに読もうと思います。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
2018年2月7日水曜日
20世紀スピリチュアル本100選
先日の本の話の続きです。
死ぬまでに読む本のリストを作る件ですが、とりあえずこんなリストを参考にしてみようと思います。
アメリカの出版社、ハーパーコリンズ社が1999年に出した、20世紀スピリチュアル本100選です。20世紀に初版が出版された本を対象にしたリストで、今でもネットでよく取り上げられていますから、こういったリストの中では一番権威があるようです。
日本語のサイトもありましたのでこちらをご覧ください。
英語のサイトはこちら
日本語に翻訳されてるのは半分くらいかな。
ざっと見てみると、知っている本は少ないです。誰でも知ってそうなのは遠藤周作(日本人ならですが)、指輪物語(The Lord of the Rings)、ヘッセ、TSエリオット、WBイエーツ、CSルイス、カミュ、ユング、マーティン・ルーサー・キング、マザーテレサ、ガンジー、カフカ、サマセット・モーム、リチャード・バック。こんなところかな。
この中で、読んで感銘を受けてもう取り合えず読み返す必要がない本が8冊、読んだことあるけどかなり昔のことで、読み返したほうがいいものが 5冊、映画で見たから許してというのが2冊。ということは、この中から90冊読むべきということですね。
しかし90冊も「死ぬまでに読む本」のリストに入れると、それで半分以上になりますから(150冊あげる予定)、この中でも厳選しないといけません。 中には詩集とかカトリック系の本とか、あんまり食指の進まない本もあるので、とりあえず興味あるもの中心にリストに入れてみます。
どれもヘビーっぽいので、読むの時間かかりそうだな。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
死ぬまでに読む本のリストを作る件ですが、とりあえずこんなリストを参考にしてみようと思います。
アメリカの出版社、ハーパーコリンズ社が1999年に出した、20世紀スピリチュアル本100選です。20世紀に初版が出版された本を対象にしたリストで、今でもネットでよく取り上げられていますから、こういったリストの中では一番権威があるようです。
日本語のサイトもありましたのでこちらをご覧ください。
英語のサイトはこちら
日本語に翻訳されてるのは半分くらいかな。
ざっと見てみると、知っている本は少ないです。誰でも知ってそうなのは遠藤周作(日本人ならですが)、指輪物語(The Lord of the Rings)、ヘッセ、TSエリオット、WBイエーツ、CSルイス、カミュ、ユング、マーティン・ルーサー・キング、マザーテレサ、ガンジー、カフカ、サマセット・モーム、リチャード・バック。こんなところかな。
この中で、読んで感銘を受けてもう取り合えず読み返す必要がない本が8冊、読んだことあるけどかなり昔のことで、読み返したほうがいいものが 5冊、映画で見たから許してというのが2冊。ということは、この中から90冊読むべきということですね。
しかし90冊も「死ぬまでに読む本」のリストに入れると、それで半分以上になりますから(150冊あげる予定)、この中でも厳選しないといけません。 中には詩集とかカトリック系の本とか、あんまり食指の進まない本もあるので、とりあえず興味あるもの中心にリストに入れてみます。
どれもヘビーっぽいので、読むの時間かかりそうだな。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
2018年1月27日土曜日
リグレッション(regression)体験
ワイス博士という米国人のセラピストの前世療法のテープ(っていうか、録音なんですが、最近の日本語ではなんと言うんでしょう?)をダウンロードしたので、今日の午後一人で30分ほど部屋にこもって聞いてみました。
まずリラクゼーションから入ります。頭、背中とだんだん足まで下がってきて、深くリラックスします。その後、子供の頃の記憶に戻ります。そしてその次は胎児のときの記憶、そして生まれてくるときの記憶。その後に前世の記憶をたどります。
子供の頃の記憶はそう難しくはないです。なかなか鮮明にはよみがえってきませんでしたが、小学生の頃の遊んだ記憶が浮かんできて、その頃の友達の名前などが出てきました。
胎児、出生の時の記憶。これはなんとなくビジョンは浮かびましたが、これが本当に自分の記憶かどうかはすごく怪しいです。テレビで見たものとか想像の可能性が高いですが、それはそれでいいそうです。
そして前世の記憶。
私はなんだかきれいなというか奇抜な衣装みたいなものを着てます。最近凝っているインドかなと思いましたが、鳥の羽とかがついているので、インカ人とか、なにか南米の衣装かなと思いました。
その後何人もの男性に囲まれて崖の上に連れて行かれ、崖から落ちて(落とされて?)死にます。痛いとか怖いとかいう感情は一切ないです。そしてその男性たちの顔を見ると、中に最近医療関係でお世話になっている人の顔がありました。 どうやらインカではなく、北米のアメリカインディアンの種族のようです。
この辺で意識がぼんやりしてきて、そのあとすぐにセッションは終わりになりました。
崖から突き落とされるっていうのはあまりにも強烈でありえないシーンのようですが、数々の前世の中で一番記憶に残っているものということなら、これを思い出しても不思議はないです。それにそれぞれの前世で何かの形で死を経験してるんだから、中にはバイオレントな物があっても当然かもしれません。
一年ほど前同じことをしたのですが、そのときは中世の冴えないヨーロッパの町の、議会の下級公僕みたいな前世でした。これはこれでその凡庸さが、リアリティーを持っていました。
こういうのが本当か嘘かは誰にもわからないことだし、この程度では何のセラピーにもならないんだけど、おもしろかったです。
ちなみにワイス博士というのは著名な著者なので、興味のある人は簡単に本は見つかりますよ。
ではこちらもよろしく

イギリスランキング
まずリラクゼーションから入ります。頭、背中とだんだん足まで下がってきて、深くリラックスします。その後、子供の頃の記憶に戻ります。そしてその次は胎児のときの記憶、そして生まれてくるときの記憶。その後に前世の記憶をたどります。
子供の頃の記憶はそう難しくはないです。なかなか鮮明にはよみがえってきませんでしたが、小学生の頃の遊んだ記憶が浮かんできて、その頃の友達の名前などが出てきました。
胎児、出生の時の記憶。これはなんとなくビジョンは浮かびましたが、これが本当に自分の記憶かどうかはすごく怪しいです。テレビで見たものとか想像の可能性が高いですが、それはそれでいいそうです。
そして前世の記憶。
私はなんだかきれいなというか奇抜な衣装みたいなものを着てます。最近凝っているインドかなと思いましたが、鳥の羽とかがついているので、インカ人とか、なにか南米の衣装かなと思いました。
その後何人もの男性に囲まれて崖の上に連れて行かれ、崖から落ちて(落とされて?)死にます。痛いとか怖いとかいう感情は一切ないです。そしてその男性たちの顔を見ると、中に最近医療関係でお世話になっている人の顔がありました。 どうやらインカではなく、北米のアメリカインディアンの種族のようです。
この辺で意識がぼんやりしてきて、そのあとすぐにセッションは終わりになりました。
崖から突き落とされるっていうのはあまりにも強烈でありえないシーンのようですが、数々の前世の中で一番記憶に残っているものということなら、これを思い出しても不思議はないです。それにそれぞれの前世で何かの形で死を経験してるんだから、中にはバイオレントな物があっても当然かもしれません。
一年ほど前同じことをしたのですが、そのときは中世の冴えないヨーロッパの町の、議会の下級公僕みたいな前世でした。これはこれでその凡庸さが、リアリティーを持っていました。
こういうのが本当か嘘かは誰にもわからないことだし、この程度では何のセラピーにもならないんだけど、おもしろかったです。
ちなみにワイス博士というのは著名な著者なので、興味のある人は簡単に本は見つかりますよ。
ではこちらもよろしく

イギリスランキング
2018年1月24日水曜日
マグカップ
メディテーションのリトリートで思ったことをちょっと書きます。
ダイニングルームにはいつでもお茶やコーヒーが入れられるような用意がしてあり、棚にはマグカップが50個以上置いてありました。そこから勝手にカップを取って、色々あるハーブティーや紅茶やコーヒーを作れるようになってます。
たくさんのマグカップは同じものがそろっているのではなく、いろんなサイズや色や柄のものがありました。それで最初の2日間ほどは、一番簡単に取れるものに手を伸ばして使ってました。
その時にふと思ったのです。子供たちが小さい頃、同じような機会があれば、絶対にわいわいいいながら好きな模様のマグカップを選んでたなって。時には取り合いの喧嘩までしてたことを思い出しました。マグカップなんてどんな模様でも味が違うわけでも無し、どうだっていいのに。あの頃の子供たちにとっては、カップを選ぶことさえ楽しい重要な事だったんですね。
そういうの、大人の人生からは消えちゃいましたね。どうでもいいようなことなんだけど、いちいちわいわい言って楽しむようなこと。別にわいわい言わなくてもいいんだけど、そんな風に、すべての機会にささやかな楽しみを見つけること。
こういうのって、マインドフルなんだと思います。
ほかの事考えながら、どれでもいいやって手近のカップに手を伸ばす。 ほかの事考えながら、適当にランチを食べる。ほかの事考えながら、いつもの決まった道路を運転する。こういうのはマインドフルの逆で、ぜんぜん今の瞬間を大切にしていない。
マインドフルとは、あらゆる瞬間が奇跡であることを知り、そのときそのときを生きること。カップひとつ選ぶにしてもきちんと選んで、おいしく味わってお茶を飲んで、丁寧にカップを洗うこと。
そうか、茶道が禅と言われるのは、こういうことなんだな。
それでリトリート後半は、いちいち吟味してカップを選んでました。やっぱりちょっとだけ楽しいですね。
こんな感じで生活 していくこと。難しいな。でもそれをしないことには、結局いつまでも同じ漠然とした不満と不安の人生から抜けられないように思います。
こつこつ丁寧に、ねじを巻くように生きていくしかありません。(村上春樹が欧米で禅と評価されるのもこのへんかも?)
ではこちらも よろしくね

イギリスランキング
ダイニングルームにはいつでもお茶やコーヒーが入れられるような用意がしてあり、棚にはマグカップが50個以上置いてありました。そこから勝手にカップを取って、色々あるハーブティーや紅茶やコーヒーを作れるようになってます。
たくさんのマグカップは同じものがそろっているのではなく、いろんなサイズや色や柄のものがありました。それで最初の2日間ほどは、一番簡単に取れるものに手を伸ばして使ってました。
その時にふと思ったのです。子供たちが小さい頃、同じような機会があれば、絶対にわいわいいいながら好きな模様のマグカップを選んでたなって。時には取り合いの喧嘩までしてたことを思い出しました。マグカップなんてどんな模様でも味が違うわけでも無し、どうだっていいのに。あの頃の子供たちにとっては、カップを選ぶことさえ楽しい重要な事だったんですね。
そういうの、大人の人生からは消えちゃいましたね。どうでもいいようなことなんだけど、いちいちわいわい言って楽しむようなこと。別にわいわい言わなくてもいいんだけど、そんな風に、すべての機会にささやかな楽しみを見つけること。
こういうのって、マインドフルなんだと思います。
ほかの事考えながら、どれでもいいやって手近のカップに手を伸ばす。 ほかの事考えながら、適当にランチを食べる。ほかの事考えながら、いつもの決まった道路を運転する。こういうのはマインドフルの逆で、ぜんぜん今の瞬間を大切にしていない。
マインドフルとは、あらゆる瞬間が奇跡であることを知り、そのときそのときを生きること。カップひとつ選ぶにしてもきちんと選んで、おいしく味わってお茶を飲んで、丁寧にカップを洗うこと。
そうか、茶道が禅と言われるのは、こういうことなんだな。
それでリトリート後半は、いちいち吟味してカップを選んでました。やっぱりちょっとだけ楽しいですね。
こんな感じで生活 していくこと。難しいな。でもそれをしないことには、結局いつまでも同じ漠然とした不満と不安の人生から抜けられないように思います。
こつこつ丁寧に、ねじを巻くように生きていくしかありません。(村上春樹が欧米で禅と評価されるのもこのへんかも?)
ではこちらも よろしくね

イギリスランキング
2018年1月22日月曜日
メディテーションから帰って来ました
メティデーションのリトリートから帰って来ました。
4日間のサイレント・リトリート。これが長くて長くて、家に帰るのが待ち遠しかったという人もいただろうし、実際にリタイアした人も数人いたようなのですが、私は帰りたくなかったです。ホリデーに行ったら帰りたくないのが普通ですが、それとはちょっと違う感じ。この4日間で得た心の平安、家に戻るとすぐに無くすんだろうなあと思うと、本当に悲しかった。
50人定員のリトリートだったのですが、満員でした。若い20代・30代の人も多かったのがちょっと驚きでした。
本格的なプログラムでした。初日は夕方から始まったのですが、2日目と3日目は、起床6.15分。
6.45 瞑想
7.30 朝食
8.15 労働(掃除や食器洗いなど、振り分けられたもの)
9.30 瞑想
10.15 歩行瞑想
11.00 瞑想
11.45 歩行瞑想
12.30 昼食
14.30 瞑想
15.15 歩行瞑想
16.00 瞑想
16.45 歩行瞑想
17.30 夕食
19.30 瞑想
20.00 講話
20.45 歩行瞑想
21.15 質疑応答
22.00 就寝
4日間で45分(夜の瞑想は30分)の瞑想が17回、歩行瞑想が12回ありました。瞑想は床に座らなくてもいいし、メティテーション・スツール(低い椅子のようなもの)を使ってもいいし、椅子でもよかったです。大半の人は床に座布団かスツールを使って座ってました。45分じっと座っているのは肉体的にも結構苦痛です。私は歩行瞑想の時間にちょこっとヨガをしてストレッチしましたが、そうでない人はどうしてたんでしょう?
45分の瞑想、これはきつかった人もいるだろうし、そうでない人もいたでしょうね。瞑想をする習慣のない人は大変だったんじゃないかと思います。
私は初日の午前中はなかなか集中できませんでしたが、2日目からは落ち着きました。
最終日、午後の最後のセッションの前、居間の椅子に座ってコーヒーを手にじっと外を見て15分ほど座ってました。
ただ何もせず、特に何も考えるでもなく、かといってうとうとしたりぼうっとしてるわけでもなく。このリトリートに来る前は、ただ静かに何もせず座るなんて出来なかったです。
こんな風に、ただじっと何もせず座っている時間。こんな時間は現実に戻るともうやってこないだろうなと思うと、悲しかったです。 たとえ家で一人の自由時間があっても、何もせずに過ごせるなんて贅沢な時間はないです。家事や仕事でないとしても、「本を読まねば」などと思ってしまいます。
ひとつ実際的なこととして実感したことは、デジタルワールドは疲れるということ。家に帰るのがいやなことのひとつは、メールボックスを開けることでした。きっと私はネットの世界で時間を使いすぎなんでしょう。ネットからの情報は必要だし、実際にこのリトリートだってネットで検索したわけなんですが、それでもネットの世界との関わり方を吟味しないとなあと感じました。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
4日間のサイレント・リトリート。これが長くて長くて、家に帰るのが待ち遠しかったという人もいただろうし、実際にリタイアした人も数人いたようなのですが、私は帰りたくなかったです。ホリデーに行ったら帰りたくないのが普通ですが、それとはちょっと違う感じ。この4日間で得た心の平安、家に戻るとすぐに無くすんだろうなあと思うと、本当に悲しかった。
50人定員のリトリートだったのですが、満員でした。若い20代・30代の人も多かったのがちょっと驚きでした。
本格的なプログラムでした。初日は夕方から始まったのですが、2日目と3日目は、起床6.15分。
6.45 瞑想
7.30 朝食
8.15 労働(掃除や食器洗いなど、振り分けられたもの)
9.30 瞑想
10.15 歩行瞑想
11.00 瞑想
11.45 歩行瞑想
12.30 昼食
14.30 瞑想
15.15 歩行瞑想
16.00 瞑想
16.45 歩行瞑想
17.30 夕食
19.30 瞑想
20.00 講話
20.45 歩行瞑想
21.15 質疑応答
22.00 就寝
4日間で45分(夜の瞑想は30分)の瞑想が17回、歩行瞑想が12回ありました。瞑想は床に座らなくてもいいし、メティテーション・スツール(低い椅子のようなもの)を使ってもいいし、椅子でもよかったです。大半の人は床に座布団かスツールを使って座ってました。45分じっと座っているのは肉体的にも結構苦痛です。私は歩行瞑想の時間にちょこっとヨガをしてストレッチしましたが、そうでない人はどうしてたんでしょう?
45分の瞑想、これはきつかった人もいるだろうし、そうでない人もいたでしょうね。瞑想をする習慣のない人は大変だったんじゃないかと思います。
私は初日の午前中はなかなか集中できませんでしたが、2日目からは落ち着きました。
最終日、午後の最後のセッションの前、居間の椅子に座ってコーヒーを手にじっと外を見て15分ほど座ってました。
ただ何もせず、特に何も考えるでもなく、かといってうとうとしたりぼうっとしてるわけでもなく。このリトリートに来る前は、ただ静かに何もせず座るなんて出来なかったです。
こんな風に、ただじっと何もせず座っている時間。こんな時間は現実に戻るともうやってこないだろうなと思うと、悲しかったです。 たとえ家で一人の自由時間があっても、何もせずに過ごせるなんて贅沢な時間はないです。家事や仕事でないとしても、「本を読まねば」などと思ってしまいます。
ひとつ実際的なこととして実感したことは、デジタルワールドは疲れるということ。家に帰るのがいやなことのひとつは、メールボックスを開けることでした。きっと私はネットの世界で時間を使いすぎなんでしょう。ネットからの情報は必要だし、実際にこのリトリートだってネットで検索したわけなんですが、それでもネットの世界との関わり方を吟味しないとなあと感じました。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
 |
| 二人部屋でした。ルームメートは30歳くらいのとっても静かなまじめにプログラムを守る女性でした。 |
 |
| 寝室からの風景 |
 |
| ベジタリアンの食事が、予想以上にすごくおいしかったです。それでお土産もかねて、レシピ本を買ってきました。参加者女性の大半が買っていました。 |
2018年1月17日水曜日
リトリート
明日から4日間、メディテーション・リトリートに行ってきます。場所はデボンの南なので、家から車で2時間弱の場所です。
瞑想といってもいろいろ宗派ややり方がありますが、ここは上座部仏教の瞑想を取り入れたセンターです。といっても、多分そんなに宗教的なリトリートではなく、教義にこだわりはないんじゃないかなと思います。
が、こだわりがあるのは、これはサイレント・リトリートということ。つまり4日間、喋ることが禁止されています。喋るだけでなく、読書も書くのも禁止。言葉以外のコミュニケーションも禁止です。ワイファイもないし携帯電話も禁止です。
先生のレクチャーはあるので、先生は喋っていいんでしょうね。
友達(ヨガの生徒さん)と3人で行きます。
最初は、「そんな環境、夢見たいにリラックスできるやん。」と乗り気でしたが、先週くらいからちょっと心配になってきました。そしてまた今週からはわくわくしてます。友達と泊りがけでどこかに行くってこと自体が20年ぶりくらいだし。そう思ったら、もっと楽しいイベントじゃなくてリトリートなのが残念なくらい。
一緒に行っても多分部屋も別になるだろうし、おしゃべりすることもできませんからね。でもまあ、友達と行くと何かと心強いことは間違いなし。道中も楽しいし。
って、本末転等か。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
瞑想といってもいろいろ宗派ややり方がありますが、ここは上座部仏教の瞑想を取り入れたセンターです。といっても、多分そんなに宗教的なリトリートではなく、教義にこだわりはないんじゃないかなと思います。
が、こだわりがあるのは、これはサイレント・リトリートということ。つまり4日間、喋ることが禁止されています。喋るだけでなく、読書も書くのも禁止。言葉以外のコミュニケーションも禁止です。ワイファイもないし携帯電話も禁止です。
先生のレクチャーはあるので、先生は喋っていいんでしょうね。
友達(ヨガの生徒さん)と3人で行きます。
最初は、「そんな環境、夢見たいにリラックスできるやん。」と乗り気でしたが、先週くらいからちょっと心配になってきました。そしてまた今週からはわくわくしてます。友達と泊りがけでどこかに行くってこと自体が20年ぶりくらいだし。そう思ったら、もっと楽しいイベントじゃなくてリトリートなのが残念なくらい。
一緒に行っても多分部屋も別になるだろうし、おしゃべりすることもできませんからね。でもまあ、友達と行くと何かと心強いことは間違いなし。道中も楽しいし。
って、本末転等か。
ではこちらもよろしくね

イギリスランキング
登録:
投稿 (Atom)




